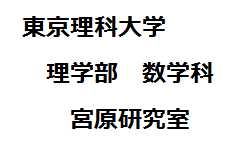歴史の“バトンタッチ”(平成19年浩洋会例会講演)
よく知られているように、世紀の大物理学者アイザック・ニュートン(1642~1727)は、近世物理学の祖とも言うべきガリレオ・ガリレイ(1564~1642)の没年に生まれた。もとより、これは単なる偶然に過ぎないのであるが、我々は、この事実に、あたかも物理学の担い手のバトンがガリレオからニュートンへと手渡されたかのような象徴的な意味合いを感じたくなるのである。このような例はほかにも見られる。例えば、これもまた物理学の二巨人、ジェームズ・マクスウェル(1831~1879)とアルベルト・アインシュタイン(1879~1955)である。また、数学では、ルネサンスの時代に3次方程式の理論に大きな貢献をしたイタリアの二人の数学者シピオーネ・デル・フェッロ(1465~1526)とラファエル・ボンベッリ(1526~1573)のような例がある。前者は3次方程式の解法の最初の発見者であるが、それを公表せずに死んだ。後者は方程式の解として初めて虚数を容認し、虚数の公的認知に端緒を開いた人物である。ちなみに、もう一つ面白い例を挙げると、かのミケランジェロ (1475~1564) の没年とガリレオの生年とは同じなのである。これまた、ルネサンス期から近世への時代の移り変わりを印象づけるものである。上記の例はすべて偶然によるもので、特別な意味はないのであるが、これとは別に、文化や思想や政治などにおいて、歴史的な事柄が、個人や民衆の間で、あるいは国家や王朝の間で、次々に“バトンタッチ”されたかのように、受け継がれていったいろいろな場面を、記録により確認することができる。そのようないくつかの例を本講において述べてみたい。
(1)ギリシア数学
ミレトスのターレス(B.C.620?~550?)に始まるとされる古代ギリシアの数学は、アテネの時代を経て、紀元前3世紀にアレクサンドリアにおいて黄金時代を迎え、この時期には、エウクレイデス(ユークリッド)、アルキメデス、エラトステネス、アポロニオスなど多数の大学者が輩出した。古代ギリシアの数学が存続した期間は非常に長く、紀元5世紀頃にようやく衰退期に入る。7世紀半ばから8世紀始めにかけて、イスラム教徒のアラブ人の軍勢が、アレクサンドリアを始めとする北アフリカのヘレニズム世界を征服し、さらにジブラルタル海峡を渡ってイベリア半島の大部分を占領するに至った。バグダッドを首都とするアラブ人のイスラム帝国は、ギリシア文化特にギリシア科学(数学を含む)を急速に吸収していった。ギリシア科学はギリシア世界からイスラム世界へと“バトンタッチ”されたのである。そうして、8世紀から9世紀にかけて、イスラム帝国はその極盛期を迎え、華やかなイスラム文化が咲き誇った。特に、9世紀はアラブの数学の栄光の世紀であった。アラブ人は、ギリシア人から受け継いだ数学を、インドの数学の影響も受けながら、さらに大きく発展させたのである。しかし、11世紀末期以後、さしもの大帝国も、セルジュク・トルコやヨーロッパの十字軍の侵略を受け、次第に衰退していった。
当時のヨーロッパの文化的水準は依然として低く、イスラム世界とは比較にならなかった。12世紀になって、中世の暗黒時代の眠りからようやく目覚めかけたヨーロッパ人は、スペインに居座っていたイスラム教徒から高度な学問を学び始めた。彼らはアラビア語の数学・科学の書物をラテン語に翻訳することから出発したのである。
陽光が射し始めたこの時代は「12世紀ルネサンス」と呼ばれている。13世紀に入るとヨーロッパにも独創的な数学者が現れ始め、14世紀にはルネサンスの時代を迎える。古典復興の気運に乗り、数学や科学においても、アラビア語を通じてではなく、ギリシアの古典から直接に翻訳を行うようになった。こうして、アラブの数学・科学はヨーロッパ人に完全に“バトンタッチ”されたのである。それ以後、ヨーロッパは、飛躍的な文化の発達を遂げ、17~18世紀の数学・科学革命から現代に至るまで、一度も停滞することなく発展を続けてきたのである。(この項目の要旨は、平成17年の浩洋会例会の講演「ギリシア数学概観」の内容と同じであるので、詳しく述べることはしなかった。)
(2)王家の系譜
ヨーロッパにおける諸王国の王の系譜には二種類のタイプがある。第一のタイプは血縁を重んずるもので、父から子へ、さらに孫へと譲位してゆくのを原則とし、それが不可能になった時は、血筋のつながる他の系列の者を選ぶというものである。第二のタイプは、血縁をあまり重視せず、派閥の勢力や人物の能力、人格などを考慮し、選挙や推薦などによって次の王を決めるというものである。第一のタイプが圧倒的に多いが、第一と第二のタイプが混在する場合もあり、時には、クーデターや暗殺などにより流れが乱されることもあった。このように、王位を次代の者に譲り渡してゆくことを、本講のテーマである“バトンタッチ”と見なし、これについて考えてみよう。
現在のヨーロッパは39か国から成り立っているが、そのうち、王国は、イギリス、スペイン、オランダ、ベルギー、スウェーデン、デンマーク、ノールウェーの7か国、公国は、アンドラ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、モナコの4か国で、これらに準ずるものとしてヴァティカン市国がある。これら以外の国はすべて共和国である。かつては、フランス、オーストリア、ドイツ、イタリア、ギリシアも王国ないし帝国であった。現在の王国、公国の王位、爵位の継承の仕方は昔からほとんどすべて第一のタイプを守り続けたものであるが、ヴァティカン市国だけは、その元首ローマ教皇を決める方法は第二のタイプである。
それでは、古代、中世にまで遡って、当時の王国や帝国の状況はどうであったか見てみよう。まず、ローマ帝国は、東西に分裂する前は、ほとんど第二のタイプであった。例えば、ローマが最も平和であった五賢帝時代(1世紀末からおよそ80年間)を見ればよい。それは、現皇帝が自己の後継者に相応しいと見極めた人物を次期皇帝に指名し、それが守られた時代であった。もちろん、父から子へと譲位した例もいくつかあるが、ほとんどその代限りの相続で終わった。ローマの国境が蛮族に脅かされるような時代になると、蛮族撃退に功のあった将軍が皇帝に推される場合が多かった。他方、分裂後の東ローマ帝国の皇帝たちの幾人かの運命は悲惨であった。朝廷には権謀術数がはびこり、暗殺されたり、処刑(斬首、四つ裂きなど)された皇帝が非常に多かった。このようにむごい方法で、皇帝位の“バトンタッチ”が行われたのである。西暦476年の西ローマ帝国滅亡後、西ヨーロッパにはいくつかの王国が建国されたが、それら諸王国のその後の興隆衰亡の歴史は極めて複雑であって、離合集散を繰り返し、紆余曲折の結果、現在のヨーロッパ諸国が形成されたのである。
さて、それでは、古代から現代までに存在したヨーロッパ諸王朝のうち、第一のタイプで、すなわち血縁を保ちながら、最も長い期間続いた、あるいは続いているものは、どこの国の王朝であろうか? それはイギリスである、という意見が多いと思う。そこで、イギリスの現女王エリザベス2世の系譜を遡ってみよう。すると、この系図はかなり込み入っていて、途中に何人も女王でない女性が現れてくるのである。すなわち、イギリスの王家は、王もしくは女王の候補者が絶えた時に、他家へ嫁した王女の子孫を自家の王として迎えるということを何回か行っていて、現女王はその子孫なのである。(筆者の調べたところでは、4回行われている。)このような仕方で、血筋が守られてきたのであるが、これは王位継承の原則から言って大きな弱点である。従って、過去に、ハノーヴァー朝の祖ジョージ1世(在位1714~1727)も、チューダー朝の祖ヘンリー7世(在位1485~1509)も、この点において王位継承の資格に疑義が持たれ、反対者が多かったという。スチュアート朝、プランタジネット朝それぞれの祖ジェームズ1世(在位1603~1625)、ヘンリー2世(在位1154~1189)も同様の状況であった。ちなみに、ジョージ1世はドイツ人、ジェームズ1世はスコットランド人、ヘンリー2世はフランス人であった。けれども、このように女系を通じてであっても血筋のつながりは事実であるから、さらに系図を遡ってゆくと、何と驚くべきことに、現女王の血のつながった祖先として、829年にイングランドを統一しアングロ・サクソン王国を建国したエグバート王に辿り着くのである。しかしながら、いかに血統が続いていようとも、アングロ・サクソン王朝を現在のイギリス王朝の祖先と考えることはできない。なぜならば、アングロ・サクソン王朝は、1066年にノルマン王朝を興したウィリアム1世(在位1066~1087)に滅ぼされたからである。現在のイギリス王朝は、このウィリアム1世を始祖として持つものであって、従って940年ほどの歴史を有することになる。
次に、フランスの場合はどうであろうか。フランスの王朝は、有力な封建諸侯であったパリ伯ユーグ・カペー(在位987~996)に始まる。1328年、カペー家の男系が絶え、同家の傍系ヴァロワ家に王位が移った。1589年、ヴァロワ家の男系が絶え、今度は王位は、カペー家の王であったルイ9世 (在位1226~1270) の末の息子の直系であるブルボン家に移った。同家からは太陽王ルイ14世(在位1643~1715)が現れ、その当時、フランスの宮廷はヨーロッパ随一の隆盛の時代を謳歌した。けれども、国民無視の統治が長く続いた挙句、1789年フランス革命が勃発し、ルイ14世よりわずか2代後の王ルイ16世(在位1774~1792)は、王妃ともども処刑されるという憂き目を見たのである。後年、ルイ16世の弟と、傍系のルイ・フィリップが、ブルボン王朝を再興するが、1848年をもって同王朝はその幕を閉じることになった。かくして、ユーグ・カペー以来、フランスの王朝はおよそ840年続いたことになるが、これは明らかにイギリスの王朝の歴史より100年ほど短い。しかし、フランスの場合、ヴァロワ、ブルボン両家は、ともにカペー家の直接の男系の子孫であり、しかも、この三つの王朝はすべて男系を通したのである。そして、もう一つ忘れてはならないことがある。1700年、それまで200年ほど続いていたスペインのハプスブルク王朝が断絶した際に、後継をめぐってスペイン継承戦争が起こったが、ルイ14世率いるフランスが最終的に勝利し、その孫フェリペ5世 (在位1701~1746) をスペイン王の座に据えることに成功した。すなわち、フランスのブルボン朝がスペインに移植されたのである。それ以来300年余り、スペイン・ブルボン家は直系をもって今日まで 続いている。従って、カペー家より始まり、ヴァロワ、ブルボン、スペイン・ブルボンの順に続き、ほとんどすべて男系をもって連なる王朝(スペイン・ブルボン朝には女王が一人だけいる)は、合計1020年の歴史を持つことになる。こうしてみると、単独の国で最も長く続いた王朝を持っているのはイギリスであるということになるが、イギリスの場合は女系を通じて何度も他家から王を譲り受けているという欠点があり、他方、フランスの場合は、常に男系を連ねており、血脈の薄い他家から王を迎えたことは一度もないという長所がある。しかも、フランスのブルボン朝は、スペインのブルボン朝へと男系の血統を移しており、それは現在まで続いているのである。それゆえ、国を無視して、イギリスの王朝とフランス・スペインの王朝との継続期間の長さを争うリレー競争を考えると、フランス・スペインに軍配が上がることになるのである。
(3)帝国理念
広大な領土を有したローマ帝国も、西暦395年には完全に東西に分裂した。この後、東ローマ帝国はさらに1000年以上を生き長らえるのであるが、西ローマ帝国は、北方の蛮族の侵攻に耐え切れず、476年には終に滅亡した。大挙して西ヨーロッパに侵入したゲルマン諸族が新たに建設した諸王国のうちで、最も強力であったのはフランク王国であった。486年に始まり約500年に及ぶこの国の歴史はちょうど半分に区分される。すなわち、建国より二百数十年後、当時宮宰を務めていたピピンなる実力者が、ローマ教皇と結託して、王位を簒奪し、王朝が代わったのである。これがメロヴィング王朝からカロリング王朝への“バトンタッチ”であった。ピピンも“遣り手”であったが、カロリング王朝の2代目の王カール(ピピンの子)はさらに大人物であった。彼は、イベリア半島を除くヨーロッパの大部分を征服し、かつての西ローマ帝国に匹敵するほどの広い領土を支配した。当時、隣国の侵略に悩まされていたローマ教皇は、カール王に援助を依頼し、その代償として彼に皇帝の位を与えた。西暦800年のことである。かくして、フランク王国は「フランク帝国」となり、後にカールは「大帝」と呼ばれるようになった。それは、「西ローマ帝国の復活」と見なされ、東ローマ帝国と並び立つ国家となった。カールの側近アルクインのカール宛の書簡が残っているが、その中で彼は、「キリスト教帝国」という表現を用いて、この帝国のためにカールが強い指導力を発揮することを望んでいる。アルクインが持っていた、キリスト教を基盤とするこの帝国の構想には、一つの政治的・宗教的統一体という画期的な理念が窺えるが、それを実現しようとしたカールの国家は、「ヨーロッパ世界」の誕生とも言われている。けれども、甚だ不幸なことに、この高邁な理想はカール大帝の死(814年)の後に消え去った。カールの大帝国は、その子と孫たちによる激しい後継者争いの結果、843年には、西フランク王国、中フランク王国、東フランク王国の三つに分裂したのである。(ごく単純に言えば、これら三国が後にそれぞれ、フランス、イタリア、ドイツになるのである。)
カロリング王朝が断絶した後、やがて恐ろしい「暗黒の10世紀」がやって来る。ヨーロッパは、北からはヴァイキングの、南からはアラブ人(イスラム教徒)の、東からはマジャール族(ハンガリア人)の、長期にわたり頻繁に繰り返される襲撃によってこの上なく苦しめられた。他方、イタリアでは、万人の模範たるべきローマ教皇庁が堕落を極め、特定の一族による、乱脈な、いわゆる「娼婦政治」がはびこった。このような乱世に、東フランク王国(ドイツ王国)の王であったオットー1世 (在位936~973) は、大挙して侵入を企てたマジャール族を決定的に打ち破って、完全に服従させた。この勝利がオットーの名望を著しく高め、彼は、カール大帝と同じように、西方キリスト教世界の指導者としての支配、統治に努めたのである。当時、イタリア王によるローマ教皇領への度重なる侵入に耐えかねた教皇は、オットーにローマ遠征を懇請した。オットーは、大軍を率いてアルプスを越え、イタリア王を臣従せしめて教皇領の安堵を約束したのである。その褒賞として、962年、教皇はオットーに皇帝冠を授与した。オットーの皇帝権は、カール大帝に始まったローマ的皇帝権を継承するものであり、ここに 「神聖ローマ帝国(ドイツ帝国)」 の発祥の起源がある。
オットーの後継者たち、オットー2世および3世も皇帝位を獲得し、彼らは、アルプスの北と南の王国を一つに融合し、ローマの地を支配の中心とする帝国を創り上げようという政治理念を実現することに専念した。この理念は、かつての栄光の大ローマ帝国を復活、再現させようというものであり、オットー3世に至っては、ローマのパラティーノの丘に宮殿を建造し、それを住居としていたほどであった。しかし、オットー3世の長期の滞在と統治をローマ人は決して歓迎せず、1001年にはローマ貴族たちの反乱が勃発した。やむなくローマから脱出したオットーは、その後間もなく、ローマ奪還に向け遠征中に病死した。21歳の若さであった。この時代に、かようなローマ帝国復活を目指す「帝国理念」が芽生えたのであるが、以後、神聖ローマ帝国の歴代の皇帝たちの多くが、この理念にとりつかれ、帝位獲得のため、あるいはイタリア征服を夢見て、アルプスを越えた。当然、ドイツ本国の統治はおろそかになり、さらに、皇帝は軍費提供の見返りにドイツの諸侯や都市に様々な特権を与えたため、諸侯や都市の勢力の増大をもたらし、国内に多数の領邦や都市の割拠を許容するという事態を招いた。こうして、ドイツは、隣国のフランスのように一つの国に統一されることなく、この分裂状態は19世紀末まで続くことになったのである。これもひとえに、ドイツが皇帝の座という「重荷」を常に背負っていたがゆえの結果であった。
この「帝国理念」が、ローマ帝国の本家たるイタリアではなく、ドイツに発生したということは、一見奇妙に思えるが、強大な軍事力をもって創り上げたカール大帝やオットー大帝(1世)の帝国にその起源があることを考えると、当然と言ってよいのである。大ローマ帝国が消え去って以来、ヨーロッパの人々は常にかの輝かしい大帝国の再興を夢見てきた。それを達成する可能性があるのは、軍事力に優れたドイツ民族しかいなかったのである。11世紀には、ドイツの人々の意識の中で、「帝国理念」は具体的な形をとり始めた。例えば、ドイツ語で書かれた最初の歴史物語「アンノの歌」 (1080年頃書かれた作者不詳の詩作) においては、ローマの英雄カエサル(シーザー)が、ドイツ人と同盟してローマの元老院議員を追放し、皇帝となって以来、ドイツ人はローマにおいて愛され尊敬されていた、と歌われているのである。(もちろん、これは事実ではなく歴史の捏造であるが。)そして、ドイツ人は、そのような経緯からして、帝位に対する請求権を持つのだ、と暗に主張しているのである。また、それより少し前、司教ブレーメンのアダムは、当時の皇帝ハインリヒ3世を、ローマの初代皇帝アウグストゥス以来90代目の後継者であると、年代記に記した。以後、この数え方が引き継がれ、1100年頃の年代記の中で、それまでのすべての皇帝にまで拡げて体系化されたのである。
オットー朝以来、「帝国理念」という“バトン”を受けた諸皇帝の多くが、その理念実現のために、多大の労力と資金を費やし、イタリアに遠征した。従って、イタリアはしばしば戦場となったが、イタリアの諸都市や教皇、司教たちは頑強に抵抗した。他方、皇帝に与する諸侯や都市もあり、人々は皇帝派(ギベリーニ)と教皇派(グエルフィ) に分かれて激しく戦った。今もなお語り草となっている名高い二人の皇帝フリードリヒ1世(在位1152~1190)とその孫フリードリヒ2世(在位1215~1250)の起こした数々の熾烈な戦いに代表されるように、オットー3世以後およそ250年にわたる期間、皇帝が代替わりする度に、何度もイタリアを舞台とする戦闘が行われた。けれども、結局は、諸皇帝のイタリア征服の夢は実現せず、すべて失敗に終わったのである。しかしながら、神聖ローマ帝国は長く存続し、「帝国理念」は皇帝から皇帝へと“バトンタッチ”されて生き続けた。それゆえ、長い間、実質的にはともかく、帝国は、名目上はイタリアを自己の領土に所属するものと見なし続けていたのであるが、15世紀末頃にはそのような考えも通用しなくなった。けれども、ハプスブルク家の傑出した二人の皇帝マクシミリアン1世(在位1493~1519)とその孫カール5世 (在位1519~1556) は、ともにかつての神聖ローマ帝国の権威を取り戻そうと真剣に努力した。そのため、彼らの生涯は戦いに明け暮れたのであった。カール5世の時代には宗教改革が起こり、マルティン・ルターを支持するプロテスタントの思想が諸侯の間にも広がっていった。カールは、彼らとの戦闘には勝利したものの、最終的には信仰の自由を認めざるを得ず、彼が追い求めていたキリスト教国家の大連合という目的は遂に達成することができなかった。そして、17世紀半ば、新旧両教徒の争いに端を発する30年戦争に敗れた神聖ローマ帝国は、ドイツ諸邦の主権を認めることを余儀なくされ、事実上崩壊した。けれども、「神聖ローマ帝国」の名義だけは辛うじて残されたのである。
全ヨーロッパ制覇という大それた野望を持っていたナポレオン・ボナパルト(1769~1821) は、数々の戦いに勝利した後、1804年、突如として皇帝に即位した。これは途方もない行為であった。人々の間には、皇帝というものは、古くはローマ皇帝、そしてカール大帝やオットー大帝の流れを汲むものであるという固定観念があった。ナポレオンはそれをいとも簡単に打ち破った。彼もまた、分不相応にも、「帝国理念」にとりつかれてしまったのである。1805年、皇帝ナポレオンは、神聖ローマ皇帝とロシア皇帝を相手に戦い(アウステルリッツの三帝会戦)、これに圧勝した。その勢いを駆って、翌年、彼は「フランス帝国」の保護の下にライン同盟を組織し、ここに、わずかに命脈を保っていた神聖ローマ帝国は、終に完全に消滅したのである。その後、さしものナポレオンも、1815年、ワーテルローの戦いに敗北を喫し、わずか11年で栄光の「帝国」は消え去った。その後、ドイツにおいては国民運動が活発になり、その一つの目標が、分立していた諸邦を統一することであった。しかし、国民の多様な主義主張、急進派の革命運動、複雑な民族問題などにより国内は非常に混乱した。そして、統一ドイツの国家像は、プロイセン王国の宰相オットー・ビスマルクの主導により、ハプスブルク家のオーストリアを除外する形で形成されていったが、遂に、1871年、プロイセン王を皇帝とする「ドイツ帝国」が誕生した。ところが、20世紀に入って間もなく、第1次世界大戦が始まり、これに敗れたドイツ帝国は、1918年、建国後わずか50年足らずにして崩壊したのである。戦後、巨額の賠償金の支払いに苦しんだドイツにおいて、種々の勢力の中から台頭してきたのがナチ党であり、その党首アドルフ・ヒットラー(1889~1945) は1933年に念願の政権を獲得した。ドイツ民族の優秀性なる観念に毒され、「世界に冠たるドイツ」を標榜して、第2次世界大戦を引き起こしたヒットラーも、時代錯誤の「帝国理念」にとりつかれた一人である。彼の究極の目的は全世界制覇であったであろう。自ら皇帝気取りで、ドイツを、かつての「神聖ローマ帝国」および「ドイツ帝国」に次ぐ「第三帝国」と称したのである。「千年帝国」などと誇ってもいたが、この「帝国」は1000年どころかわずか12年で滅び去った。しかし、この短い期間に、この邪悪な「帝国」はヨーロッパ中にこの上なく大きな破壊と悲劇をもたらし、未だにその傷は完全には癒えていない。古代から現代に至るまで、「帝国理念」なるものは、良きにつけ悪しきにつけ、世界の歴史に極めて大きな影響を与え続けてきたことを痛感させられるのである。
(平成19年11月記す)