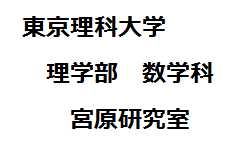物語 「メロヴィング王朝の歴史」
西暦6世紀末期に書かれた「10巻の歴史」という書物がある。作者は、フランスの都市トゥールの司教であったゲオルギウス・フロレンティウス・グレゴリウス(c.540~c.590) という人物である。通常、トゥールのグレゴリウスと称されている。彼はこの書に題名をつけなかったが、後世の訳者が上記のように名づけたものであり、「歴史十書」とも「フランク史」とも呼ばれている。これは、5世紀末、西ローマ帝国滅亡直後に建国された、現在のフランス国の前身と考えられる「フランク王国」の歴史や政治そして社会の状況などについて、作者が生きていた時代に見聞きしたことを淡々と綴ったものである。彼がこの書をいかなる意図で書いたのか、断定的なことは言えない。彼がこれを歴史書あるいは年代記として書いたのか、また、他人に読まれることを意識していたのか、あるいは、自身のためだけの手記として残したのかはっきりしないのである。これは、もちろんラテン語で書かれているが、もう30年以上も前に、日本語への対訳書が出版されている。それは、左頁にラテン語、右頁に日本語訳を載せた、専門の研究者にはとても便利な、箱入りの大部の書物で、2巻に分かれている。この本を一読しての筆者の感想は、その内容についてはさておき、何と粗悪で拙劣な文章だろうかということであった。その原因は、訳文が悪いということではなく、そもそも原文の質があまり良くないことにあるように思われる。用語が適切でなかったり、単純過ぎる表現が多かったり、また、唐突に話題が変わったり、読んでいて非常に違和感を覚えたのである。作者のグレゴリウスは、ローマ帝国の時代から続く、誇り高い元老院貴族の家柄の出身であって、当時の最高の知識階級に属していた。だが、ちょうどその頃あるいはそれ以前から、格調高い古典ラテン語が崩れ始めていて、一流の知識人のグレゴリウスでさえもが、粗雑なラテン語を用いており、自身もそれを認めていたという。その上、彼の文章の表現の仕方や言い回しにもお粗末なところがかなりあるように思われ、それは、たぶん、彼が、他人に読まれることを考慮せず、気取らずにこの手記を書いていたためでもあるだろう。むろん、古い時代のものを現代の感覚だけで理解しようとすることは正しくないだろうし、ラテン語を知らない筆者がこのようなことを言うのは、甚だ無責任であり僭越極まることかも知れない。けれども、この対訳書を読むとき、日本語の文章としてそぐわない表現がしばしば見受けられるのは、おそらく、訳者がもともと良質とは言えない原文の逐語訳あるいは直訳を試みておられたからであろう、と推測している。内容が面白いだけに、もっと自然な分かりやすい意訳をして下さればよかったのにと、筆者は始めはとても不満に思っていた。しかし、仮に、この書物を流麗な読みやすい文章に意訳したとすれば、原著の持つ雰囲気が大きく失われることにもなりかねず、また別の問題が生ずるであろう。従って、原文の持ち味を日本語で忠実に再現するためには、この翻訳は妥当なものであったのだと今は思っている。そして、一昨年、別の訳者によるこの書の新訳(対訳書ではない)が出版された。早速ひもといてみたが、こちらの方が、言葉遣いがより適切かつ現代的で、読みやすいように感じられる。
フランク王国初期の時代については史料が極めて少ないので、歴史家にとってこの「10巻の歴史」はこの上なく貴重なものであり、当時の政治や社会の状況を知る上で、質量ともに第一級の史料とされている。文学作品としては欠点だらけであるが、中世初期の乱世をこれほど具体的に生き生きと物語った資料は他になく、一般の世界史年表にも記載されているほどである。この時代に関する他の文献として、7世紀にフレデガリウスという人物が記述した「年代記」が存在するが、これは、内容が伝承的で具体性に乏しく、史料としての価値はグレゴリウスのものより低いと言われている。 また、「10巻の歴史」を典拠として、19世紀半ばに、フランスの歴史家オーギュスタン・ティエリは、興味深い歴史物語を著した。その日本語訳が「メロヴィング王朝史話(小島輝正訳)上・下巻 」として岩波文庫より出ている。これは、原典で扱っているほど長い期間にわたるものではないが、フランク王国内で起こった様々の事件を七つの完結した話として語ったものである。グレゴリウスの原典あるいはティエリの物語は、史書としても読物としても大変面白いものなので、ここで筆者の関心を引いた部分を抜粋し紹介してみようと思う。ちなみに、これから述べる物語の時代は、日本においては、いわゆる飛鳥文化、白鳳文化が栄えた頃であって、仏教が伝来し、聖徳太子が活躍した時期に当たる。これらの書物において次々に繰り広げられる殺伐な時代の血腥い悲劇を読むとき、平和な社会に生きている我々は、かくも野蛮で道徳の退廃した時代があったのかと嘆息を禁じ得ないであろう。(参考文献1,2,3,4,11)
1. フランク王国
ローマ帝国の北方の国境は、大雑把に言って、ライン河とドナウ河であった。紀元前の時代から、この両河の向こう側に住んでいたゲルマン諸族が、河を渡って領内に侵入し、帝国を脅かしていたが、紀元3~4世紀にはいよいよそれが激しくなり、歴代のローマ皇帝は、国境の警戒と彼らの駆逐に全精力を費やさざるを得なかった。大きくなり過ぎていた帝国は、3世紀末以来、防衛上、政治上の理由から、四つに区分されていたが、395年には、完全に東西に分裂し、二人の皇帝がそれぞれ独立に統治することになった。大挙して押し寄せて来るゲルマン人に手を焼いた帝国は、ついに彼らを受け入れ、領内に定住させることにした。ところが、彼らのうち、いくつかの部族は、西ローマ帝国の無力さにつけこんで、領内に王国を形成し始めた。 北西スペインのスウェビ王国(411年)、南ガリアの西ゴート王国(418年)、北アフリカのヴァンダル王国(429年)、ローヌ川上流のブルグンド王国(443年)などである。東ローマ帝国と違って、財政的に困窮し、また、凡庸な皇帝が多かった西ローマ帝国は、遂に476年に力尽きて滅亡した。その後、旧帝国領内には、ガリア北部にフランク王国(486年)、イタリアに東ゴート王国(493年)が建国された。このように、旧西ローマ帝国領内に分立した諸王国の中で、最も注目すべきはフランク王国である。なぜなら、この王国は、やがて、西ゴート王国を遠くスペインにまで追いやり、さらにブルグンド王国をも併合し、ほとんど現在のフランス国全土に匹敵する広大な領土を有する恐るべき強国となったからである。そして、この国は、諸王国の中で最も長続きし、400年を越える歴史をもつことになるのであるが、後代のヨーロッパ世界の基礎を築く国に成長してゆくのである。
帝国に侵入した諸部族のそれぞれは、単一の部族ではなく、いくつかの大部族、小部族が集まって形成された集団であった。フランク族の場合、それは、北海沿岸に居住していた「サリー族」とライン河下流域に居住していた「リプアリア族」およびその他の雑多な小部族を合わせた集合体の総称であった。フランク族と他の部族を比較するとき、最も顕著なことは、彼らがそれぞれ建国するまでに移動した距離の大きな違いである。例えば、ヴァンダル族の故郷は現在のドイツ東部であり、彼らはその地からはるばると南下、スペインを縦断し、さらにジブラルタル海を渡って、北アフリカに辿り着き、そこに王国を建てた。また、東西ゴート族の発祥の地はバルト海沿岸地方であったが、東方のドニエプル河を越えた地域にまで移動し、さらにバルカン半島を南端に至るまで迂回した後に、イタリアあるいは南ガリアへと向かい、定住した。それに対してフランク族は、ライン河に接する地域、現在のオランダ、ベルギー、ドイツ、フランスにまたがる地域に建国したのであるから、彼らの居住地から河を越えただけの場所に移住したに過ぎないのである。従って、彼らが移動に際して要したエネルギーは最小ですんだし、国を維持するために必要な人員を彼らの故地から補充することも容易であった。さらに、極めて重要なことであるが、フランク王国にとって地理的に有利であった事由がもう一つある。それは、この王国が東ローマ帝国から非常な遠隔の地にあったということである。東ローマ帝国は、西ローマ帝国が消滅した後も、産業や交易によって栄え、経済的に極めて豊かであったこと、また、優れた皇帝が現れたことなどの理由から、地中海世界最強の大帝国であり続け、新興の諸王国は常に帝国のご機嫌と鼻息を窺っていなければならなかった。後年、ヴァンダル、東ゴート両王国は帝国への対処を誤り、帝国に攻め滅ぼされてしまった。それぞれ、534年、553年のことであり、北アフリカとイタリアは再び帝国の領土となった。また、西ゴート王国も、554年、内紛に乗じた帝国に、アンダルシア地方を奪い取られることになったのである。ところが、フランク王国は帝国から極めて遠い位置にあったため、帝国はこれに手を出すことが全くできず、同王国は、その勢力増大に伴い、帝国に一目置かれる強国に成長していった。(参考文献6,7,8,14)
2. メロヴィング王朝
フランク王国を建設(486年)したのは、サリー族の出身で、15歳にして王となり、英主と謳われているクロヴィスであった。彼の祖父メロヴィクは、451年、アッティラ率いるフン族とローマ連合軍との戦いにおいて、ローマ側に味方して参戦し、勇名をとどろかせたのを契機としてフランク族統合を果たしたと伝えられている。その子キルデリック王の時代には、既に王という名称が史料に現れ、名実ともに王の地位は確保されていた。彼は元テューリンゲン王妃と結婚し、その間に生まれたのがクロヴィスであった。クロヴィスは統率力と実行力に優れた王ではあったが、狡知と残虐さを兼ね備えていた。奸策を巡らし、親族を討つことも平気であった。彼は、フランク王国の軍事力を強化し、ガリアにおけるローマ人の最後の拠点であったシアグリウスの国、西ゴート王国、アレマンネン王国を打ち破り、広大な領土を獲得した。彼に始まるフランクの王朝は、サリー族の祖と考えられるメロヴィクに因んで、「メロヴィング王朝」と呼ばれている。クロヴィスはブルグンド王女クロティルドを娶った。彼女は熱心なキリスト教徒であったが、王子インゴメルの夭折をきっかけに、夫に異教からの改宗を強く勧誘したと想像される。496年、クロヴィスは、3000人のフランク兵士とともにキリスト教に入信し、洗礼を受けたのである。当時、キリスト教は、神とキリストは同質であるとするアタナシウス派と、そうではないとするアリウス派に分裂していた。既に、ニケーア公会議(325年)において、アタナシウス派がキリスト教の正統(カトリック)であると認定されていたが、異端と見なされたアリウス派の勢力は根強く残り、ゲルマン諸国の多くはこれを信奉していた。正統派のキリスト教会は、アリウス派に対抗して、教会の組織化を目指し、布教に邁進するとともに、できればゲルマン諸国の王室に入り込み、政治的にも発言権を得ようとする機会を探していたので、教会側からもクロヴィス王に対し改宗を勧める強い働きかけがあったと推測される。クロヴィスの方にも、国家の勢力増強のために、正統派の教会と連携をとることによって一つの共同体を形成し、他国への遠征や合併の正当化を得るという期待があって、キリスト教正統派への入信を決意したものと思われる。
511年、クロヴィスが45歳で没すると、この部族古来の伝統に従って、フランク王国の領土は四人の息子テウデリク、クロドメル、キルデベルト、クロタールに分け与えられた。長男のテウデリクはクロタールとともにテューリンゲン族を討ち、さらにブルグンドやバイエルンをも支配下に置き、530年代には、王国全体の版図はクロヴィス王の時代よりもさらに拡大した。一方、クロドメルは戦いのさなかに騙し討ちに会い戦死したが、彼には幼い二人の息子がいた。腹黒いキルデベルトとクロタールは、兄クロドメルの領土を奪い「山分け」しようと企み、この10歳と7歳の甥二人をおびき寄せて、「死にたくない、助けて」と泣き叫ぶ二人を自らの手で刺し殺したのである。ところが、キルデベルトには男子がなく、テウデリクの方も孫の代になって男子がいなくなり、結局、クロタール以外の分王国の男系が絶えたために、558年、フランク王国はクロタール(1世)によって再び統一された。しかし、わずか3年後にこの王が死ぬと、またもや王国は四人の息子カリベルト、グントラム、シギベルト、キルペリクにより分割統治されることとなった。ところが、長兄カリベルトが早世したために、567年からは、三つの王国が分立することになった。次男グントラムは「ブルグンディア」(現在のフランス南東部)を、三男シギベルトは「アウストラシア」(同北東部)を、末子キルペリクは「ネウストリア」(同北西部)を治め、同時に、アキタニア(同南西部)を複雑に区分した所領として三者が分け合うという取り決めがなされたのである。これら三分王国の首都は、順に、オルレアン、メッツ、パリであった。その後、このような三分王国体制が平和裏に進行した訳ではなかった。血族間の感情的な対立や怨恨、欲望や所領争いに、諸地域に根を張る貴族や豪族の政治的な思惑が絡み、それらが原因となってことごとに激しい不和、内訌を引き起こした。宮廷内に陰謀がはびこり、血の惨劇が繰り返されたこの時代の悪逆無道ぶりは、他の時代に類例を見ないものである。(参考文献1,2,3,5)
3. 西ゴート王国の王女たち
三人の王のうち、末子のキルペリクは、父親譲りの好色家で素行が収まらず、王妃や側妾の数が最も多かった。最初の王妃は、彼の側仕えの女たちの中から選ばれたアウドヴェラであった。彼女は、人の良い単純な性格で、思慮が足りない女であった。彼女の侍女の中に、名をフレデグンドというフランク人の若い娘がいた。彼女は、奴隷上がりの身分であったが、たぐい稀なる美貌の持主で、大きな野心を抱き、極めて奸智に長けていた。ティエリは、「フレデグンドは、善悪の観念のない、原初的野蛮人の典型である」と言っている。フレデグンドは、秘かに姦策をめぐらして王妃を陥れ、王が彼女を離別するように仕向けたが、浅はかな王はその悪巧みにまんまと乗せられ、王妃を、生まれたばかりの娘ともども、ル・マンの修道院へ追放してしまった。そして、フレデグンドの容姿の美しさにすっかり惑わされたキルペリク王は、彼女を王妃として迎えることにしたのである。
一方、シギベルトは、キルペリクに比べると、より高潔な王で、自分の結婚についても、王族の出身の娘を選ぶことを心に決めていた。その頃、スペインの西ゴート王アタナギルドに二人の娘があり、年下のブルンヒルドはつとにその美貌をもって知られていた。彼女は、挙措優美で、王女としての威儀と典雅さを兼ね備え、その上、思慮深い性格であった。シギベルトは、使者に多大の贈り物を持たせて、スペインへ遣わし、彼女に求婚した。アタナギルド王は喜んでこれに応じ、莫大な財産とともに娘をアウストラシアへ送り出した。この上なく豪華な婚儀と祝宴がとり行われ、首都メッツは歓喜に沸き立った。これを知ったキルペリクは、自分が妻や側妾にした幾人かの身分の低い女たちがつまらない存在に思えてきて、兄の高貴で盛大な結婚に非常な羨望を覚えた。そこで、彼は、アタナギルド王に使節を派遣し、ブルンヒルドの姉ガルスヴィントとの婚姻を申し入れたのである。ところが、キルペリク王の乱行の噂はスペインにまで届いていたので、ガルスヴィント本人も母ゴイスヴィントもこの縁談を非常に嫌がった。父王は決心しかね、言を左右にして返事を延ばし続けたが、使者に迫られ、やむなく、キルペリクが王妃側妾のすべてを離別し、新婦に生涯添い遂げることを誓文をもって約束しない限り、この話には応じられないと返答した。直ちに急使がネウストリアに向け出発し、やがてキルペリク王の誓文を持って帰って来た。しかも、彼は、結婚の贈り物として、所有していたリモージュ、カオール、ボルドーなどのアキテーヌの諸都市をその周辺地域とともに、ガルスヴィントに贈ることを約束した。このように豪勢な贈り物と将来の政治的利益の大きさを考え、とうとう西ゴート王はネウストリア王と娘の婚姻を承諾したのである。
母と娘は、別れの悲しみと行く末の不安から、毎日を泣き暮らした。結婚の豪華な支度が整えられ、ついに親子の別離の日が来た。随行の家臣や馬車や荷車から成るえんえんたる婚礼の隊列が、西ゴート王国の首都トレドを出発し、北方へと向かった。母は見送りのため行列に加わったが、名残を惜しみ、娘の馬車に乗り込んだ。そして、一向に降りようとせず、別離の時を一日また一日と先へ延ばし続けた。とうとう山々が近づき、道が険しくなってきたので、供奉の家臣たちに強く説得され、ようやく母は馬車を降りた。母は道端に立ち尽し、娘の行列をそれが彼方に消え去るまで見送った。これが二人の今生の別れとなったのである。婚礼の行列は峻険なピレネーの峠を越え、ナルボンヌ、カルカソンヌを経て、ポワティエ、トゥールを通って、セーヌ河の河口にほど近いルーアンの町へと向かった。婚姻の祝典はルーアンで行われることになっていた。当時のルーアンは水上交易の要衝であり、ネウストリア分王国の首都パリと並んで非常に重要な都市であった。キルペリクとガルスヴィントの婚儀は、シギベルトとブルンヒルドのそれと同じくらい盛大に行われた。その儀式において、キルペリクはガルスヴィントとの永遠に変わらぬ夫婦の神聖な誓いを行った。そして、彼は、アタナギルド王に渡した誓文の通りに、妻を離別し、側妾たちに暇を出した。妻のフレデグンドは、そのような仕打ちに冷静に応じたが、自分を元の侍女として宮廷に置いてくれるように懇願し、それは許された。新婚生活は初めのうちは平穏無事に過ぎていったが、そのうちに、何事にも飽きやすいキルペリクは、新妻に対して愛情を感じなくなり、ただ倦怠感だけを持つようになっていった。そのような時がいつか来ると見抜いていたフレデグンドは、それを辛抱強く待っていたのである。ある日、偶然のように装い、彼女は王の前にその姿を現し、微笑みながらうやうやしくお辞儀をした。それを見た王は、またもや彼女の美しさに心を奪われてしまった。彼女は再び王の側妾となり、その寵愛をよいことに、王妃をないがしろにし、軽蔑するような振舞いをたびたび見せるようになった。怒ったガルスヴィントは、王に激しく不満を言い、自分を離別して国へ帰して貰いたいとしきりに頼み込んだ。その度に、王は甘言をもってなだめたが、二人の仲は険悪になるばかりであった。ついに、ある夜、王の命令を受けた下僕が、王妃の部屋に忍び込み、眠っていた彼女を絞め殺してしまったのである。王は、王妃の死をいかにも驚き悲しむようなふりをして見せたが、数日後にはフレデグンドを再び妻として迎えた。佞奸なフレデグンドが、言葉巧みに王をそそのかして王妃暗殺を実行させたのではないか、という疑いは極めて濃厚である。狙い通りに王妃に復帰した後、いよいよ、稀代の悪女として史上に名高いフレデグンドの、神をも恐れぬ数々の悪行が始まるのである。(参考文献1,2,3,9)
4. 戦乱勃発
ガルスヴィント殺害の知らせがアウストラシアの宮廷に届くや、憤怒に燃えた王妃ブルンヒルドは姉の復讐を王に求め、王シギベルトもそれを成し遂げる義務があると思った。直ちにネウストリアへの宣戦が布告され、戦いが始まった。それは568年頃のことであった。シギベルトは、兄グントラムを味方につけたが、グントラムは味方というよりは仲裁者の役回りを務めるようになった。彼は、戦闘ではなく、フランク人の法律である「サリカ法」によって、この一件を解決するように求め、自ら裁判長として裁定し、次のように宣告した。「結婚の贈り物としてガルスヴィントがキルペリクより受け取った諸都市を、以後、妹ブルンヒルドおよびその相続者の所有とすることを条件に、シギベルトおよびキルペリクの間に和平と友好を回復する。」両王はともにこの裁定を受け入れた。しかし、キルペリクは内心ではこれに従うつもりはなかった。そのうちいつか、これらの諸都市を取り戻すか、これらと同じ価値の領地をシギベルトから奪い取ってやろうと秘かに思い、機会を窺っていた。
数年後、キルペリクは、最初の妻アウドヴェラとの間に生まれた末子のクロヴィスにシギベルトの領地であるトゥールとポワティエを攻撃させたが、若い彼は未熟さを露呈し、それは失敗に終った。そこで、今度は長子のテウデベルトに再侵略の指揮を委ねた。裁定人を務めたグントラムは、緊急の調停に乗り出してきたが、キルペリクは聞く耳を持たず、すべての策が徒労に終った。テウデベルトは、トゥールとポワティエの攻略に成功すると、さらにリモージュ、カオールへと進み、田畑を荒らし、人家を掠奪、人民を虐殺するなど、暴虐の限りを尽した。これに対抗して、シギベルトは、自分の王国の兵士を結集させただけでなく、ライン河の彼岸にいるゲルマン人のあらゆる部族の男たちを誘い徴兵を行った。このようなゲルマンの野蛮で粗暴な異教徒の部族民までをも兵士として採用したことを、グントラムは認めることができず、シギベルトから離反し、キルペリクと同盟を結んだ。シギベルトは、この恐るべき軍隊を率いて、キルペリクの王国に向かう進軍の途中で、グントラムの領地の通過の了承を恫喝的に要求した。グントラムは恐れをなしてそれを認めた。キルペリクは、シギベルトの会戦の申し入れにも応ぜず、怖気を振るってただ逃げ回るばかりで、ついに追い詰められてしまった。キルペリクは、たわいもなく、相手のすべての要求を受け入れると言う約束の下に和睦を乞うた。シギベルトは、トゥール、ポワティエ、リモージュ、カオールを直ちに返すこと、テウデベルトの軍隊を引き揚げさせることだけを求め、和議が成立した。ところが、ライン河の向こう側からやって来て戦いに参加したゲルマン部族の兵士たちの間には非常な不平不満が溢れていた。彼らは、このような遠方の地まで来たのに、思いがけない和睦のために、掠奪により得るつもりでいた獲物の期待がすっかりはずれたのである。軍陣が解かれ故郷へ帰る途中で、彼らは、それを禁じられていたにもかかわらず、通過する町や村を襲い、手ひどい掠奪行為に走った。彼らがそれぞれ郷里の自分の家に帰ってから、悪逆な行為で特に目立った者どもは、一人ずつ捕えられ、死刑に処せられた。
和議の約定締結より1年も経たぬうちに、性懲りもなく、シギベルトに対抗して、キルペリクはグントラムと同盟を結び、子のテウデベルト率いる軍をアウストラシアに向けさせた。再び、町村の焼打ち、略奪が始まった。シギベルトは激怒し、フランク兵はもとより、例のライン河彼岸の蛮族の兵士を結集させ、今度は公然と略奪行為の許可を与え、キルペリクに対する戦いに向かった。キルペリクは、以前と同様に決戦を避け退却し、それを追ってシギベルトはパリの城下まで迫り、そこに陣を布いた。他方、臣下の将軍ボゾ・グントラム(ブルグンディア王グントラムとは別人、以後ボゾと呼ぶ)に命じて、テウデベルト討伐の軍を向けさせた。その戦いにテウデベルトは敗れ、戦死した。このとき、ボゾがテウデベルトを自らの手で殺したか、部下の兵士たちが殺すがままに放置していたのだ、という噂が広まったので、父キルペリクは彼に強い憎悪の念を抱いた。旗色悪しと見た王グントラムは、キルペリクを裏切り、シギベルトと和睦した。それを知ったキルペリクは、妻子とともに首都パリを捨て、トゥルネの城内に逃げ込んだ。トゥルネは、現在ではベルギーの領土になっている地域にあった町だが、フランク王国のかつての首都であって、非常に堅固な城を持っていたのである。575年、シギベルトはパリを占領した。それと同時に、彼はネウストリア王国の数々の都市を奪い取っていった。そして、この王国の多くの貴族が、自分たちの王を見捨てて、次々にシギベルトに帰順したのであった。キルペリクは、トゥルネに孤立し、まさに四面楚歌の状況に陥った。
姉ガルスヴィントの復讐に執念を燃やすブルンヒルドは、アウストラシアの首都メッツを離れて、二人の娘イングンドとクロドシンド、そして幼い息子キルデベルトを伴い、夫シギベルトが支配しているパリへやって来た。パリとメッツは直線距離にして300キロメートル近く離れているが、それを馬車で移動するとなると、おそらく半月以上はかかる旅になったであろう。なぜ、それほどまでして彼女は夫の元へ来たのであろうか。それは、彼女にとっては不倶戴天の仇キルペリクを討つ絶好の機会を得た今、夫が、またもや慈悲心を起こして弟を許し、和睦を受け入れることがないように鼓舞激励するためであった。彼女がパリに入った日、住民は群をなして彼女を歓迎し、多くの聖職者や貴族は、拝謁のため、われ先に彼女のもとへ馳せ参じた。しかし、最高の指導者として人々の尊敬を集めていたパリ司教の聖ジェルマンだけは現れなかった。彼は内戦が始まったときからその調停役を務めようとしており、シギベルトがパリに来たときにも和平を求めて懇請を繰り返していたのだが、全く耳を貸して貰えなかった。そこで、彼はブルンヒルドに、「兄弟の争いを止めてフランク国を戦乱から救って下さるよう王に進言して頂きたい」という内容の書簡を送った。(ティエリによれば、この書簡は彼の時代には存在していたとのことである。)けれども、復讐心の強い彼女がそれを聞き入れるはずもなかった。
シギベルトは、軍隊を送り、トゥルネを完全に包囲させた。そして、彼は、キルペリクを追い出した地域の新しい王としての即位の儀式をとり行うべく、トゥルネにほど近いヴィトリに赴いた。その儀式は、四人の兵士が支える一枚の盾の上に王を乗せ、兵士の作る円陣の周りを三度回るというものであった。儀式が終った後は、集まって来た人々を歓待し、豪勢な宴会が何日も続いた。その頃、シギベルトの軍勢に包囲されていたトゥルネの城の内部では、キルペリクは、生き延びる一縷の望みもないと知り、覚悟を決めていた。しかし、フレデグンドは、未練がましく、何とかこの窮地を脱する方策はないものかと、あれこれと考えを回らしていた。彼女は、かねてから忠義に篤いと思っていた二人の若い家臣に目をつけた。女王は、彼らを身近に呼んで、贅沢な酒食の饗応とともに甘い言葉で相手を感動させ、これから二人で秘かにヴィトリへ行き、シギベルト王を暗殺してきて欲しいと切り出した。彼らは驚いたが、「女王様のためとあらば」と、それをしかと請合った。女王は鞘入りの短剣を取り出し、彼らに手渡した。その刃には毒が塗られていた。二人の若者は、城砦からの脱走兵を装い、ヴィトリへと向かった。彼らがヴィトリに着いたときは、その地はまだ即位式後の宴会に沸き立っていた。王の住まう館に辿り着いた二人の刺客は、我々はネウストリア王国から来た者であるが、シギベルト王に折り入ってお話し申し上げたいことがあると言って、面談を乞うた。それは簡単に許され、王は機嫌よく面会に応じた。王が二人の話を聞いているとき、頃を見計らった彼らは、同時に王に躍りかかって脇腹に短刀を刺し込んだ。王は大声を上げて倒れ、息絶えた。駆けつけた家臣たちにとり囲まれ、二人の暗殺者はめった切りに殺された。やがて、トゥルネの城を包囲していたシギベルトの兵士たちの間にこの一大変事が知れわたると、誰も彼もが、慌てふためいて荷物をとりまとめ、散り散りになって己が故郷へと逃げ帰って行った。恐るべきはフレデグンドの魔手であった。その乾坤一擲の大ばくちがまんまと当たり、キルペリクとフレデグンドは辛くも死地を脱したのである。(参考文献1,2,3)
5. メロヴィクの恋
パリにいたブルンヒルドは、夫が凶刃に倒れたという報せを聞いてしばらくは、悲嘆と心痛のあまりなすすべを知らなかった。ところが、いち早くキルペリクは、ブルンヒルドを始めとする兄の遺族を取り押さえるために、また、王妃がはるばるとパリまで携えて来た財宝を奪うために、いち速く兵を率いてトゥルネを発しパリに向かっていたのである。その道すがら、シギベルトに帰順していたネウストリアのすべての貴族たちが、罷り出て、キルペリクの許しを乞い、再び彼に服従することを誓った。アウストラシアの貴族たちでさえ、寝返ってキルペリクの支配下に入る者が多かった。それゆえに、ブルンヒルドはパリを脱出することができなかったのである。仮にパリを逃げ出したとしても、彼女はすぐさま裏切り者の手によって捕えられたであろう。しかし、まだ幼い王子キルデベルトの脱出は、ブルンヒルドに付いて残っていたただ一人の忠義な将軍グンドヴァルドによって秘かに準備が整えられた。夜に、王子は大きな籠に入れられて、宮殿の窓から外へ出され、町の外へと運び去られた。王子は、目立たぬように下僕がただ一人だけ付き添い、はるか遠方のメッツに奇蹟的に帰還した。思いがけぬ王子の帰国は、アウストラシアの人々を狂喜させ、崩壊寸前であった王国の体勢を立て直させた。年齢わずかに5歳のこの王子は、アウストラシア王キルデベルト2世として即位し、貴族や司教たちから選出された幾人かの顧問が彼の後見として政務をとることになった。
パリに到着したキルペリクは、ブルンヒルドの身柄と彼女が携えて来た高価な財宝を捕獲した。確実に追い詰めながら、あと一歩のところで逃げられた、憎んでも余りある仇敵に、囚われの身となって相まみえたブルンヒルドの心境はいかばかりであったろうか。薄ら笑いを浮かべる仇を前に、おそらく、積もる口惜しさ、辛さを歯噛みしながら耐えたに違いない。自分の身はともかく、一緒に捕えられている二人の娘の身の安全を考えれば、姉と夫が殺されたことについて強くなじることはできなかったであろう。会見は短時間で終った。彼女は一室に閉じ込められ、厳重に監視された。欲深なキルペリクは、早々とブルンヒルドの財宝を検分してみたが、その量が自分の思っていたよりもずっと多かったので、すっかり機嫌を良くし、彼女の処置を寛大に取り計らうことにした。彼女は、今は亡き姉とキルペリクの婚儀が行われたあのルーアンの地へ流刑となったのである。そして、彼女の二人の娘イングンドとクロドシンドはパリの東方約50キロメートルの地モーに流された。
さて、キルペリクは、パリでブルンヒルドと対面をしたこのときに、最初の妻アウドヴェラとの間に生まれた次男メロヴィクを伴っていた。メロヴィクは、そのとき初めて、この魅惑的な囚われの美女に出会った。これは彼にとって運命の出会いとなった。この年上の寡婦に対する彼の賛美、憧憬そして同情の念は、やがて強い恋心に変わっていったのである。ところで、キルペリクは、キルデベルト王子を取り逃がしたばかりに、アウストラシア王国支配の好機を失ったことを、極めて残念に思っていた。その埋め合わせに、彼は、生前のシギベルトとの間に繰り返された紛争の原因であったアキテーヌの諸都市のうち、トゥールを除いて、ポワティエ、リモージュ、カオール、ボルドーの攻略を始めることにした。トゥールだけは彼に帰属していたが、この四つの都市はそうではなかったのである。そこで、彼はメロヴィクをその派遣軍の総大将に任命し、ポワティエ地方へ進軍するように命じた。ところが、メロヴィクは、遠征の途中で独り、ル・マンの修道院に入っていた実母アウドヴェラに会いに行くようなふりをして、ルーアンへ向かったのである。ブルンヒルドに会うためであった。思いもかけぬこの訪問に彼女はいたく喜び、二人の恋は急速に進展した。夫を失ってから少ししか年月が経っていないのに、ブルンヒルドは、あろうことか、仇敵の子メロヴィクとの結婚を承諾したのである。しかし、この結婚は教会法によって禁止されていた。なぜなら、ブルンヒルドはメロヴィクの義理の伯母であったからである。ところが、そのときのルーアンの司教プラエテクスタトゥスは、メロヴィク誕生に際し洗礼を授けた人物であって、彼にわが子のような情愛を感じていた。そのメロヴィクに泣きつかれた司教は、やむなく法に背いてこの甥と伯母の婚姻のミサを上げ、祝福を与えなければならなくなった。この件は、後になって、プラエテクスタトゥスに災いをもたらした。すなわち、彼は、キルペリク王の主催する裁判においてその責任を追及され、ノルマンディー沖のジャージー島に流刑となったのである。彼は、数年後にはルーアンの司教に復帰したが、たまたま、ある会合で王妃フレデグンドと顔を合わせたことがあった。その席上で、彼は、王妃と口論になり、並みいる有力者たちの面前で彼女を徹底的にやり込めてしまった。それを深く恨みに思った彼女の放った刺客によって、プラエテクスタトゥスは、聖堂において祈祷のさなかに襲われ殺されたのである。
王子メロヴィクのアキテーヌ遠征の成功を期待していたキルペリクは、それどころか、王子の脱走とブルンヒルドとの結婚と言う驚くべき知らせを受け取った。激怒した彼は、その結婚を解消させるために急ぎルーアンに向かった。彼が到着すると、新婚の夫婦はルーアンの城壁の上に建っていた小さな聖マルタン教会の中に逃げ込んだ。中世の教会は「庇護権」というものを持っていて、いかなる罪人といえども、教会の建物の中にいる者は、何人も踏み込んでこれを捕えることはできなかったのである。当時、現在の警察のような組織は存在しなかったので、例えば、殺人事件が起きた場合、被害者の遺族あるいは縁者が犯人を捕えて裁判にかけ、償いをさせなければならなかった。殺人者はその追跡を逃れて教会の中に避難することが多かったが、追跡者は犯人が教会の外へ出て来るまでは何もできなかった。その他の犯罪者や亡命者についても同様であった。さて、サン・マルタン教会の中に逃げ込んだ二人を、キルペリクは、あれこれと巧言を弄して騙し、外へおびき出して取り押さえた。そして、ブルンヒルドを厳重な監視の下にルーアンに残して、メロヴィクを連れ、ソワソンの町へ兵士たちとともに向かった。(参考文献1,2,3)
6. メロヴィクの放浪
キルペリクとメロヴィクがソワソンの近くまで来たとき、その町がアウストラシア軍によって包囲されているという知らせを受けた。その都市に滞在していた王妃フレデグンドは、先妻の子クロヴィスと、生まれて間もない実の男の子を連れて、難を逃れていた。町を囲んでいたのは、もともとアウストラシアの二人の貴族で、シギベルト暗殺後にキルペリク側に寝返り、今度また裏切ってアウストラシアの幼王キルデベルト2世についた者たちであった。キルペリクは、珍しくこの包囲軍との戦いに勝って、ソワソンの町に入った。ところが、フレデグンドは、この包囲はメロヴィクと組んでブルンヒルドが企んだ陰謀によるものであり、彼は父を倒して王位を奪い、不倫の結婚によって結ばれた彼女と一緒にフランク王国を支配しようとしているのだと、まことしやかにキルペリクに吹き込んだ。疑い深く思慮のない彼は、それをたやすく信じ、すぐに息子を捕え監禁した。ちょうどその頃、アウストラシアの幼王キルデベルトの後見人たちからの使節が、キルペリク王に会いにやって来て、ブルンヒルドと二人の娘の釈放を願い出た。フレデグンドから吹き込まれた話に脅えていた王は、陰謀を企んでいる女を、自分の領地に置いておくのは危険であると思い、あまり難色も示さず、その願いを認めてやった。思いがけず解放されたブルンヒルドは、急きょルーアンを出発し、モーに囚われていた二人の娘を伴って、メッツの宮廷に無事帰還した。アウストラシアの国中で待ち望まれていたブルンヒルドの復帰は大いに喜ばれたが、時が経つにつれ、幼王の摂政格として政治に容喙してくる彼女と、王の後見人たちが組織していた重臣会議の間に大きな摩擦が生じ、後に国内の厄介な紛争に発展した。
監禁されていたメロヴィクは、フレデグンドの讒言により、すっかり父王キルペリクに対する謀反人に仕立て上げられていたが、親族裁判において、彼女の積極的な発言により、断髪の刑を宣告された。すなわち、生まれたときから一度も鋏を入れたことのない彼の長髪は、王族の男子の象徴であったのだが、それを断たれることは、王族の一員としての身分を剥奪されるということであった。フレデグンドは、まだ幼い実の息子をキルペリクの後継者にすべく、邪魔な先妻の息子たちを陥れようと秘かに機会を窺っていたのである。長男のテウデリクは、4節で述べられたように、既に、ボゾとの戦いにおいて敗死していたが、彼女はこれを内心では非常に喜んだのであった。逆に、父キルペリクは、ボゾを息子の仇として深く恨み、復讐しようとしていたのだが。メロヴィクは何もかも取り上げられて、僧侶の衣装を着せられ、ル・マン近辺のサン・カレー修道院に押し込められることになった。そうなったら、逃げ出すこともできず、救い出される当てもなかった。ところが、このとき、上記のボゾが、キルペリク王の追及を逃れて、トゥールのサン・マルタン修道院の庇護を求め、ここに逃げ込んでいたのである。当時のトゥールの司教は、序文冒頭に述べた「10巻の歴史」の作者グレゴリウスであった。キルペリク王は、トゥールに一隊の兵士を派遣し、ボゾを当方に引き渡すようにと、グレゴリウスに要求した。その要求は次第に威嚇的になっていった。しかし、彼は、穏やかではあるが毅然とした態度で、それを拒否し続けた。ボゾは謀略を回らすことにかけては際立っていた。彼は、メロヴィクが蒙った逆境の事情を正確に知ると、自由の身になるために、自分よりもはるかに脱出の機会が多いメロヴィクを利用することを思いついた。すなわち、彼は、メロヴィクと合流し協力して、アウストラシアに逃げる手段を探ろうとしたのであった。彼はメロヴィクと連絡を取るためにル・マンに使者を遣わした。ちょうどその頃、メロヴィクの臣下のガイレヌスという若い戦士が、彼を救出するために兵士を引き連れて来ていて、メロヴィクがル・マンの修道院に護送されて到着するのを待ち構えているところであった。護送隊は、ガイレヌスの一行に襲われ、メロヴィクは解放された。そして、ボゾが遣わした使者は、メロヴィクに会うことができ、彼を、サン・マルタン修道院へ連れて行って、ボゾに引き会わせた。こうして、ボゾはメロヴィクを抱き込むことに成功した。
キルペリク王が、ボゾを捕えるために、兵士を率いてサン・マルタン修道院を攻撃する決心を固める一方、フレデグンドは、邪魔者メロヴィクを亡き者にする計画を立て始めた。彼女は、ボゾとメロヴィクが合流したことを知ると、家来をボゾに送り、メロヴィクを修道院の外へ連れ出して殺すことに成功したならば、莫大な褒賞を取らせると申し入れたのである。ボゾは大喜びでこれを引き受けた。そこで、ボゾは、金銭と兵力の準備に精を出し、これ以上時機を遅らせる必要はないと見極めをつけると、ついにメロヴィクとともに修道院を出発し、アウストラシアを目指した。ところが、二人は途中の町で通過を阻まれ、争いの混乱の中で、離れ離れになってしまった。
それから、メロヴィクは忠臣ガイレヌスを伴い、道中を進め、ついにアウストラシアの領内に足を踏み入れた。その地では、妻ブルンヒルドが彼を待っており、夫の地位に相応しい栄耀栄華が得られるはずであった。ところが、本節で述べたように、その頃、アウストラシア王国では、幼王キルデベルト2世の顧問として政治を司っていた重臣会議と、幼王の摂政たらんとするブルンヒルドとの間に、絶え間のない紛争が沸き起こっていた。メロヴィクが王国の首都メッツに着いたとき、彼は、重臣会議から、直ちにこの町を立ち退くようにという命令を受け取った。彼を手厚く迎えてやるようにとのブルンヒルドの懇願も無駄であった。彼は、身を寄せる最後の望みの地も失い、来た道を引き返し、ランス地方を村から村へと放浪し始めた。密告を恐れて、日中は隠れ潜み、夜中にあてどもなく歩くという逃避行が続いた。そして、彼は、再びトゥールのサン・マルタン修道院を目指すことにした。その噂はすぐにネウストリアに伝わり、それを聞いたキルペリク王は、軍を進めてトゥールを占拠し、サン・マルタン修道院を封鎖した。王は、メロヴィクの潜んでいそうな地域を、隈なく探させたが、彼は下層の人々の助けにより、父の捜索の手を逃れることができた。トゥールへ行くことができなかった彼は、アウストラシアの地を流れ歩くしかなかった。ところが、このとき、メロヴィクのかつての道連れであったボゾが、この地に到着していた。このボゾに、以前にメロヴィク殺害を依頼したことのあるフレデグンドが、ランスの司教を通じて、またも、豪華な褒賞つきの同様の指令を送ってきた。これを引き受けたボゾは、この二人と協力して奸計を練った。その結果、フレデグンドに忠誠を尽くしていたテルアンヌ地方から、何人かの男たちがメロヴィクに会いに来て、「もし、貴方が我々のもとにお越しになれば、我々はキルペリク王を廃位して、貴方を王にお迎えすることができる」と伝えたのである。困り果てていたメロヴィクは、この甘言に、前後の見境もなく飛びついた。彼の一行は、この得体の知れぬ男たちの後に従い、ネウストリアの領内をテルアンヌへと進んだ。アラスの北方に来たとき、一隊の兵士が歓声を上げて彼らを迎え、丁重に、ある一つの荘園の中に案内した。彼らがそこに入ると、背後で門扉がぴたりと閉じられ、荘園は大勢の兵士によって厳重に取り囲まれた。ただちに、馬に乗った急使がフレデグンドのもとへ走った。陥穽に嵌り、もう生き残る道がないことをようやく知ったメロヴィクは、忠臣ガイレヌスにわが身の処置を命じた。ガイレヌスの一撃により、メロヴィクは絶命した。こうして、フランク族の太祖と同じ名を持つ王子が、あらぬ罪を押し付けられて、父を始めとする身内に追い詰められ悲惨な死を遂げたのである。(参考文献1,2,3)
7. クロヴィスの悲劇
フランク王国の行政は、西ローマ帝国のそれをそのまま受け継いだものと言ってよく、税制については、ローマ時代の古い土地台帳を基礎としたものを用いて、租税の徴収を行っていた。そのため、実際に地租を払うのは、古い時代から住み着いていたガリア人の地主だけで、新たに定住したゲルマンの自由民たちは、要求されても頑強な反抗によって、租税を払おうとはしなかった。従って、国家の財政は非常に不規則かつ不安定になっていた。そこで、ネウストリア王国では、580年頃に、王妃フレデグンドの意見具申により、全般的国勢調査を施行し、税制の大改革を行うことになった。このように述べると、至極まともに聞こえるが、実のところは、要するに、自分たちの栄耀栄華のために、できるだけ沢山の税金を人民から搾り取ってやろうということであった。そこで、抜け目のないやり手の役人が調査に派遣され、新しい土地台帳が作成されることになった。まず手始めに、それはキルペリク王の所有にあったリモージュの町において行われた。ところが、この町では、以前に市民がキルペリクに忠誠を誓ったときに、新たな課税をせぬとの約束を取り付けていたのである。そのため、新税制案作成の交渉の会議は大騒動となり、群衆に囲まれ詰め寄られた役人は危うく殺されそうになったが、辛うじてこの町を脱出した。群衆は、役人が置き去りにしていった帳簿などの書類を残らず燃やしてしまった。王はこれを反乱と見なし、改めて役人と軍隊を派遣して、暴動を起こした者たちを一網打尽に捕え、死刑や国外追放に処した。彼らの財産はすべて没収され、市民には、従来よりもはるかに過酷な重税が押し付けられたのである。ネウストリア王国のリモージュ以外のすべての都市においても、新たな税制が定められ、この重税に耐えかねた夥しい数の市民がネウストリア王国を立ち去り、キルデベルト2世の治めるアウストラシア王国へ、あるいは、グントラム王の治めるブルグンディア王国へと、移住していった。
キルペリク王の圧政がネウストリアに暗い影を落としたこの年は、次々に大きな災難が続いた年であった。中でも特筆すべきは、ガリア中部の町々に赤痢が発生して、各所に伝染し、ついにガリア全域に大流行するに至ったことである。その死亡率は極めて高く、特に幼児や年若の人々に犠牲者が多かった。流行は、ついにパリとその周辺に、さらにソワソンに達した。王家はソワソンの近傍に昔から所有していたブレーヌの荘園に避難していたが、疫病の侵入は、その宮廷にも及んだ。最初にキルペリク王が感染したが、間もなく彼は回復した。すると今度は、末の王子ダゴベルトと、15歳になる兄の王子クロドベルトが発病した。病状は重く、まず弟が斃れ、続いて兄も絶命した。キルペリクとフレデグンドの間に生まれていたサムソンとテウデリクは、既に幼時に死亡しており、これで彼らの間には男子がいなくなった。今や、王位継承者として残ったのはただ一人、フランク王国建国の祖と同じ名を持つクロヴィスであった。彼はキルペリクと元王妃アウドヴェラの間に生まれた三人の王子の末子であったが、4節と6節において述べられたように、長兄テウデベルトは戦死、次兄メロヴィクは父王に追われ、放浪の果てに死亡していたのである。フレデグンドは、この次期王の唯一の候補者クロヴィスを、何とかして陥れ、亡き者にしてやろうと様々に悪知恵を回らせた。彼女は、病を避けて王とともにブレーヌを離れていたが、王をけしかけて、疫病がますます猛威を振るっているブレーヌに、うまい口実を設け、クロヴィスを行かせることを思いついた。王はすぐにそれに乗せられ、彼にブレーヌ出張を命じた。ところが、彼は、全く病気にかからず、無事に任務を終えて戻って来た。クロヴィスは、兄弟たちの中でただ一人生き残ったことで、わが身の強さに自信過剰となり、驕り高ぶった。将来の王国は自分のものだとあちらこちらで広言し、フレデグンドを見下しては、彼女についての悪口雑言を大っぴらにまき散らした。それがフレデグンドの耳に入り、彼女の身体は怒りに震えた。
ある日のこと、でたらめな讒言をするために王妃のもとへやってきた者がいた。その者は、クロヴィスは王妃の召使の女を愛人としており、その女の母親は魔女であって、この度の疫病による二人の王子の死は、実はクロヴィスがこの魔女に呪いをかけさせたためであると言うのであった。即座に、フレデグンドはこの母娘を取り押さえ、拷問の責め苦を与えた。母親は全く身に覚えのない罪を白状させられてしまった。後に、この哀れな女は、裁判にかけられ、生きながらの火刑に処せられたのである。この女の虚偽の供述を動かぬ証拠として、フレデグンドはキルペリク王に、クロヴィスに対する報復を求めた。彼女は、クロヴィスは王位簒奪と父親殺しまでをも狙っていると、言葉巧みに言いくるめた。そして、それを信用し動揺した王は、息子の言い分を聞こうともせずに、彼を王妃の裁きの手に委ねることにしたのである。王は彼を召し捕り、王妃に引き渡した。結果の決まり切っている王妃主催の裁判が三日間行われたが、王子の支持者たちの名前が明らかになると、四日目にクロヴィスは外へ連れ出され、刺し殺された。その遺骸は埋葬もされずに川に投げ込まれた。ところが、それが遠くに流されもせず、近くに住む漁師の網に引っかかったのである。漁師はその長髪を見て、これは王子の死体であると直感した。彼は死骸を岸に引き上げ、丁寧に埋葬し、その場所に目印を付けておいた。そして、彼は後難を恐れてこの秘密を長い間誰にも打ち明けなかった。
クロヴィスの実母で、かつてフレデグンドが姦計をもって王妃の地位から退けたアウドヴェラは、ル・マンの修道院でまだ生きていた。クロヴィス殺害後、アウドヴェラに対する憎しみが急に強くなったものか、あるいは彼女の復讐を恐れたものか、よく分からないが、フレデグンドは、家来に命じてこの修道院を襲わせ、アウドヴェラを殺させたのである。神を恐れぬ極悪非道の所業であった。その修道院には、アウドヴェラの娘バシナ(クロヴィスの妹)が一緒に暮らしていたが、彼女も襲われ、かつては王女の身でありながら、いわれのない陵辱を受けた。その後、彼女はポワティエのサント・クロワ修道院に身を寄せ、その創立者である聖女ラデグンドの手厚い保護の下に入った。
クロヴィスの家臣や支持者たちにもフレデグンドの魔手が伸び始めていた。国境の各都市の伯は逃亡者の逮捕を命じられていた。クロヴィスの会計係をしていた男が捕えられ、首都へ護送される途中、トゥールの町を通過した。そのとき、たまたま、「10巻の歴史」の作者、トゥールの司教グレゴリウスが、縛られて歩いているその男を目にして、彼を待ち受けている悲惨な運命を哀れみ、警護の者たちに彼の命乞いの手紙を手渡して、王妃に届けさせた。多くの人々に尊敬されていたこの人物の懇願は、フレデグンドの荒んだ心に驚くべき効果をもたらした。彼女は捕えたその男を何の咎めもなしに解放した。あたかも突然神の声を聞いたかのように、彼女はこのときから一切の報復行為をぴたりと停止したのである。
歳月も過ぎ、クロヴィスの事件のほとぼりもすっかり冷めた頃、ブルグンディア王グントラムは、墓もないクロヴィスを哀れに思い、その死について調査をし始めた。その噂がパリの近辺にまで広がっていった。ある日、一人の田舎者がグントラム王のもとへやって来て、クロヴィス王子の遺体の在りかをお教えしたいと申し出た。それはクロヴィスを埋葬した漁師であった。彼の案内に従って、グントラムはクロヴィスの遺骸を手に入れることができた。その後間もなく、テルアンヌ地方に埋められていたメロヴィクの遺体も発見され、グントラムによって、この二人はパリのサン・ヴァンサン教会に丁重に葬られた。この教会は、メロヴィング王家の墓所となり、その後、4節に登場した聖人ジェルマンの名をとって、サン・ジェルマン・デ・プレ教会と改名された。これは、現存するパリ最古の、極めて由緒ある教会である。(参考文献1,2,3)
8. 聖女ラデグンド
時代は少し遡る。王家の四人兄弟カリベルト、グントラム、シギベルト、キルペリクの父クロタール1世は、2節において述べたように、兄テウデリクとともに隣国のテューリンゲン族を攻撃し、連戦連勝を重ね、ついに彼らを滅亡させてしまった。531年のことであった。フランクの宮廷に仕えたイタリア生まれの詩人ウェナンティウス・フォルトゥナトゥスが、このときの凄まじい惨状を生々しく描写した詩作「テューリンゲン族の最後」を残している。テューリンゲン族の王ベルタカルの娘であった少女ラデグンドは、陥落時の王の居城において繰り広げられた惨劇を、身をもって体験し、後年、その状況をフォルトゥナトゥスに、微に入り細にわたり語り聞かせた。その話をもとに、美しくも悲壮な詩に詠い上げたものがこの作品であった。そのとき、彼女は兄とともに捕えられ、二人とも人質としてフランク王国に連行された。まだ8歳というのに、この少女の気品漂う美しさは人々の目を引き、好色なクロタール王は、この王女を自分の好きなように育て上げ、ゆくゆくは我が妻に迎えようと決めたのである。ラデグンドは、ソンム河畔の王の離宮で大切に養育され、富裕なガリア人の子女が受けるような高等な教育を授けられた。彼女は、ラテンやギリシアの古典文学、世俗の詩やキリスト教学などを学んだ。生まれつき聡明で優れた能力を備えていた彼女は、やがて、深い教養と宗教的熱意を伴った高貴で崇高な精神の持ち主に成長していった。それとともに、当時の、不正や暴力のはびこる世の中、野蛮で下劣な男たちに激しい嫌悪感を抱くようになった。やがて一族の仇であるあの粗暴な王の妻にならねばならぬと思うとき、彼女は恐怖の念に身震いするのであった。ついにそのときが来て、婚礼の式典を挙げるので、ソワソンの王の宮殿に来るようにとの命令が伝えられると、彼女は本能的嫌悪に耐え切れず、逃亡を図った。しかし、彼女は、すぐさま捕えられ連れ戻されて、泣く泣くフランク国の王妃となったのである。この結婚は538年のことであるから、このとき彼女はまだ15歳であった。
ラデグンドは、嫌いな夫王との結婚生活の苦しさから逃れるために、すべてをキリスト教への奉仕と慈善事業に捧げ、自ら貧者と病人の救済に献身した。婚姻の贈り物として王から与えられたアティの離宮は弱者たちの救済所となった。宮廷の祝典や饗宴、家臣たちとの付き合いなどは、彼女を退屈させ、疲労させた。けれども、司教や教養の深い聖職者が宮廷に姿を現したときには、彼女は、喜んで彼らと面会し、長い時間をかけて信仰や文学などについて語り合った。夫とともにする食事の時間には、彼女は必ず遅刻した。待ちくたびれた王がひどく怒っても その行為は変わらなかった。夜は、王とともにいるときは起きて過ごし、床に敷いた粗末な毛布の上で眠り、体が芯から凍えるまでは夫婦の寝床につくことはなかった。このように妻から嫌悪されたクロタール王はいらだちを見せることはあっても、ラデグンドに対する愛着の念は消えなかった。
ラデグンドにとって希望する唯一の居場所は修道院であった。彼女は心の底から尼僧院の生活に憧れていた。けれども、いろいろな障害があって、彼女がそれを実行するためには、長い歳月が必要であった。それを彼女に踏み切らせたのは、彼女の一族に起こった最後の不幸であった。ともに人質としてフランク国に連れて来られた彼女の兄が、どのようないきさつがあったのかは分からぬが、王の命令により殺されてしまったのである。別の説によれば、ラデグンドは、兄を殺すように王から強要されたということである。ともかく、彼女は、兄の死を契機として、修道院入りを決意したのであった。そのために、彼女はソワソンの北西40キロメートルほどの地ノワイヨンに赴いた。そこには、彼女の望みを叶えてくれる人物、当時、聖人としての名声が全ガリアに広まっていた司教メダルドゥスがいたのである。しかし、メダルドゥスはクロタール王によって司教に任ぜられた人物であった。ラデグンドは司教に会うとすぐに修道女の祝別を我が身に与えて欲しいと強く願い出た。この唐突な願いに驚かされた司教は、しばらく考えさせてくれるように言った。これは、司教にとっても容易ならぬ決心を必要とすることであったからである。すなわち、それは、フランク人の法律であるサリカ法に則って正式に結ばれた王族の婚姻関係を打ち壊してしまうことであったからである。何も知らずに王妃に付き添って来た家臣たちは、その由々しい事態に気づいて騒ぎ始め、司教を取り囲み威嚇しながら叫びたてた。ラデグンドは、その騒ぎに恐れをなして一時別室に身を潜めたが、やがて、王妃の衣装の上から尼僧の衣を着けて現れ、思い悩んでいる司教メダルドゥスの前に歩み寄って言った。「もし貴方様が、私に修道女としての祝別を与えず、神を恐れるよりも人を恐れられるならば、主は貴方様の敬信の念をお疑いになるでしょう。」これを聞いた老司教はにわかに勇気を取り戻し、司教としての良心がすべてに打ち勝った。彼はもはや迷うことなく、自らの権威をもってラデグンドの婚姻関係を断ち切り、彼女に祝別を与えた。ここに至っては、家臣たちも、神に仕える修道女としてのラデグンドを、腕ずくで宮廷に連れ戻すことはできなかった。
ラデグンドは急ぎガリア南部へと向かった。クロタール王の追跡を逃れるためである。彼女は、オルレアンの町に辿り着き、そこから舟に乗ってロワール河を下り、トゥールで上陸した。彼女は近辺の修道院に身を潜めながら、有力な聖職者の手を介して王に手紙を送り、もう二度と会うことは諦めて、自分の切なる信仰の念を通させて欲しいと、懇願した。だが、クロタールは、彼女のどんな言葉にも耳を傾けることなく、あくまでも夫の権利を主張し、力ずくでも逃げた王妃を連れ戻すと言い張った。彼女はトゥールからさらに南のポワティエへと逃避した。クロタールは、聖マルタン参拝を口実に、彼女を捕獲するために、一度はトゥールまでやって来たのであるが、司教聖ジェルマンのたっての諫言によって、さらにポワティエへ脚を伸ばすことは思いとどまった。そしてついに、クロタールはラデグンドを取り戻すことを諦めて、彼女の望みを叶えてやり、さらに、彼女がポワティエに女子修道院を創設することをも認めたのであった。しかも、クロタール王は、彼女に修道女の祝別を与えた司教メダルドゥスに何の危害も加えなかった。それどころか、王は、司教の死後、彼を追悼してその墓所に聖堂を建立したのである。ようやくにして念願を果たしたラデグンドは、ポワティエの町はずれに場所を定め、ここに新しいサント・クロワ修道院の基礎を置いた。彼女は自分の全財産をこの隠棲所の開設に注ぎ込んだ。王に逆らい王妃の地位をなげうってまでして、修道生活を求め、新しい尼僧院を建てようとしている気高い貴婦人の話は、当時の人々に大きな衝撃を与え、その噂は驚嘆すべき大事件として遠隔の地にまで伝わっていった。用意万端整えられて、いよいよラデグンドが遁世の場所に入る当日は、彼女が通ることになっている道筋や広場は、この稀有の聖女を一目見ようという夥しい数の人々によって溢れんばかりであった。彼女は、同じ修道の志を持って彼女とともに隠棲の道を歩もうとする数多くの若い娘たちを引き従え、群衆が見守る中を、静かに尼僧院に入って行った。世間の人々は、かの修道院こそ現世の「ノアの方舟」であると言い合った。(参考文献1,2,3,7)
9. 西ゴート王国の内乱
ブルンヒルドやガルスヴィントの父親であった西ゴート王アタナギルドは、国内の反対勢力を追放し王権を保持するため、東ローマ帝国皇帝ユスティニアヌス1世(大帝)に軍事援助を求めたが、そこにつけこんだ帝国は、アンダルシア地方の広い部分を西ゴート王国より奪い占領してしまった (554年)。その後、王国は幾度となく帝国軍の侵入を受け、国内の安定は得られなかった。アタナギルドの死後、南ガリアのナルボンヌの公爵リウバが王となったが、間もなく弟のレオビギルドに王位を譲った(572年)。レオビギルドは、その14年余りの統治の間に、失われていた西ゴート王国の領土のかなりの部分を回復し、王国に繁栄をもたらした。妻と死に別れていた彼は、アタナギルドの妻であり、ブルンヒルドとガルスヴィントの母であったゴイスヴィントと再婚した。西ゴート王国においては、キリスト教のアリウス派が信奉されており、少数派のカトリック教徒への迫害が激しかった。多くのカトリック信者が、追放され、財産を奪われ、投獄され、様々な刑罰により殺された。このような悪業の主謀者は王妃ゴイスヴィントであったが、たちまち、彼女に神の罰が下った。彼女の片方の眼を白い雲が覆い、視力を奪ってしまったのである。さて、レオビギルドは、先妻との間に二人の王子を持っていたが、579年、兄のヘルメネギルドをアウストラシアの前王妃ブルンヒルドの娘イングンドと結婚させた。彼女は豪華な婚礼の調度品とともにスペインへ嫁いで来た。祖母のゴイスヴィントは大喜びであった。二人の愛娘をフランク国へ泣きの涙をもって送り出し、そのうちの一人は理不尽にも夫に命を奪われたのである。彼女は孫娘の到来を、長い間家を空けていた我が娘が帰って来たかのような歓喜の思いで迎えたに違いない。しかし、その喜びは長くは続かなかった。イングンドは、フランク国の伝統に従って、カトリックを信仰していた。ゴイスヴィントはそれを激しく嫌って、アリウス派に改宗するように強く迫った。イングンドは自己の信仰を固く守りたいとして、それをきっぱりと断った。これを聞いたゴイスヴィントは、白い眼をつり上げ、恐ろしい形相で怒り狂った。彼女は、イングンドの髪の毛をつかみ床に引き倒して、何度も蹴り上げた後、血まみれになったイングンドの衣服を剥ぎ取り、その体を池の中に放り投げるように家来に命じたのである。けれども、そのようなことがあっても、イングンドの心はカトリックの信仰から離れることはなかった。
レオヴィギルド王は、長男ヘルメネギルドにセビリャの町を領土として与えたので、彼は妻イングンドとともにその町に移り住み、領地を統治した。イングンドは夫に、アリウス派の異端を捨ててカトリックの信仰に転向するように熱心に勧誘し始めた。彼は長い間それを拒否し続けていたが、セビリャの司教レアンドルスらの影響もあって、ついに彼女の説得に応じ、カトリックの洗礼を受けたのである。それを知ったレオヴィギルドは激怒し、息子を懲らしめ制裁を加えるための方策をあれこれと考え、実行し始めた。それに反発したヘルメネギルドは、当時西ゴート王国を攻撃していた東ローマ帝国の側につくことにし、アンダルシアに駐留していた帝国の地方総督によしみを通ずるべく、使者を送った。ところが、父王は、地方総督に金貨3万枚を贈って、息子を援助しないように計り、軍隊を動員し出陣させた(581年)。ヘルメネギルドは、妻をセビリャに残し、王国内のカトリック系の有力者とスエヴィ国王ミロの支援を得て、また、帝国軍の助力を当てにして、父の軍に対抗しようとした。だが、父王に買収された帝国の地方総督の援軍は得られず、とうてい勝ち目がないことを知った彼は、ある教会に逃げ込み立て籠もった。レオヴィギルドは、ヘルメネギルドの弟レカレドをその教会に遣わし、兄の説得に当たらせた。弟は兄に、父の前に平伏すれば父は貴方を許すであろうと告げると、それを信じた兄は父を呼び、その足元に身を投じた。父は息子を抱き起こして、優しい言葉をかけ、砦へ連れて行った。けれども、砦に到着すると、父は家臣に息子を捕縛させ、その美しい衣装を剥ぎ取って粗末な衣服を着せた。そして彼をバレンシア地方に追放してしまった。ところが、いくつかの都市がヘルメネギルドを支援したことに力を得て、彼は父に対して再び謀反を起こした。しかしながら、それも失敗に終り、彼はタラゴナにおいて捕えられ、ついに処刑されたのである。586年のことであった。そして、この父子の戦いの間、583年頃のことと思われるが、セビリャの宮殿にいた妻イングンドと幼い息子アタナギルドは、攻めて来た東ローマ帝国軍の捕虜となってしまった。アタナギルドは西ゴート王国の継承権を持っているので、帝国にとっては、外交交渉において使い道のある貴重な人質であった。翌年、この二人の人質は帝国の首都コンスタンティノープルへと護送されることになった。まず二人は、船で北アフリカへ送られたが、それから後の行方が杳として知れないのである。恐らく、585年頃、イングンドは移送の途中アフリカにおいて死亡し、アタナギルドだけがコンスタンティノープルに連れて行かれたものであろう。
イングンドの母ブルンヒルドは、この頃には、成人に達したアウストラシア王キルデベルト2世の摂政の地位を得ていたが、捕えられた娘と幼い孫の身の上を気遣い、その安否を知ろうと方々に懸命に働きかけていたようである。彼女は、イングンドの死を薄々知った後も、東ローマ皇帝マウリキウスを始めとし、皇妃コンスタンティナや帝国の聖俗諸高官に宛てて、孫アタナギルドの釈放を要請する多数の書簡を送っているのである。また、アタナギルド本人に対しても、肉親の身を案じ励ます内容の手紙を書いているのである。これらの書簡は、17世紀初頭にハイデルベルク大学の図書館の古文書の中から偶然発見され、「アウストラシア書簡」と呼ばれている極めて貴重な史料の一部分をなすものである(参考文献13)。それらを読むと、愛娘の生んだ孫に対するブルンヒルドの深い哀憐の情を感じ取ることができる。しかし、彼女の懸命の努力にも拘らず、アタナギルドは解放されることはなかった。悲運の王子アタナギルドのその後の消息を物語る史料は存在しない。(参考文献1,2,12,13)
10. カルタゴ事件
553年、東ローマ帝国は東ゴート王国を滅亡させ、イタリア半島は再び帝国の領土となった。ところが、当時、勢力を強めていたゲルマンの一部族であるランゴバルド族が、北方からイタリアに侵入し始め、その後帝国の拠点となるラヴェンナ周辺、ローマ周辺の教皇の領地および南イタリアを除く、イタリア半島の大部分を占領し、王国を建設した。568年のことであった。これを容認できない帝国は、キルデベルト2世とブルンヒルドの統治するアウストラシア王国を懐柔し、帝国軍との挟撃によって、ランゴバルド族をイタリアから追放しようという方策をとった。このランゴバルド族征討計画を実行するために、アウストラシア王国と帝国の間を何度も使節が往復した。アウストラシアもこの計画に乗り気であったが、その動機は、ランゴバルド族の信奉する異端アリウス派の打破という宗教的理由と、帝国の提供する多量の金貨であった。このときアウストラシアの使節がコンスタンティノープルへ携えて行った帝国宛の書簡のいくつかが、前節において述べられた「アウストラシア書簡」の中に見出されるのである(参考文献13)。そのうちの一つは、アウストラシアの三人の使者ボディギシルス、エウァンティウス、グリッポが持ち運んだもので、その内容は帝国軍の迅速な出動の要請であった。
この使節団は588年末頃にアウストラシアを出発し、危険な陸路を避けてマルセイユあるいはジェノヴァで乗船する海路をとった。そして、シチリアのシラクサを経由し、翌年春頃には、当時再び東ローマ帝国の領土となっていた北アフリカのカルタゴに上陸した。通常、ここで、使節団は長い滞在期間をおき、コンスタンティノープルにいる皇帝との面会が叶うように、そしてまた、以後の航海の安全や便宜を計ってもらうために、カルタゴの地方総督の指令を待つことになっていた。ところが、彼らがカルタゴに逗留している間に大事件が起こったのである。使者の一人エウァンティウスのある従者が、市内で、町の商人から商品を奪い取って自分の宿に逃げ帰った。後日、路上でこの従者を見かけた商人は、急いで従者を捉え、盗んだ品物を返すように激しく迫った。従者は逃げようとして剣を抜き、商人を斬り殺して宿に帰ったが、それを誰にも言わなかった。当地の市長は従者の犯行の知らせを受けると、大勢の兵士や市民を集め武器を持たせて、その夜使者たちが眠りについた頃、一行の泊まっている宿を襲撃させた。使者たちはたたき起こされ、何も知らぬ彼らが外へ出ると、興奮した暴徒たちの攻撃を受けた。ボディギシルスとエウァンティウスは彼らに斬殺された。もう一人の使者グリッポは、剣を持ち外へ出て、「我らは皇帝への和平の使者である。それを斬り殺すとは何事か」と大声で叫び、襲撃を止めるように説得した。それを聞いた暴徒たちは興奮から冷め、おとなしくなって引き揚げて行った。後に、地方総督がグリッポを訪ね、暴徒たちの非行を詫び、皇帝マウリキウスへの面会の手はずを整えてくれた。無事にコンスタンティノープルに到着したグリッポは、皇帝に面会し、使節としての使命を果たすことができた。そのとき、彼は皇帝にカルタゴでの事件の一部始終を話すと、皇帝はひどく狼狽し、この件については、キルデベルト2世の要望に沿って後始末をつけるという約束を彼に与えた。その後、590年頃、皇帝マウリキウスは、キルデベルト2世の使者を殺した事件の犯人であるという12名のカルタゴ人を引き連れた使節団をアウストラシアへ派遣した。彼らは手枷をつけられ、鎖で縛られていた。皇帝の使者は、キルベルト2世に、彼ら全員を処刑するか、あるいは、一人につき金貨300枚の賠償金を受け取り彼らを釈放するかのどちらかを選ぶように伝えた。キルベルトは、彼らの受け取りをためらい、彼らが果たして真犯人であるか否かを判断することは難しいと言った。生き残った使者グリッポは、真犯人は皇帝側の手によって処分されるべきであると主張し、結局、キルデベルトは改めて皇帝の下へ使者を派遣することにし、犯人たちも含めて彼らに故国へ帰るように命じた。史料には、この大事件の原因を作った張本人である従者の処分については何も語られていないが、たぶん、アウストラシア側から最も厳しい処断が下されたであろうと考えられる。(参考文献1,2,13)
11. 王女リグントの婚約
西ゴート王国の王子ヘルメネギルドゥスが、父王レオヴィギルドに対して起こした反乱が激化した頃、その報がアウストラシアに伝わると、キルデベルト2世は西ゴートへの出兵を計画した。それは、キルデベルトの母ブルンヒルドの主導によるもので、愛娘イングンドと孫アタナギルドの安否を案じ、その救出を目的とする企てであった。その頃、アウストラシア軍の下級兵士たちが反乱を起こして、当時のアウストラシアの最有力者たちを追放するという事件が起こり、それ以後、ブルンヒルドの政治的影響力が一段と強まっていたのである。けれども、その遠征が準備されたのは、西ゴートの内乱が終息して数か月後のことであった。従って、この戦いは、イングンドとアタナギルドの救出と同時に、レオビギルドに対する復讐という意味を持っていた。実際には、この遠征計画は実行されなかったのであるが、それに対抗するために、レオビギルド王は、ネウストリアとの同盟を求め、キルペリク王に使者を送り、次男のレカレドとキルペリクの娘リグントとの結婚を申し入れた。この婚姻政策は順調に進み、両人の婚約が相整った。
さて、王女リグントは、悪女と言われるフレデグンドの実子だけに、性悪の娘であった。彼女は、しばしば母を嘲り、女主人は自分なのだから母を元の奴隷に戻してやるなどと、ひどい悪口を浴びせかけた。母子の争いが絶えず、二人はよくつかみ合いの喧嘩をした。あるとき、魂胆があって、フレデグンドは、宝物庫へ娘を連れて行き、豪華な装飾品が一杯に詰めこまれた大きな箱を開いて、中の品物を次々に取り出しては娘に与えた。そして、あとは自分で好きなものを自由に取るように言った。そこで、リグントは箱の中に腕を差し入れて品物を取ろうとしたとき、母はいきなり蓋を閉めて、娘の首を強く打った。そのまま母は蓋を押さえつけたので、娘は首を締めつけられ目玉が飛び出しそうになった。近くにいた娘の侍女が大声で叫び、部屋の外にいた人々が駆け込んで来て、娘を助け出した。このようなことがあってからは、二人の仲は益々険悪になり、顔を合わせれば、互いに罵り合い、取っ組み合いの喧嘩をするのが常であった。
婚礼の日が近づき、リグントをスペインに迎えるために、西ゴート人の大使節団がパリに到着した。彼女には西ゴート国より莫大な結婚の贈り物が与えられた。そして、日頃いがみ合っていたとはいえ、さすがに母フレデグンドも娘との別れを惜しみ、金銀衣装など沢山の豪華な品物を贈った。これらの贈り物は膨大な量に上り、それらを乗せた荷車は50台に達した。そして、リグントの嫁入りの供をする大勢の下僕が集められた。彼らの多くの者は行くことを泣いて拒んだが、有無を言わさず強制され、逃げないように見張りがつけられた。彼らの中には、故郷を離れ、親しい人々と別れる辛さに耐えかねて、自殺をする者も多かった。いよいよ、婚礼の行列が出発するときには、パリの町は彼らの泣き声で満ち溢れた。リグントも泣きながら家族や宮廷の人々に別れを告げ、馬車に乗り込んだ。彼女の馬車が宮殿の門を出たとき、車軸の一つが音を立てて折れてしまった。それを見た人々は、「縁起が悪い」、「不吉な前兆だ」と言い合った。果たせるかな、パリを出て間もなく、隊列の一行が天幕を張り野営を初めて行った夜のこと、50人の男たちが最上の馬100頭と同数の黄金の馬具を盗んで逃亡し、キルデベルト王の下へ走った。それだけではなく、この旅が続く間いつでも、逃げる機会を見つけた者は、持てるだけの物を盗んで逃走したのである。キルペリク王は、この婚姻の行列が途中で兄のグントラム王あるいは甥のキルデベルト王の手の者に襲撃されるのではないかという疑念を持っていたので、これを軍隊で警護させていた。この旅に加わった者は全員で4000人を越えていたが、王はこの人々の旅費のために国庫から鐚一文も出さなかった。従って、彼らは通過する町や村で手当たり次第に略奪を行い、まるで戦いがあったかのように、彼らの通り過ぎたあとには何も残らなかった。
この略奪の隊列がスペインへ向かって進んでいるとき、キルペリクはパリの郊外シェルの荘園に滞在し、狩を楽しんでいた。ある日、王が狩から館に帰るとすでに夕闇が迫っていた。彼は馬から下りるため側に寄った従僕の肩に手をかけた。そのとき、何者とも知れぬ男が走り寄るや、短刀で王の脇腹を刺し、次いで下腹をえぐって、素早く逃げ去ったのである。多量の血が流れ、王は悪業に満ちたその生涯を終えた。584年のことであった。この王は人民に重税を課し、過酷に取り立て、まさに苛斂誅求を無慈悲に行った。また、彼は、たびたび自分の領土を荒し、焼き払い、それに何の苦痛も感じないどころか、むしろそれを楽しんでいた。彼が実行しなかった道楽や放蕩はないと言ってよかった。また、彼は人民に残酷な刑罰を課した。彼は裁判官に、「我が命令に従わぬ者あれば、その眼を刳り抜くべし」という文書を送った。まさに、彼はこの時代のネロであり、ヘロデであった。この暴君の遺体は、彼の二人の息子メロヴィクとクロヴィスが眠るパリのサン・ヴァンサン教会に埋葬された。キルペリク王を殺害した真犯人が誰であったのかは、ついに分からぬままであった。
ところが、王を暗殺させたのは実は王妃フレデグンドであるという噂が世間に広まった。悪巧みの権化とも言うべき彼女のことであるから、このような流言飛語が行き渡ったことは当然であろう。しかし、これが真実であるとはなかなか言い難い。なぜなら、この王妃は王を上手に操ることによって権力をほしいままにしてきたのであり、王という後ろ盾を無くすることは、彼女にとって大きな損失だと考えられるからである。ただ、この噂の根拠として、このとき王妃はすでに王との間に王子クロタール(後のネウストリア王クロタール2世)を儲けていたので、王を亡き者にした後、この幼い子を王と成し、自分は摂政として誰に遠慮することもなく、思う存分に権力を振るいたかったのだということはあり得るのである。けれども、その後のフレデグンドの行動を見ると、これも納得し難い。王の死後、彼女は王とともに滞在していたシェルからパリに帰り、財産を抱えて教会へ駆け込み庇護を求めた。さらにその後、彼女はブルグンディア王グントラムに使者を送り、夫の死を知らせ、「亡き夫の領国を差し上げるので、パリへお越し下さり、我が身と我が子の保護者となって頂きたい」と伝えさせたのである。間もなく、グントラムは パリに到着し、フレデグンドとその子クロタールは彼の庇護下に入った。ネウストリア王国の重臣たちは、まだ4か月にしかならない幼子クロタールのもとに集結し、故キルペリク王の支配下にあった諸都市に、グントラム王とクロタールへの忠誠を誓わせた。グントラムは、キルペリクやその家臣たちが不法に奪い取ったすべての財産を、法に基づいて元の持ち主に返却させた。その頃、アウストラシアのキルデベルト王の使者がグントラム王に会いに来て、フレデグンドの身柄の引き渡しを請求し、キルデベルトの次のような言葉を伝えた。「あの人殺し女を当方にお渡し願いたい。あの女は、我が伯母ガルスヴィント、我が父シギベルト、我が叔父キルペリク、我が従兄弟たちメロヴィクとクロヴィスを殺した。」こうしてみると、キルデベルトは、世上の噂のように、キルペリクを殺したのはフレデグンドであると思っていたのである。けれども、グントラムはその要求にはあまり取り合わず、応じなかった。
さて、王女リグントの婚礼の隊列はようやくガリア南部のトゥールーズの町に辿り着いた。この町からは目指す西ゴートの地も近く、行く手にこれから越えなければならないピレネーの山々を眺めることができるのである。一行は長旅に疲れ切って、衣服や履物もすっかり傷んでしまったので、もう一度旅支度をし直すために再出発を遅らせ、しばらくこの町に逗留することになった。その頃、キルペリクの家臣であった将軍デシデリウスの耳にキルペリク王暗殺の知らせが入ってきた。すぐさま、将軍は屈強の兵士を大勢集めて、リグントの一行を速足で追いかけた。彼は、トゥールーズの町に到着するや、直ちに王女を取り押さえ、その莫大な持参金と高価な財宝や調度品をすべて押収したあげく、彼女をある家に監禁し、厳重に見張りをさせたのである。こうして、豪華な婚礼の行列は完全に消滅し、婚約は事実上解消されてしまった。その後、リグントはトゥールーズの聖マリア教会に移されたが、母親のフレデグンドは使いの者をこの町へ派遣し、この上ない屈辱を受けた娘を手元に連れ戻した。それからというもの、フレデグンドは、娘の婚礼の旅に同行し逃げ帰った者を見つけると、すぐに捕えて不具の身体になるまで拷問を加えたという。(参考文献1,2)
12. ブルンヒルドの最後の奮闘
ブルグンディア、アウストラシア両王国は、同盟強化のため、587年に「アンデロ条約」を締結した。それは、ブルグンディア王グントラムヌスの要請により、彼と、アウストラシア王キルデベルト2世およびその母ブルンヒルドの三者が、アンデロの地に会合し、結んだ条約であって、その内容は、両国間において懸案となっていた領土問題、人民の所属問題、両国の相続権の問題その他に関する取り決めであった。それにより、もしグントラムが死去した場合、彼には男子がなかったので、ただ一人の王女クロティルドの相続分を除くブルグンディア王国はキルデベルトが相続することになったのである。一方、フレデグンドがグントラムに対し我が子クロタールともども庇護を願い出たことから、ブルグンディアとネウストリアの間の友好関係も進展していた。それはキルデベルトにアンデロ条約によるブルグンディアの相続権の喪失を危惧させたため、彼はグントラムに使者を送り、条約を無視してクロタールをブルグンディア王の後継者にすることのないように申し入れた。このあたりに、二人の甥を操り、主導性を取ろうとするグントラムの老獪な方策の影響が見られる。こうして、グントラムはとりあえずフランク王国に統一性をもたらし、ひとまず安定した政治的秩序を与えることができた。しかし、グントラムは、この統一政策を完遂することなく、592年に死没した。その結果、アンデロ条約に従って、キルデベルトがブルグンディア王国のおよそ5分の4の領土を相続することになった。ところが、キルデベルトもその3年後には25歳の若さで不慮の死を遂げ、貴族勢力の台頭と相俟って、王国の情勢は混迷の度を増していった。
キルデベルトの死後、長男のテウデベルト2世(11歳)がアウストラシアを、次男のテウデリク2世(9歳)がブルグンディアを相続した。この両王は若年であったので、祖母ブルンヒルドが摂政となり、その後数年間は、二人とも彼女の指導下にあって、共同統治体制をとっていた。始めのうちは、兄弟の協力関係は極めて順調に進み、両王国はネウストリアに対して攻勢を強め、その領土のかなりの部分を奪い取るほどであった。けれども、やがてこの体制はアウストラシア貴族の勢力増強に伴って崩れ始め、ついに貴族の影響下に置かれるようになったテウデベルトと、祖母の影響下に留まったテウデリクの間に対立が生じて、両者は敵対関係の度を深めていった。この争いの一つの原因として次のような事情もあった。それは、キルデベルト没後に定められた両分王国の支配領域がそれ以前とは異なっていたことである。詳しくは、テウデリクが相続したブルグンディア王国の領土は、旧ブルグンディア領に加えて、キルデベルト時代にはアウストラシア王国に属していたアルザス地方およびライン河沿いにボーデン湖からラエティア地方に至る地域にまで及んでいたのである。
599年頃、ブルンヒルドは、テウデベルトと彼を支持する貴族たちによってアウストラシアを追放され、ブルグンディア王テウデリクのもとに移った。その頃の出来事として、フレデガリウスの年代記は、次のような逸話を記している(参考文献13)。
「この年、ブルンヒルドはアウストラシアから追放された。ある貧しい男が、シャンパーニュのアルキス付近で、ただ一人さまよい歩いている彼女を見つけ、彼女に請われてテウデリクの所へ連れて行った。テウデリクは祖母を喜んで迎え入れ、とても丁重に扱った。ブルンヒルドは、その貧しい男に自分を案内してくれた返礼として、オーセールの司教職を与えた。」
608年、アウストラシア、ネウストリア両王国は、西ゴート、ランゴバルド両王国を抱き込んで、四か国の同盟を結成し、ブルグンディア王国を押し包んだ。このような動きに対抗して、ブルグンディア王国の摂政ブルンヒルドは、既に以前から、東ローマ帝国との同盟を目指し、当時のローマ教皇グレゴリウスに、皇帝マウリキウスへの仲介を依頼していた。その際の教皇からの返書が現存しているのであるが、その内容を見ると、ブルグンディア王国と帝国との同盟は成立する可能性が高かったことが推測されるという。ところが、ブルンヒルドにとっては不運にも、コンスタンティノープルの政変によって、皇帝マウリキウスが殺され、新皇帝フォーカスは、前皇帝とは異なり、ブルグンディア王国の敵であるランゴバルド王国との間に平和政策を推し進めたため、帝国との同盟は不可能となったのである。
612年、四か国同盟とブルグンディア王国の間の緊張は高まり、ついに兄弟の悲劇的な戦いが始まった。テウデベルトは弟の王国を攻撃したが、武運つたなく生け捕られ、投獄されてしまった。テウデリクとブルンヒルドは肉親のテウデベルトとその幼い息子メロヴィクの処刑を命じた。王を失ったアウストラシアの貴族たちは、ネウストリア王クロタール2世(フレデグンドの息子)を、王として王国に招き入れ、対策を講じた。一方、これに対抗しようとしていたテウデリクは、詳しいことは不明であるが、613年、予期せぬ死を迎えたのであった。そこで、ブルンヒルドは、まだ幼いテウデリクの長男シギベルトを王に据えることによって、摂政としてブルグンディア王国を操縦しようと試みた。ところが、このとき、ブルグンディアの貴族ワルナカルの裏切りによって、ブルンヒルドとシギベルトは捕えられ、敵クロタールの手に引き渡されたのである。もともと、ワルナカルという人物はブルンヒルドとテウデリクのこの上なく忠実な寵臣であったという。実は、この「忠臣」は、ブルンヒルドの摂政としての影響力に危機感を抱いていたので、また、クロタールとの戦いにブルグンディアが勝つ見込みがほとんどないことを知っていたので、既にかなり前から秘かにクロタール側と通じ合っていたのであった。彼は、ブルンヒルド捕獲の褒賞として、クロタールにより、ブルグンディアの宮宰職を与えられ、生涯クロタール王に仕えた。(「宮宰」とは、宮廷内の行政長官であって、この頃からその権勢を次第に強めていった。)ワルナカルの寝返りによって敵の手に引き渡されたブルンヒルドはもう80歳になっていた。ちなみに述べれば、彼女の不倶戴天の仇敵フレデグンドは、このとき既に肺結核を病んで死亡していたという。さて、フレデガリウスの年代記は、ブルンヒルドの最期を、次のように伝えている(参考文献15)。
「クロタール王の命により、ブルンヒルドは、三日の間さまざまのむごい拷問によって痛めつけられたあげく、毛髪と片手片足を荒馬の尻尾に固く括りつけられ、疾駆するその馬の蹄にかけられた彼女の体はばらばらに砕け散ってしまった。」
また、シギベルトとその弟コルブスは処刑され、もう一人の弟メロヴィクはネウストリアに流刑となった。かくして、邪魔者をすべて排除したクロタール2世は、フランク王国の再統一という、彼と同名の祖父クロタール1世と同様の功業を成し遂げたのである。(参考文献10,13,15)
エピローグ
争乱に明け暮れたメロヴィング王朝の歴史においては、613年のフランク王国再統一以来、クロタール2世とその長男ダゴベルト1世により638年まで統治された、わずか25年の期間が、最も平和で繁栄した時代であったと言えるであろう。けれども、その後はまたもや、地方に根を張る諸貴族の勢力が王家の力を凌ぐようになり、中でもとりわけ、アウストラシアの宮宰ピピン(2世)とネウストリアの宮宰エブロインが、頭角を現してきた。ピピンはサリー族ではなくリプアリア族の出身であった。両者はついに正面衝突を引き起こすに至り、687年、テルトリの戦いにおいて、アウストラシア軍が大勝した。その結果、ピピンはネウストリアとブルグンディアの宮宰をも兼ね、事実上、彼が全フランク王国を統治する形となり、これより後、メロヴィング王家は急速に衰退してゆくのである。
ところが、折も折、西欧世界にとっては思いもかけない一大突発事件が出来した。7世紀後期、東方より襲来したイスラム教徒の軍勢が、瞬く間に東ローマ帝国の領土であった北アフリカを席巻した後、さらに、711年には、ジブラルタル海峡を渡って、イベリア半島の大部分を征服し、西ゴート王国を滅亡させてしまったのである。そして、東はペルシアから、アラビア半島や北アフリカを包含し、西はスペインにまで及ぶ広大なイスラム教徒の帝国が出現した。その結果、地中海全域がイスラム帝国の支配圏に入ったために、地中海貿易を重要な経済的基盤としていたメロヴィング王家は大きな痛手を負い、それが没落の要因の一つになったのである。
さらに、勢いに乗ったイスラム軍はたびたびガリアの奥深くまで侵入するようになった。その頃、ピピン2世の子カール・マルテルは全フランク王国の宮宰職にあったが、732年、有名なトゥール・ポワティエの戦いにおいて、自らフランク軍を率いて、イスラム軍を撃破した。彼は、キリスト教世界をイスラム勢力の攻撃より救い、大きな名声を勝ち取った。メロヴィング王家はもはや完全に無力であったが、その血筋だけは細々と続いていた。ただし、カール・マルテルの晩年の6年間は、王座は空位のままであった。彼の死後、王家の一族の者ではあるが、血統不詳のキルデリク3世が有名無実の王位につけられた。749年にはカール・マルテルの子ピピン3世が全フランク王国の宮宰となり、その実力は他に並ぶ者がなく、権勢をほしいままにした。彼は、当時のローマ教皇ザカリアスと結託し、「実権を持つ者が国王となるべきである」という「お墨付き」の書簡を教皇から受け取り、751年、ついにフランク王国の国王に即位した。その見返りとして、彼は、ランゴバルド族の侵略から教皇を保護するため、二度にわたるイタリア遠征を行い、さらに彼らの占領していたラヴェンナからローマに至る地域を返還させ、それを教皇に献上したのである。このクーデターにより、最後の王キルデリク3世はその子とともに修道院に追いやられ、ここに、建国以来260年余り続いたメロヴィング王朝は歴史の舞台から消え去った。(参考文献7,8,12,15)
参考文献
1.トゥールのグレゴリウス 兼岩正夫・台幸夫訳 「歴史十巻(フランク史)I,II」 東海大学出版会
2.トゥールのグレゴリウス 杉本正俊訳 「フランク史 10巻の歴史」 新評論
3.オーギュスタン・ティエリ 小島輝正訳 「メロヴィング王朝史話 上・下巻」 岩波文庫
4.ジャクリーヌ・ダンジェル 遠山一郎・高田大介訳 「ラテン語の歴史」 文庫クセジュ 白水社
5.ルネ・ミュソ=グラール 加納修訳 「クローヴィス」 文庫クセジュ 白水社
6.ピエール・リシェ 久野浩訳 「蛮族の侵入」 文庫クセジュ 白水社
7.世界歴史大系 「ドイツ史1」 山川出版社
8.世界歴史大系 「フランス史1」 山川出版社
9.佐藤彰一 「ポスト・ローマ期フランク史の研究」 岩波書店
10. 佐藤彰一 「中世初期フランス地域史の研究」 岩波書店
11. 佐藤彰一 「歴史書を読む」 山川出版社
12. 鈴木康久 「西ゴート王国の遺産」 中公新書
13. 橋本龍幸 「中世成立期の地中海世界」 南窓社
14. 増田四郎 「西洋中世社会史」 岩波書店
15. Patrick J. Geary “Before France & Germany” Oxford Univ. Press
(平成21年7月20日記す)