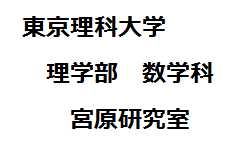東方のヴァイキング (平成21年浩洋会例会講演)
北ヨーロッパのユトランド半島からスカンディナヴィア半島にかけて住み着き、後にヴァイキング(あるいはヴィーキング)と呼ばれるようになった人々が、西暦8世紀末からおよそ200年間にわたって、ヨーロッパ各地を襲撃し略奪や殺戮あるいは土地の強奪を続けた。このヴァイキングの民は、ゲルマン民族の系列に属する人々であった。古代より広く北ドイツに住んでいたアングル族やサクソン族などのゲルマン人の一部が、郷里を捨ててさらに北方へ移動し、北欧各地において、農耕、牧畜、漁労などによる定住生活を送った。いわゆるヴァイキングなる人々は彼らの子孫なのである。彼らは、その人口が増加するに伴って、極めて活動的な民族に変貌してゆき、抑えきれぬ野望と冒険心に突き動かされたように、遠慮会釈なしに周辺の諸国を侵略し始めた。強い武力と高い技術を持っていた彼らを撃退することは困難で、ヨーロッパ諸国は彼らの侵攻に手を焼いた。彼らの活動範囲が広大であったことは驚嘆に値し、その行動は縦横無尽であった。彼らの活動のすべてが海賊行為であった訳ではなく、商業活動や殖民計画も積極的に行われていた。その行動の経路は広く東西南北にわたるものであった。南方への進路は、イングランドを始めとするヨーロッパ諸国の侵略を目的とするものであり、ノールウェーやデンマークのヴァイキングがこれに当たった。また、北方への進路は、毛皮やセイウチの牙などの採取を目的とし、船でノールウェー北端の岬を越え、ロシアのアルハンゲリスクに到り、なおもコラ半島を回って白海に入り込み、カレリア地方にまで達するものであった。さらに驚くべきことには、ヴァイキングたちは北極海のスバールバル諸島へも上陸していたという。そしてまた、西方へ進路をとったのは、ノールウェーを追われた少数の者たちであり、彼らは長い航海の後、アイスランドを発見しここに定住した。さらに彼らは、西方へと進みグリーンランドを発見、ここに殖民を行った。そして、ついに彼らは、コロンブスらによる新大陸発見よりも500年も前に、北アメリカ大陸に到達したのである。
1.ヴァイキングの東方への進出
本講の目的は東方へ進路をとったヴァイキングたちの活動の状況を述べることである。東へ向かったのは、主にスウェーデンの人々であった。バルト海は、ローマ帝国の時代から、スカンディナヴィア商人が活躍する海上交易の場であった。現在のスウェーデンの首都ストックホルムにほど近い位置にあったビルカという町が、バルト海交易の最大の中心地の一つであった。今はこの町は消滅して存在しないが、その遺跡が確認されている。スウェーデンの商人は、バルト海沿岸のみの商業活動に満足せず、7世紀後半から8世紀初期の頃には、大陸内を少しずつ東方へと進出を始めていた。彼らは、バルト海沿岸の町から、次のようなルートを経て、東の僻遠の地ガルザリーキ ( 彼らは現在のロシアの地をこのように呼んだ ) へと交易を拡大していった。すなわち、現在のラトヴィア共和国の首都リガより西ドヴィナ川を小舟でできる限り上流へ遡行し、上陸した後、幾日もかけて商品や舟を人力で運び、大河ドニエプルの上流に達すると、再び舟に乗り込み、この河を下って黒海へ向かった。また、これとは異なるルートで、バルト海を東進し、フィンランド湾の最奥部からラドガ湖に至り、この湖に注ぐヴォルホフ川を遡行し、さらにロヴォチ川を遡行した後、同様に、商品や舟を人力で運び、ドニエプル河上流に至る経路もあった。そしてまた、ラドガ湖から東へ進路をとり、ガルザリーキの奥地を進んでヴォルガ河上流に辿り着くと、この河を下って遂にカスピ海に出る者もいた。彼らはカスピ海をさらに1000kmも南へ航行して、セルクランド(彼らはイスラム教徒の支配する地域をそのように呼んだ)に到達し、商売を行った。
ドニエプル河は急流として有名であり、河下りの途中に早瀬や滝の難所がいくつもあった。そのような箇所にさしかかると、商人たちは、陸に上がって舟を引いたりかついだり、非常な難儀をしながら商品を運搬した。しかも、その途中で、ドニエプル沿岸からロシアの大草原地帯にかけて住んでいたペチェネッグ人と呼ばれるトルコ系の凶暴な遊牧民が、群れをなして商人たちを襲撃することがしばしばあったのである。そのため、商人たちは多人数で隊商を組織し、強力に武装して出発した。もともと彼らは、「右手に剣、左手に秤」と言われたように、純然たる商人ではなく、いわば半盗半商の荒くれ男の集まりであったから、土着民の襲来をさほど恐れてはいなかっただろう。彼らの集団は、西ヨーロッパ各地を震え上がらせたあの海賊ヴァイキングと少しも変わらぬ男たちの東方への遠征隊であったのだ。10世紀のアラブの外交官イブン・ファドランが、彼らヴァイキング商人たちを目撃して、述べた次のような証言が残されている。
「これまで私は彼らほど立派な体格をした者たちを見たことがない。彼らの身の丈はなつめ椰子のように高く、金髪で赤みがかった顔をしていた。彼らは上着もカフタンも身にまとわず、片側の肩だけを覆った衣服を着ているため、片腕は自由である。誰もが、斧、剣、ナイフを携行し、決して手放すことはしない。剣の刃は幅が広く、縦溝がついており、フランクの剣に似ている。・・・・・・ 神の創造物の中で、彼らほど不潔なものはない。大便や小便をしても身体をきれいにしないし、食後に手を洗うこともない。」(レジス・ボワイエ著 持田智子訳「ヴァイキングの暮らしと文化」)
彼らが取り扱っていた商品は、種々の毛皮、セイウチの牙、琥珀、刀剣、蜂蜜、蜜蝋などであったが、さらに、彼らはこの遠征の途中で、スラヴ人の集落を襲い、数多くの男女や子供を引っさらっては、奴隷として自分たちの商品に加えた。奴隷は、元手がかからず高値で売れたので、彼らにとっては毛皮と並んで最も重要な「商品」であった。こうして、彼らは、ドニエプル河を下り黒海に出た後、さらにその西海岸に沿って航行を続け、ついにビザンティン帝国(東ローマ帝国)の首都コンスタンティノープルに到達したのである。コンスタンティノープルは、北欧人が「ミヒクラガルズル」(偉大な都の意)と呼び、憧れて止まぬ都であった。郷里を出てからおよそ3000kmにも及ぶこの上なく困難な旅程を、幾多の日数を重ねて、ようやくにして到着したこの都において、彼らは携えて来た商品を売りさばいた。そして、美麗な衣服や絹製品、金銀細工品、香料、香辛料などを購入し、来た路を逆に辿って故郷へと持ち運んだのである。当時、使用されていた通貨は、ビザンティン帝国の金貨とアラブの銀貨であったが、イスラム帝国の支配地域において埋蔵量の豊富な銀山が発見されてからは、銀貨が次第に優勢となり、8世紀半ばを過ぎると銀が貨幣として用いられるほとんど唯一の金属となった。ヴァイキング商人たちが東方より持ち帰り蓄積した大量のアラブの銀貨が、今でも北欧の各地において発掘され、考古学上並びに歴史学上の貴重な資料となっているのである。
かくして、ビザンティン帝国やイスラム帝国と北ヨーロッパとの間の直接交易が、ヴァイキング商人たちの手によって行われ、長年にわたる商業活動を通じて持ち込まれた両帝国の成熟した文化が、北欧社会に計り知れない影響を与えたのであった。この史実について、20世紀前半のベルギーの著名な歴史家アンリ・ピレンヌは、その著書「中世都市」において、次のように述べている。
「およそ歴史の上で、ギリシア人の帝国とアラブ人の帝国の高度の文明が北ヨーロッパに及ぼした影響と、その媒介者がスカンディナヴィア人であったという事実ほどに興味深い現象はあまり存在しない。」
2.ロシアの建国
スラヴ人たちは遠来のヴァイキング商人たちを、「ルーシ人」と呼んだ。ルーシ人たちは、ガルザリーキの交易のルートのあちらこちらに商業上の拠点を設けたが、それらが次第に発展して大きな町を形成するようになった。そうした町に永住するルーシ人が漸次増加してゆき、彼らはそれらの町を基地として商業活動を行った。ラドガ湖の近くのノヴゴロドやドニエプル河中流域のキエフなどはそのようにして栄えた町々である。これらの町は、やがてルーシ人の指導者によって支配される公国に発展していった。1138年頃に書かれたロシアの「ネストールの年代記」によれば、862年、ルーシ人のリューリックがノヴゴロドを支配し、その初代大公となった。リューリックは17年にわたる統治の後死去したが、未成年の息子イーゴリの代わりに彼の親戚であったオレグが後継者となった。
一方、キエフは、リューリックの二人の部下であったアスコルドとディールによって建設された町である。ある日、キエフの町へ、北方から華美な衣装を身に着けた商人たちが、大勢の従者とともにやって来て、商売の取引をしたいので町の統領に会わせて欲しいと申し出た。商人たちは直ちにアスコルドとディールの所へ連れて行かれた。すると、彼らは、いきなり豪華な衣装の下に隠し持っていた剣を取り出し、アスコルドとディールや部下たちを斬り殺して、宮殿を占拠した。これらの商人を装った征服者の首領は、ノヴゴロドの大公オレグであった。オレグは、ノヴゴロドとキエフを合併し、こうして拡大されたキエフ公国の大公となり、ドニエプル河の支配者となった(882年)。ルーシ人、すなわちスウェーデンのヴァイキングたちが建設したこのキエフ公国は、後年の大帝国ロシアの母体となった。従って、ヴァイキングがあの大国ロシアの建国に関わっていたと言ってもよいのである。ちなみに、「ロシア」という名称は「ルーシ」が変形したものである。後に、「ルーシ人」はキエフ公国の住人一般を指すようになり、北方から到来したスカンディナヴィア人は、キエフの住民とは区別され、「ヴァリャーグ人」と呼ばれるようになった。この呼び名は、北欧人が自らを呼んでいた語に由来するものである。
キエフ公国は次第にその勢力を増強していった。そして遂に、オレグは、ヴァリャーグ人のみならずスラヴ人をも含む大遠征隊を組織し、コンスタンティノープルを攻撃するまでになったのである。この都市はその港を擁している金角湾の内部に敵船が入らぬように湾の入口に鉄鎖を張り渡し防衛していたが、キエフ軍は、ヴァイキング得意の方法、すなわち、人力により船を陸上で運ぶ手段を用いて対抗した。ある朝、首都の市民は、鉄鎖を避け陸路をとって湾内に入って来た多数の敵船が市の城壁に迫っているのを目にして驚愕した。時の皇帝ミハエルはあまり勇敢な人物ではなかった。彼はオレグに降伏し、キエフ側に極めて有利な条件を含む通商条約を承認せざるを得なかった。これは911年のことであった。その後間もなくオレグは死んだ。
オレグの死後、リューリックの息子イーゴリがその後を継いだ。イーゴリもビザンティン帝国に攻撃をしかけ、黒海沿岸や帝都の周辺を荒し回り、941年にはコンスタンティノープルを襲撃した。しかし、彼の船隊は恐るべき「ギリシアの火」の反撃を受け完敗を喫し、故国に逃げ帰るしかなかった。「ギリシアの火」とは、その製法を帝国が極秘にし続けたため、未だにその正体が不明であるが、たぶん、ナフサと硫黄の混合物に火をつけ強力なふいごを用いて敵船に噴射したものであろうと考えられている。帰国したイーゴリは、復讐を期して、祖先の地スカンディナヴィアのヴァイキングたちや、あの凶暴なペチェネッグ族にまで使者を送り、大軍召集の準備を始めた。それを知った皇帝は戦いを避けるためにイーゴリに使者を遣わし、944年には両国の間に新たに平和条約が結ばれることになった。だが、この条約は、以前のものに比べて、キエフ側に有利な内容のものとは言えなくなった。しかも、キエフ大公は、皇帝が戦いに際して必要とする数の兵士を帝国に提供しなければならなくなった。ヴァリャーグ兵の勇猛さは帝国においても夙に有名であり、その名は天下に轟きわたっていた。帝国軍の兵士が不足し始めていたこともあり、皇帝は、外国人傭兵として、強力なヴァリャーグ兵の帝国軍への参入を強く望んでいたのである。帝国軍の勇敢で忠実な兵士として次第にその地位を高めていったヴァリャーグ兵は、後に、皇帝の親衛隊を形成することになる。
イーゴリは、国内では徴税改革を断行したが、945年、増税を不満に思ったスラヴ人に暗殺されてしまった。彼の息子スヴャトスラフは未成年であったので、妻のオリガが摂政としておよそ20年の間統治を行った。オリガは957年にコンスタンティノープルでキリスト教の洗礼を受けたが、これがキエフ公国におけるキリスト教普及の始まりであった。ところが、息子のスヴャトスラフは、キリスト教への改宗を拒み、異教徒のままで通した。彼の体内にはまだヴァイキングの荒々しい血が流れており、彼は極めて好戦的な大公であった。彼が初めて組織した騎兵部隊は後の有名なコサック騎兵の原型となった。彼は帝国を脅かしていた隣国ブルガリアの攻撃を皇帝に約束し、その地を占領したが、それを皇帝に返還することを拒否した。そこで、皇帝はブルガリアへ大軍を派遣し、スヴャトスラフとの間に講和を結んだ。そして、スヴャトスラフは軍を率いてキエフへと帰国したが、その途中、ドニエプル河の早瀬においてペチェネグ族の急襲を受け、この戦いで彼は命を落としたのであった(972年)。
スヴャトスラフの死後、長男のヤロポルクが後継者となったが、兄弟の間で権力闘争が始まった。この争いの中で、末弟のヴラジミールはスカンディナヴィアへ亡命せざるを得なくなったが、この地で多くのヴァイキングたちを兵士として集め、帰国に備えた。彼は、兄ヤロポルクが支配しているキエフを攻め、これを征服して、兵士に兄を殺させたのである。こうしてヴラジミールはキエフ大公の地位を得た(980年)。しかし、スカンディナヴィアから連れて来られた傭兵たちは、十分な報酬を与えられなかったので不満を募らせ、ヴラジミールは暴れ者の彼らをもてあますようになった。ちょうどその頃、ビザンティン皇帝バシレイオス2世は、帝国内の反乱鎮圧のため、ヴラジミールに援軍を要請してきた。これはキエフ大公にとって大変好都合なことであった。彼はその扱いに困っていたヴァリャーグの傭兵たちをそっくり援兵としてコンスタンティノープルに送り込み、この兵たちをこちらに送り返す必要はないと皇帝に伝えたのである。ヴラジミールには、援軍派遣の見返りに、皇帝バシレイオス2世の妹アンナが公妃として与えられることになった。ただし、ヴラジミールのキリスト教への改宗がそのための条件であった。彼は、これを受け入れ、さらに家臣全員にドニエプル河で洗礼を受けるように命じた。このときからキリスト教がロシアの地において広く流布していったのである。一方、皇帝に与えられたヴァリャーグ兵たちはその猛勇と忠誠を見込まれ、皇帝の親衛隊として帝都の宮廷に留まった。そして、その後、親衛隊員の数は一定に保たれ、不足した場合には常にスカンディナヴィアから補充された。こうしてヴァリャーグ兵のみから成る皇帝の親衛隊は、1453年、ビザンティン帝国がオスマン・トルコ軍によって滅亡させられるまで、長く存続したのである。
3.イングヴァールの大遠征
アイスランドにおいて12世紀から14世紀にかけて編纂された「サガ」という散文形式の文学作品がある。その題材は北欧の、神話、伝説、英雄物語、史伝などであるが、これは、その文学的価値のみにとどまらず、歴史においても非常に貴重な史料として大きな意義を持っている。その中に「イングヴァールのサガ」と呼ばれる物語があるが、本節の内容はこの作品からとったものである。
11世紀初期、当時スヴェア王国と呼ばれていたスウェーデンに、一人の冒険心旺盛な若者が現れた。その若者は名をイングヴァール・ヴィトフェルリといい、生まれは1016年頃である。彼は、王族の一員であったが、20歳の頃、母国では望んだ地位が得られないことを知ったので、海外遠征により富と名声を獲得しようと故郷を離れる決意をしたらしい。1036年、彼は、30隻の舟を率いて、ガルザリーキへ向けて母国を後にした。その総勢は600~1000名と思われる。彼は、1節で述べたルートに従って隊を進め、キエフに到着した。当時のキエフ大公は前節に登場したヴラジミールの息子のヤロスラフであったが、ヤロスラフの妻インゲヤードはスヴェア国王アーヌンド・ヤーコブの妹であり、イングヴァールの父親の従兄妹であった。その頃スヴェア王国とキエフ公国とは婚姻により、良好な関係を保っていたのである。「ネストールの年代記」によれば、ヤロスラフがノヴゴロドに滞在しているときに、キエフがペチェネグ人に攻囲され、彼がその撃退のためヴァリャーグの傭兵隊を用いたのが、ちょうど1036年のことであったという。そうすると、この傭兵隊は、イングヴァールが率いて来た遠征隊そのものであったという可能性もあるのである。つまり、スヴェア王国の派遣した援軍としてペチェネッグ人を撃破することが、イングヴァールの海外遠征の目的の一つであった、とも考えられるのである。この遠征隊はスヴェア王アーヌンド・ヤーコブの命令により組織されたものであること、また、以前からヴァリャーグ商人が航行するドニエプル河流域がペチェネッグ人の襲撃によって脅かされていたので、この脅威を取り除くことは東方交易に重点を置いているスヴェア王国にとって大きな利益となること、を考えれば、上述のような可能性は大いにあり得るのである。それはともかく、上記の年代記によれば、キエフ軍およびヴァリャーグ傭兵の混成軍とペチェネッグ軍との戦いがキエフの近傍で行われた。ペチェネッグ軍は大軍であり、血みどろの戦闘が続けられたが、夕暮れになってようやくキエフ側が勝利を得たという。
イングヴァールはキエフに3年ほど滞在した。その間、彼は、各地を巡り歩いた商人やコンスタンティノープルから帰還したヴァリャーグ兵に出会い、遠い異国の珍しい事物や戦いの様子などさまざまの話を聞くことができた。そうするうちに、彼は、好奇心をかき立てられ、さらに遠隔の地に脚を伸ばして、未知の世界を探検してみたいという欲求を抑えられなくなったに違いない。彼は、東方への遠征を志し、ヤロスラフの支援を得て、その周到な計画と準備にとりかかった。故国を出たときから遠征に加わっていた兵士の中には死亡したり病にかかったりした者もいたので、キエフのヴァリャーグ人から新たな兵員を補充し、ついにイングヴァールの率いる30隻の舟から成る遠征隊がキエフを出発した。1040年の春のことであった。彼らは数週間をかけてドニエプル河を下り黒海に出た。そして、黒海を海岸沿いに東へ進み、グルジア王国に到着した。彼らは、この王国の首都クタイシに滞在して、ここで商いをするとともに、舟の修理や装備の点検を行い、これからの旅に備えた。その後、彼らは、コーカサス山脈の南を流れ黒海に注いでいるリオニ川を小舟でできるだけ遡った後、舟をロープで引きながら標高1000m 近いスラミ峠を越えて、分水嶺の向こう側にあるクラ川の上流にまで達した。そしてクラ川を舟で下ってティフリス(現在のトビリシ)に到着したが、一行は大変な歓迎を受け、しばらくの間ここに逗留した。しかし、グルジア王国では内乱の兆しがあり、精強なヴァリャーグ兵を味方につけようとした王の計画に巻き込まれそうになったイングヴァールは、ティフリスを離れることにし、クラ川を下った。ところが、途中で彼らの舟はギリシア人の海賊に襲われ、「ギリシアの火」の放射を浴びて数隻の舟が炎上してしまった。このような災難に会いながらも、イングヴァールはクラ川の流れに任せて漕ぎ進み、ついに目的のカスピ海に出たのであった。冬には旅を控えていただろうと思われるので、おそらく、キエフ出発以来ここまでおよそ1年ほどの月日を要したのではなかろうか。クラ川の河口は現在のアゼルバイジャン共和国の首都バクーの南方100km余りの位置にある。河口のすぐそばにルシアと呼ばれる小島があるが、驚くべきことに、ある時期この島はヴァイキングに占領されていたという。
実は、今まで述べてきたルートは、シルクロードから派生した古くから知られている交易路であって、マルコ・ポーロの「東方見聞録」にも記述されている。また、グルジア王国の古い「グルジア年代記」に、イングヴァールの遠征と同じ時期に北欧人の集団がこの経路を通過したことが書き残されているが、これは彼らの一行に関する記事である可能性が非常に高いという。「イングヴァールのサガ」によれば、カスピ海に達したイングヴァール隊は、カスピ海を東に横断し、カラ・ボガズ湾に向かった。なぜ彼らがこのような辺鄙で砂漠に近い荒れた土地を訪れたのか理解に苦しむところである。ただ、この地はシルクロードの通過する地域に近く、砂漠の向こうには、ホレズム王国や、ブハラ、サマルカンドといった繁栄している都市があったことを考えるとある程度は納得できるかも知れない。しかし、彼らがカスピ海まで辿り着いた以上は、さらに舟を進め、人口が多く豊かなカスピ海南岸部セルクランドへ向かったことは間違いない。そこまで行けば、コンスタンティノープルにも匹敵するイスラム帝国の大都市バグダッドまで旅することも可能なのである。ところで、遠征隊が携えていた沢山の商品はどうなったのであろうか。苦難の旅の途中で紛失したり破損することはなかったのか。商品がなくてどのように商売をするというのか。でも心配は無用である。彼らはもともと半盗半商のヴァイキングなのであるから。けれども、当時のイラン北部は、セルジュク・トルコが侵攻していた時期で、極めて政情不安定な土地であった。従って、この地域では交易どころか略奪すら困難であっただろう。
ともあれ、「サガ」によれば、幾月かの後、イングヴァール隊は「交易」に大きな成果を上げ、その船隊は積荷を満載し、セルクランドを後にして帰路についたという。ところが、往路を逆に辿りクラ川を遡ってグルジア王国に入ったとき、彼らはとうとう激しい内乱に巻き込まれてしまった。止むを得ず戦いに加わった彼らは、勝利を収め、ここでまた多くの戦利品を獲得した。この時点までは、隊における死亡者の数はさほど多くはなかった。しかし、往路と同様の山越えの難儀の後、黒海沿岸に向かう下り坂にさしかかったときに、思いもかけぬ悲劇が一行を待ち受けていた。疫病が彼らを襲ったのである。それは赤痢あるいはマラリアではなかったかと思われる。兵士の半数以上が斃れ、隊長イングヴァールも帰還を果たすことなくこの世を去った。1041年のことであった。故国を後にして5年の歳月が過ぎていた。
指導者を失った隊員たちは、帰路の取り方などについて意見が合わず、ついに分裂してしまった。このとき、12隻の舟しか残っていなかったが、キエフに戻る者、ビザンティン皇帝の親衛隊員を志願しコンスタンティノープルを目指す者など、別々の行動をとることになり、多くの舟が消息を絶った。帰国することにした兵士たちは、キエフで一冬を過ごした後、春には郷里へと向かった。その年の晩夏のある日、憔悴しきった彼らを乗せた数隻の舟が、ようやくにしてストックホルムの入り江に辿り着いた。遠征に参加した兵士のうち何名の者が帰還できたのかは不明である。彼らは、イングヴァール遠征隊の経験した一部始終を国王に報告した後、帰らなかった仲間の親族にその事情を克明に知らせた。親族のある者は、旅の途上遠い異国で死んだ者を偲び、ルーン文字(1世紀頃に作られ、ゲルマン人が使用した文字)を刻んだ記念の石碑を建てた。その石碑はストックホルムの周辺のあちらこちらに現存しており、その数は30余りにのぼる。これらのルーン石碑と「イングヴァールのサガ」とが、本節で述べられた物語がおおむね事実であることを示しているのである。そして、イングヴァールの遠征をもって、スヴェア人による大規模な東方遠征は幕を閉じた。東方のヴァイキングの時代の終焉であった。
4. ヴァイキング王ハーラル・ハードラーダ
11世紀に入ると、北欧諸国においてもキリスト教が普及し、ヨーロッパ諸国を震撼させたヴァイキングの侵攻も終息に近づいていた。この時期、勢力を増大させたのはデーン(デンマーク)王国であった。デーン王クヌートは、20年という短い期間ではあったが、デンマークとイングランドにまたがる「北海王国」に君臨した。ノールウェー王オーラフ・トリュグヴァソンがクヌート王に敗れた後、その後継者オーラフ・ハーラルソン王は、祖国ノールウェーの奪還を目指して、1030年、勝つ見込みのない悲劇的な戦闘に身を投じ、英雄的な死を遂げたのであった。このとき、ハーラルソンの異父弟ハーラル・ハードラーダ(1015~1066)は、まだ15歳であったが、自ら望んでこの戦いに加わっていた。そして、重傷を負った彼は、森の中へ逃げ込み、ある農民の家にかくまわれた。傷が癒えた後、彼は祖国を後にし、スヴェア王国に落ち延びた。ここで、彼は同じように敗走して来た多くの戦友たちに再会し、ともにキエフ公国へと向かった。当時のキエフ大公は、前節に登場したヤロスラフであった。ハーラルは、ヤロスラフに仕え、親衛隊の指揮官に任ぜられた。ここで、ハーラルは、ヤロスラフの娘エリザベートと相思相愛の恋仲となってしまった。それにも拘らず、この亡命者は、湧き上る冒険心を抑えることができず、愛する恋人を置き去りにし、500名の兵士を率いてコンスタンティノープルへと赴いたのである。
ハーラルは、この憧れの帝都で皇帝ミハエル4世の親衛隊長となり、ある年、イスラム教徒の侵入が激しくなってきた東方のセルクランドへ派遣された。その後さらに、これまたイスラム勢力の増強しているシチリア島へ、ヴァリャーグ兵の部隊の指揮官として出陣を命ぜられた。スカルド詩(北欧の詩)において、ハーラルがこの島の沿岸部を占領した武勲が詠われている。しかし、これは、シチリア島におけるイスラム軍の侵攻に対する帝国軍の防衛が成功した最後の戦いとなった。この島は、その後100年間ヨーロッパ人の手に還ってくることはなかったのである。1040年と1041年には、南イタリアで発生した反乱鎮圧のため、皇帝はヴァリャーグ兵を送り込んだが、最初の年にはハーラルも従軍したと見られる。ところが、その直後に彼は、反乱が起こったブルガリアへと派遣されたため、命拾いをすることになった。というのは、南イタリアに残ったヴァリャーグ部隊は反乱軍と激闘を繰り返し惨敗した結果、膨大な数のヴァリャーグ兵が戦死したからである。この反乱軍の中には、フランスのノルマンディーからやって来た多数のノルマン人の傭兵がいた。彼らの祖先は、100年ほど前に、はるばるスカンディナヴィアからフランスへ移り住んだヴァイキングだったのである。ヴァリャーグ兵の祖先もヴァイキングであった。共通の祖先を持つ者同士が、南イタリアの地で、敵味方に分かれて激しく戦ったことは、奇しくも痛ましい運命であった。ハーラルは、遠征からコンスタンティノープルへ帰った後、今度は聖地イェルサレムに出向を命ぜられた。当時、ヨーロッパから聖地へ向かう巡礼者が盗賊やイスラムの無法者に襲われることが多く、聖地への巡礼路の治安が非常に悪くなっていた。彼はこれらの悪党どもを排除し、巡礼者を保護するために派遣されたのである。これは後年の十字軍や修道会の活動の先駆けをなすものであった。
皇帝ミハエル4世が没し、その後継者としてミハエル5世が帝位についた直後、ハーラルは、皇帝に所属すべき戦利品を自分のものにしたという理由で、投獄されてしまった。ところが、この皇帝には信望がなく市民の反乱が勃発し、それが拡大するさなかに、皇帝に背いたヴァリャーグの親衛隊の手によって、ハーラルは獄中から解放されたのである。即位後わずか4か月で帝位を追われたミハエル5世は捕えられ、抜眼の刑に処せられた。そして、ミハエル4世の妃ゾエと結婚することにより、コンスタンティノス9世が新皇帝となった。ハーラルは新皇帝に祖国ノールウェーへの帰還を願い出たが、認められなかった。そこで、彼は秘かに帝都を脱出せんと、部下とともに2隻のガレー船に乗り込み金角湾の波止場から出航したが、湾の出口には鉄鎖が張られていた。彼はこの鎖を強引に乗り越えようとしたが、彼の船は成功し、もう一隻は船体が真っ二つに折れてしまった。多数の溺死者を出したが、泳げる者を救った後、彼の船は黒海を北へと向かった。順調な航海の後、ドニエプル河を遡行し、船は無事にキエフに到着した。1042年のことであった。
ハーラルは、彼の帰りを待ち侘びていたヤロスラフ大公の娘エリザベートに求婚し、大公の承諾も得て、結婚した。キエフ帰還の翌年の春、彼は新妻とともに故国ノールウェーへと旅立った。戦いに敗れ、止むなく亡命の旅を始めてから、もはや10余年が過ぎていた。今や、彼は、ビザンティン帝国の軍人として幾多の勲功を立て、夥しい財宝を携えて故郷に錦を飾る、いわば凱旋将軍であった。彼が率いて来た艦船は、いずれも豪華に飾り立てられ、緋色に輝く帆をなびかせながら、故国の海を航行した。このとき、首都トロンヘイムにおいては、彼の異父兄であった前王オーラフ・ハーラルソンの息子マグヌスが、ノールウェー王として君臨していた。ハーラルは甥マグヌスを追い落とそうとして、トロンヘイムに進撃した。ところが、マグヌスは、当時としては珍しく柔和な性格の王であって、流血を嫌い、荒々しい叔父に権力の分割を申し出た。ハーラルはこの妥協案を受け入れ、マグヌスの死ぬ1047年まで共同統治することになったのである。そして、マグヌスの死後はハーラルの専制政治が行われた。彼はデーン王スヴェンと激しく争い、ユトランド攻撃のための軍事基地としてオスロを建設した。そして、デーン王国の重要な商業の中心地ハイタブ(現在のシュレスヴィヒ)を全滅させてしまった。しかし、激しく戦ったこの二人の王は、その後和睦し、互いの主権を尊重することを誓い合った。
時は1066年の秋、ハーラル・ハードラーダの最後の冒険が待っていた。当時イングランド王国においては、王エドワードの死後、直臣のハロルドが王の遺言を守ると称して王座についていた。一方、イングランドの対岸の地ノルマンディー公国の領主ウィリアムが、エドワードとの間の王位譲渡の約束を楯にとって、イングランド王位をハロルドから奪おうと計画を練っていた。そして、準備を十分に整えた彼は、英仏海峡を隔てたノルマンディーの地に大船団を集結させ、風が追い風に変わるのを今か今かと待ち続けていたのであった。ところが、ここにもう一人、イングランドの王冠を狙っている男がいたのである。それは他ならぬハーラル・ハードラーダであった。そのいきさつは次のようなものである。イングランド王ハロルドの弟トスティは、兄王から全軍の司令官に任ぜられていたが、その傲慢で粗野な性格は臣下の強い反感を買い、彼はイングランドを追われ国外へ逃亡しなければならなくなった。兄からの助けを得られなかった彼は、他国の武力を借りて祖国へ帰る道を選んだ。まず、彼は、デーン王国に走りスヴェン王にイングランド侵攻をそそのかしてみたが、すげなく断られたので、次に、ノールウェー王ハーラルを訪ねたのである。冒険好きのハーラルはこの話に大いに乗り気になった。イングランドを攻略しハロルド王を打ち破った暁には、ハーラルがイングランド王となること、そしてトスティはまずウェセックス伯の地位を得て、ハーラル王の次の王となること、が取り決められた。
1066年9月、ハーラルはトスティを伴い1万の軍を率いてヨークへ向かって進軍し、ゲート・フルフォードの地で大勝利を得た。このときロンドンにいたハロルド王は、王位簒奪をもくろみ北と南から同時期に攻めて来る二人の敵を相手にしなければならなくなったのである。そこでハロルドは、まず北方のハーラル軍を電撃的に壊滅させ、すぐに南にとって返しウィリアムの船団を待ち受けるという策をとった。ハロルドは2万の大軍を率いて素早くヨークの町に入った。うかつにもそのことを全く知らなかったハーラルの軍は、ヨークの北方14kmのスタンフォード・ブリッジに来たときに、待ち構えていたハロルドの大軍の予想外の迎撃を受けたのである。それはゲート・フルフォードの戦いの丸一日後のことであった。イングランド軍は始めはノールウェー軍の猛烈な矢の雨に阻まれ、前進することができなかったので退却した。ノールウェー軍は逃げる敵を追いかけた。実はこれは見せかけの退却であった。罠にはまったハーラル軍は、待ち受けていたイングランド軍の弓矢隊の激しい攻撃を受けた。そして、飛来した一本の矢がハーラルの首を貫いた。稀代の豪勇ハーラル・ハードラーダも、ここで遂に武運尽き、まさに波瀾万丈の生涯を閉じたのである。結局、この戦いで勝利を収めたのはハロルド王であった。彼はハーラルの遺体をノールウェーの首都トロンヘイムへ送り返した。
それからわずか二日後に、ヨークにいるハロルド王のもとに、ノルマンディー公ウィリアムの軍団が海峡を渡りサセックス海岸に上陸したという知らせが届けられた。イングランド王は直ちにヨークを立ち南方へ急いだ。そして間もなく、ハロルドとウィリアムは有名なヘイスティングズの戦いを迎えた。しかし、わずか19日前のスタンフォード・ブリッジの戦いにおいて、ハロルドは力を使い果たしてしまっていた。ウィリアムの勝利は当然の結果であった。ウィリアムはイングランド王位を獲得し、ここにノルマン王朝が始まったのである。それにしてもウィリアムはこの上ない好運に恵まれた。なぜなら、ハロルドがハーラルを迎え撃つために北上し、南方にハロルド軍がいなくなったまさにその時に、英仏海峡を吹く風の向きが逆転し、ウィリアムは海峡を無事に渡ることができたのであるから。もし、このときの風向きがいつまでも変わらず、ウィリアムの海峡渡航が大幅に遅れたとしたら、どのような結果になったか分からない。また、もし、ハーラルが、もっと用意周到に戦いを計画し、ハロルド軍とウィリアム軍の戦闘が終った直後にイングランド侵攻を開始していたなら、歴史の流れは大きく変わっていただろう。ともあれ、ヴァイキング王ハーラルとヴァイキングの末裔ウィリアムの直接対決は遂に見られなかった。優劣をつけ難いこの二人の剛の者同士の対決が、もし実現していたならば、さぞや興味深い場面が展開されたであろうにと、筆者は非常に残念に思うのである。
(平成21年11月 記す)