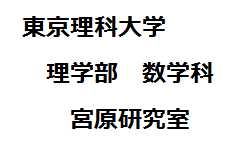フィレンツェの秘話 (平成23年浩洋会例会講演/改訂版)
有名な歴史小説家塩野七生女史の著書に、「愛の年代記」(新潮文庫)という作品がある。これは、主に中世からルネサンス期にかけてのイタリアの歴史に題材をとった9編の短編小説を集めたものであるが、それらは、大体のところ、史料やその他の文献を基礎として、かなり史実を考慮した骨組みが作られ、さらに小説としての魅力的な肉付けがなされている。読んでみると、どの編も大変に味わいがあり、一つを読み終えると次の物語へと進み、止められないのである。その中でも、第1話の「大公妃ビアンカ・カペッロの回想録」、第2話の「ジュリア・デリ・アルビッツィの話」について、筆者は特に興味を引かれることになった。これらは話の内容自体が面白い上に、それぞれに意外な驚くべき後日談があって、歴史に関心を持つ者には、「これぞ歴史観想の醍醐味である」と思わせ、興趣尽きないからである。それでは、この二つの物語を以下にご紹介しよう。
1 大公妃ビアンカ・カペッロ
ビアンカ・カペッロは、ヴェネツィアの貴族の娘として生まれた。今からおよそ470年ほど前、1543年頃の生まれである。彼女は幼い頃に実母を亡くし、父は後妻を娶るが、この継母はビアンカに冷たく当たり、父親も娘を大切に扱わなかった。家庭の愛情に恵まれなかった彼女は、16歳の頃、ピエトロというフィレンツェ出身の平民の男と恋仲になった。この関係がビアンカの両親に認められるはずもなく、二人は、ある夜ヴェネツィアを捨て、ピエトロの父が住んでいるフィレンツェへと逃亡したのである。直ちにヴェネツィア政府は、貴族の子女誘拐の罪でピエトロの首に賞金をかけ、二人は追われる身となった。彼らは、辛い逃避行の末、やっとのことでフィレンツェの町に辿り着いた。彼らはこの地で正式に結婚し、聖マルコ広場に面しているピエトロの父の家にかくまわれたが、追っ手を恐れて外出することはできなかった。こうして、1年余りが過ぎた頃、窓から聖マルコ広場を眺めていたビアンカを、ちょうど広場を馬で通り過ぎていた一人の貴公子が目にとめ、彼女に挨拶を送って去って行ったのである。その後、彼は度々広場に現れ、二人は互いに挨拶を交わすようになった。その貴公子は、メディチ家の中興の祖と言われているトスカーナ大公コジモ1世の長男フランチェスコであった。今を時めく大公の世継ぎであったのだ。
そうしたある日、ある貴族の夫人を介して、フランチェスコがビアンカに会いたいという意向をピエトロの父に伝えてきたのである。大公の後継者からの申し出であるから、夫ピエトロを始めとして一家は、大きな見返りを期待し、浮き浮きとしてビアンカをフランチェスコに差し出した。こうして、彼女は大公の世継ぎの愛人となったのである。ビアンカは18歳、フランチェスコは独身で21歳であった。そして、職のなかったピエトロにはメディチ家の使用人の身分が与えられた。3年余りの月日の後、フランチェスコは、ハプスブルク朝のドイツ皇帝フェルディナント1世の息女ジョヴァンナ・ダウストリアと結婚することになった。以後10数年にわたり、ビアンカはメディチ家の別荘に住まいを与えられ、フランチェスコの愛人としての生活を送ることになるのである。
1572年以降、ビアンカの周辺には不幸が相次いだ。まず、夫のピエトロが、ある貴族の未亡人とねんごろな仲となったため、その親族の男たちにつけ狙われ、とうとう殺されてしまった。1574年には、絶対君主として権勢をほしいままにしたトスカーナ大公コジモ1世が病死した。フランチェスコは33歳にして、その後を継ぎ、イタリアの四大強国の一つであったトスカーナ大公国の君主となった。そして、それから数年後にはフランチェスコの正妻ジョヴァンナが急死してしまった。彼は、人目もはばからず、妻の死後わずか2か月にして、ビアンカと再婚したのである。フランチェスコは、君主としては非常に変わった人物であって、若い頃から政治にはあまり関心がなく、化学、錬金術、生物学などに異常な興味を抱いていた。彼は、ヴェッキオ宮殿に実験室を備え、毎日のようにこの部屋に引き籠っては、種々の薬品や品物を製造していた。また、彼は沢山の珍しい文物を収集していたが、後にそれらを陳列し、人々に公開することにしたのである。それが有名なウッフィーツィ美術館の始まりであったという。しかし、当時、民衆は、彼が実験室で毒薬を作りビアンカを使って妻ジョヴァンナを毒殺させたのだなどと、まことしやかに噂した。二人はフィレンツェ市民には人気がなかったのである。それというのも、フランチェスコには当時すでに枢機卿となっていた弟フェルディナンドがいたが、この弟は兄夫婦を極度に嫌悪し、根拠もない二人の悪評を巷間に宣伝させていたからである。フランチェスコは、この弟を始めとする周囲の猛反対を押し切って、ビアンカに大公妃としての公式の地位を与え、各国の特使を招待し、大公妃の戴冠式を盛大にとり行った。この式には、彼女に追っ手を差し向けたヴェネツィア国の特使までが出席した。
ビアンカが大公妃になって8年後、1587年秋のある日、大公夫妻はフィレンツェ郊外の別荘において、夕食をとった直後に激しい病に襲われ急死した。そのとき、その別荘には夫妻を憎悪していた弟のフェルディナンド枢機卿がちょうど居合わせ、彼らと食事をともにしたのだが、フェルディナンドは無事だったので、彼が夫妻に毒を盛ったのではないかという噂が広まった。けれども、医師の診断によって二人の死因はマラリアであるとされた。大公の遺体は、メディチ家の墓所である聖ロレンツォ教会に葬られたが、大公妃の棺は、フェルディナンドの命令により、大公と引き離され、別の場所に埋葬されたのである。その墓がどこにあるのか未だに知られていない。また、ビアンカにはアントニオという名のまだ幼い男児が一人あったが、本来なら大公の世継ぎであるべきこの息子は、一生陽の当たらぬ生活を送ったという。大公夫妻の死後、フェルディナンドは、枢機卿の職を辞し、3代目のトスカーナ大公となった。彼の親族に対する極めて冷酷な仕打ちにもかかわらず、彼は兄とは違って政治家として優れ、温情ある統治を行ったので民衆に人気があった。彼の時代にトスカーナ大公国はかつてない繁栄を謳歌し、後年、彼はメディチ家最後の名君と称賛されるまでになったのである。
さて、今年の1月のある日、筆者はナショナル・ジオグラフィック・チャンネルで、2009年製作の「フィレンツェの秘密」というテレビ番組を見ていた。それは、フィレンツェの歴史上の秘密めいた種々の事柄について次々に解説してゆくものであったが、そのある箇所で、筆者は凝然として画面に見入ってしまった。今まで述べてきたフランチェスコとビアンカの死が取り上げられていたからである。彼らは弟フェルディナンドに毒殺されたという噂はあったが、死因はマラリアであると片付けられ、以後420年余りずっと、それが史実として信じられてきた。ところが、医学史研究者のフィレンツェ大学教授ドナテッラ・リッピ女史の調査によれば、二人の死後直ちに検死解剖が行われ、そのとき作成された報告書が現在残っているというのである。その内容は、当時検死に当たった三人の医師のうち、メディチ家の担当医は死因はマラリアだと判定したが、他の二人の医師たちの所見は、大公夫妻の腸がともに異常にただれていることから、毒物による死であるというものであった。そこで、リッピ教授は、毒死説を裏付けるべくフランチェスコの墓を発掘し、内臓を取り出して化学分析を行ったのである。フランチェスコの遺体は聖ロレンツォ教会に葬られたが、どういう訳か、彼の肝臓は検死後フィレンツェ郊外のサンタ・マリア・ア・ブオニスタッロ教会に埋葬されていた。リッピ教授が地下の埋葬所を掘り起こしてみたところ、キリスト像と容器の破片、そして複数個の肝臓の断片が見つかった。彼女は、入手した肝臓の細片をフィレンツェ大学医学部に提出し、鑑定を依頼した。その結果、組織から得られたDNAが遺骨から採取されたフランチェスコのものと一致した上、かなりの量の砒素が検出されたのである。毒死説は真実であった。おそらくは、当時の噂の通り、フェルディナンドによって仕組まれた毒殺であろう。彼は、兄夫妻をただ単に嫌っていただけではなく、以前から大公の座を虎視眈々と狙っていたに違いない。彼は、夫妻の子アントニオが成人になる前に、二人を同時に亡き者にする必要があると考えたのであろう。フェルディナンドが大公夫妻の別荘を訪れ、食事をともにしたあの時はその絶好の機会であったのだ。
かくして、リッピ教授の粘り強い探査により、フィレンツェ史の永年の謎が解明された。ちなみに、このリッピ教授は、ルネサンス中期にフィレンツェで活躍した大画家フィリッポ・リッピ(1406~1469)の子孫だということである。
2 ジュリア・デリ・アルビッツィ
これも、第1話とほぼ同じ時期のフィレンツェを舞台とする物語である。すなわち、メディチ家のフランチェスコ1世がトスカーナ大公としてフィレンツェを統治していた時代の話である。フィレンツェにおいても、他の都市国家と同様に、メディチ家が台頭するはるか以前に古い貴族階級が衰退し、商業や金融によって実力をつけてきた新興勢力、いわゆるブルジョワジーが政治を牛耳るようになっていた。14世紀末頃に、その中心にいたのがアルビッツィ家であって、後にメディチ家との熾烈な抗争に敗れ、その後塵を拝することになるのだが、アルビッツィ家といえばフィレンツェでは有数の名家であった。ジュリアは、1563年頃にこの旧家アルビッツィ家の庶子として生まれた。彼女は同家の三男と使用人の女との間に生まれたのである。同家は生まれたばかりの赤子と母親を実家の両親の家に引き取らせた。しかし、母親は間もなく病死し、父親もジュリアがまだ幼い頃に死んだ。父親はジュリアを認知していたので、彼女はアルビッツィの姓を名乗ることができた。その後、アルビッツィ家からは定期的に養育費が届けられ、彼女は祖父母の庇護の下ですくすくと育ち、やがて美しい娘に成長していった。
ジュリアが21歳になったある日のことであった。突然アルビッツィ家の使いが来て、彼女に明朝同家に来て欲しいと伝えたのである。翌朝、何事であろうかといぶかりながらも、いくばくかの期待感を持って彼女が同家に赴くと、当主を始めとする多くの男たちの待ち受ける広間に通された。その中には、トスカーナ大公フランチェスコの側近の大臣までがいた。彼らは一斉に彼女に熱意のこもった好奇の視線を向けた。そして、別間に連れて行かれた彼女は、同家の当主から思いもかけない実に奇妙な要請を受けたのである。
それより少し前の話であるが、マントヴァ公国の世継ぎヴィンチェンツォ・ゴンザーガの結婚相手の候補にトスカーナ大公フランチェスコの息女レオノーラの名が挙がった。ところが、そのときヴィンチェンツォの父のマントヴァ公が、レオノーラの継母である現大公妃(第1話の中心人物ビアンカ・カペッロ)をあげつらって、「愛人上がりの女に育てられた娘など息子の嫁には欲しくない」と言ったため、この縁談は立ち消えとなった。そして、ヴィンチェンツォの花嫁として選ばれたのは、パルマ公の孫娘マルゲリータであった。この婚約は何の障害もなくまとまり、華やかに婚礼がとり行われたのだが、何と、花嫁の身体上の欠陥のため、この結婚は成立せず破談となってしまったのである。その結果、一旦立ち消えとなっていたトスカーナ公女レオノーラとの縁談が再び浮上することになった。ところが、今度は大公妃ビアンカ・カペッロが以前にマントヴァ公から受けた侮辱を忘れてはおらず、その意趣返しに「前回の破談の原因にはヴィンチェンツォ殿の方にも肉体的欠陥があったのではないのか、そうでないと言うのなら、それを証明して欲しい」と言い出し、それを婚約の条件の一つとしてつきつけたのである。これはマントヴァ公国側には大きな恥辱であったが、いろいろな状況からこの条件を受け入れざるを得なくなった。そして、ヴィンチェンツォの肉体的健全さを証明するための「実験台」として、指名されたのがジュリアだったのである。彼女はこの要求を拒絶することはできなかった。もしそうしたならば、これまでアルビッツィ家から彼女に与えられてきた養育費は直ちに止められ、彼女の一家は明日からでも路頭に迷うことになるに違いない。ジュリアには、その代償として、メディチ家から多額の金貨と結婚相手が与えられることになった。当時はルネサンス末期であって、近世に足を踏み入れようとする時代ではあったが、まだまだ、このように「貴族にあらざれば人にあらず」という、理不尽で非人道的な仕打ちがまかり通っていたのである。
間もなく、ヴィンチェンツォとレオノーラの婚儀が盛大にとり行われ、その翌年、ジュリアは、与えられた持参金を持って、メディチ家お抱えの楽師カッチーニのもとへ嫁いで行った。筆者の推定によれば、極めて興味深いことに、このカッチーニこそは、イタリア・オペラの揺籃期にフィレンツェで活躍し、もう一人の楽師ヤコポ・ペーリとともに、作品が現存する世界最古のオペラの作曲者として、音楽史上に燦然と輝く人物なのである。ジュリオ・カッチーニは、1550年頃ローマに生まれ、既に10代の頃にその優れた楽才をトスカーナ大公コジモ1世に認められて、メディチ家の宮廷楽師として雇われていた。彼は同家のリュート弾きと歌手を長年にわたって務め、1618年にフィレンツェでその生涯を終えた。彼は、作曲家であると同時に卓越した歌手でもあったが、現代でも好んでとり上げられる歌曲「麗しのアマリッリ」に見られるような、彼の音楽の特色である流麗な旋律は、歌手としての体験から生まれたものであろう。
オペラは、「カメラータ」と呼ばれる、フィレンツェの音楽家、詩人、学者、芸術愛好家が形成する小さな集団の手によって誕生した。カメラータの最も古いメンバーの中には、かの大科学者ガリレオ・ガリレイの父であるヴィンチェンツォ・ガリレイがいて、このグループの理論上、実践上の基礎となった著作を書いていた。実践に当たって主に活躍したのは、詩人リヌッチーニ、作曲家ペーリ、カッチーニらであった。カメラータの活動も、ギリシア・ローマの古典文化の復活を目指したルネサンスの革新運動の一つであって、その目標は古代ギリシアの音楽劇を再現することであった。この集団が、手に入る限りの古代の文献を参考にたゆまぬ研究と討論を行った結果、生み出されたものが「オペラ」という全く新しい形式の音楽劇であった。世界最古のオペラは、リヌッチーニの台本にペーリが作曲した「ダフネ」(作曲1594年、初演1597年)であるが、残念ながら、その楽譜は断片的な2曲以外には残っていない。全編が現存する最古のオペラは、1600年、リヌッチーニの台本にペーリとカッチーニがそれぞれ別々に作曲した「エウリディーチェ」である。両作品とも、フランスのブルボン王朝の始祖であるアンリ4世とトスカーナ大公フェルディナンド1世の姪マリア・デ・メディチとの結婚の祝典のために作曲されたものであるが、ペーリの曲(その一部分はカッチーニが作曲)は、1600年、メディチ家のピッティ宮殿で上演され、翌年出版された。カッチーニの曲も同年出版されたが、1602年まで完全な形では演奏されなかった。(D.J.グラウト著 服部幸三訳「オペラ史」上巻による。)
ついでながら、上に述べたマリアというのは、前トスカーナ大公フランチェスコ1世と妻ジョヴァンナとの間に生まれた息女であり、マントヴァ公国へ嫁した先述のレオノーラの妹である。当時、巨額の借金を抱え財政難に窮していたフランス王アンリ4世が、メディチ家からの莫大な持参金を目当てにして、この結婚がとり決められたものである。現トスカーナ大公フェルディナンド1世は、姪マリアの将来について大変に気を遣っていたようで、大国の王とのこの婚姻を積極的にととのえようとしたと思われる。むろん、大国フランスと交誼を結ぶことはフィレンツェにとって大変に有益なことではあったが、それだけでなく、マリアの父を毒殺したフェルディナンドには、罪滅ぼしの気持ちがあったであろうし、先々代のドイツ皇帝フェルディナント1世の孫である彼女を粗略に扱うことはできなかったのであろう。マリアの夫アンリ4世はもともと多情な男であったし、巨額の持参金だけに魅力を感じていた彼とマリアとの間に夫婦の愛情はなかったという。フランスではマリー・ド・メディシスと呼ばれたこの王妃は、宮廷においては「太っちょの女銀行家」とあだ名された。彼女の依頼により、フランドルのバロック絵画の巨匠ルーベンスが描いた一連の大作「マリー・ド・メディシスの生涯」はルーヴル美術館の呼び物の一つとなっている。
なお、カッチーニと結婚した後のジュリアの生活がどのようなものであったかについては全く知られていない。おそらく、当時は身分の低かった楽師の妻として目立たぬようにひっそりと暮らしていたのであろう。1600年の記録によれば、その頃には、彼女はもうこの世を去っていたという。
(平成23年12月2日記す)