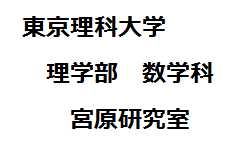フランスとドイツの起源 (平成27年浩洋会例会講演)
フランス、ドイツ両国家の起源を考えるとき、西ローマ帝国の滅亡(西暦476年)の後ほどなく、ライン川下流域に建国されたフランク王国にまで遡らなければならない。この王国は、ライン川を渡り帝国領に侵入して来たサリー・フランク族の首領クロヴィスにより、486年に創建された。クロヴィス王の強力な統治により、フランク王国は、当時の諸王国の中で最も強大な勢力を持つ国家に成長していった。クロヴィスに始まるこの王朝は、「メロヴィング王朝」と呼ばれているが、およそ250年の後、この王国の大貴族であり宮宰として権勢を振るっていたピピンが企てたクーデターにより滅亡した。ピピンは新しい王朝の初代国王となった。彼の死後、息子のカールが後継王となり、カールが統治した時代に、フランク王国は領土を拡大し、かつての西ローマ帝国の領土にほとんど匹敵するほどの大国に発展していった。この王朝はカールのラテン名カロルスにちなんで「カロリング王朝」と呼ばれている。西暦800年、カールはローマの地において、教皇レオ3世により皇帝位を授けられ、フランク王国は「フランク帝国」となった。それは既に消滅していた「西ローマ帝国」の復活であった。旧帝国と異なる点は、その基盤として「キリスト教」が据えられていたことである。キリスト教を中心とするカールの優れた治政により、帝国は経済的にも文化的にも大いに繁栄し、一つの大きな共同体となった。これは現代にまで連なる「ヨーロッパ」の誕生である。カールはその偉大な業績により「大帝」と呼ばれた。
カール大帝の死(814年)の後、広大なフランク帝国は大帝の長男ルイに相続された。ルイは、「敬虔帝」と呼ばれるほど、篤い信仰心を持った人物であって、教会政策には力を注いだが、一般の政治上の能力については凡庸で、大帝国を統治する指導力に欠けていた。ルイは帝位継承に関して規則を定め、長子ロタールを後継者に指名した。これに不満を抱いた弟たちルートヴィヒとシャルルは、父ルイ敬虔帝の死後、連携して兄ロタールと対立し、抗争を続けたのである。そして841年、「フォントノワの戦い」で、ロタールは敗北した。その翌年、「ヴェルダン条約」が取り決められ、帝国領は三兄弟により三つに分けられることになった。末弟シャルルは西方の地域(西フランク王国)を、次弟ルートヴィヒは東方の地域(東フランク王国)を獲得し、兄ロタールは中央部の地域(ロートリンゲン)、プロヴァンスおよびイタリア半島(中フランク王国)を得た。大帝の死後、わずか30年足らずで大帝国は崩壊したのである。さらに、ロタールの死後、中フランク王国北部のロートリンゲン地方は、ルートヴィヒとシャルルによって分割され、東および西フランク王国に組み込まれた。大雑把に言えば、こうしてでき上がった西、東、中フランク王国が、それぞれ紆余曲折を経て、近代のフランス、ドイツ、イタリア三国へと変貌してゆくのである。この三兄弟の子孫たちの間で、その後も紛争が相次ぎ、非常に複雑な分裂、併合を繰り返した後に、870年に成立した「メルセン条約」によって、現代の独仏伊三国の領土の基本的な輪郭がほぼ定まった。
カール大帝の治世の頃より、ノルマン人と呼ばれる北方の民族ヴァイキングが、船団を組み大挙してヨーロッパ各地の襲撃を頻繁に繰り返していた。歴代の皇帝や諸国の王たちはその対処に手を焼いていた。885年、西フランク王国の主都パリにも、ヴァイキングの戦士たちは押し寄せてきた。彼らは北海からセーヌ川を船で遡り、パリを包囲したのである。これに対し、当時の西フランク王シャルル2世(肥満王)は何らなすすべがなく、その無能ぶりをさらけ出した。そのとき、パリ伯に任じられていたロベール家のウードの獅子奮迅の活躍により、ヴァイキングたちは撃退された。そのため、民心はシャルル肥満王から離れ、代わってウードが王となった(888年)。しかし、ウードの在位はわずか10年であって、王位は再びカロリング家に戻り、シャルル3世(単純王)が王となった。彼もヴァイキング対策に困惑したあげく、苦肉の策として、パリの西方、現在のノルマンディー地方一帯を許可なく占拠して住み着いていたノルマン人の一味の首領ロロを呼び出し、その地帯を封地として正式に与える代わりに、北方より新たに侵入して来るヴァイキングたちを撃退してほしいと要請した(911年)。ロロはこの要求を承諾した。その結果、ヴァイキングの襲撃はフランスでは次第に減少し終息に向かった。ロロが得た地はノルマン人の名にちなんでノルマンディーと呼ばれたが、その後、大いに繁栄し、ノルマンディー公国となった。この強大な公国の6代目の当主ギョーム(ウィリアム)は、大船団を率いてイギリス海峡を渡り、イングランド王国を攻略して、その地にノルマン王朝を打ち立てることになる(1066年)。
シャルル3世以後、フランスの王位は、カロリング家とロベール家の間を行き来したが、遂に、987年にカロリング朝は断絶し、ロベール家のユーグ・カペーがフランス王となった。これ以降の王朝をカペー王朝という。カペー朝初期の王は周囲をノルマンディー、フランドル、ブルゴーニュ、シャンパーニュ、アキテーヌ、アンジューなどの大諸侯に囲まれ、その圧力に苦しみ、王としての権威などほとんどなかった。カペー家の領地の中心はパリであった。パリには尚書局、裁判所、会計検査院など種々の統治機関が置かれ、パリは首都としての政治的重要性を漸次増していった。そして、パリにほど近いランスの聖堂や王家の墓所であるサン・ドニ修道院などはパリに宗教的威厳をもたらした。また、当時、フランス北部で使用されていたオイル語がフランス語の主流となり、パリは文化的にもフランスの中心地となっていった。王家は、フィリップ1世の時代に王位世襲権を確立し、戦闘を繰り返しながら、次第に勢力を伸長させ、12世紀末期の王フィリップ2世(尊厳王)の時代には、王権は著しく強化された。しかも、フィリップ2世の母はカロリング家の血を引き、また、同王は、カール大帝の娘の嫁ぎ先であったエノー伯家より妃を迎え、次の王ルイ8世を生んだ。このようなカロリング家との血統上の結びつきは、カペー家の権威を一層高めた。
一方、ドイツ(東フランク王国)では、911年にカロリング王朝の男系の血統が断絶した。乱立する諸邦から有力者が集まり、次期の王として、カロリング王家の縁戚に当るコンラート1世を選出した。しかし、コンラートは、その政策が諸侯の反発を招き、彼らと戦わざるを得なくなったが、敗北を重ね、王国は分裂、解体の寸前にまで追いやられた。彼は死の直前に、諸侯の中からザクセン大公ハインリヒを後継者として指名した。このハインリヒ1世の努力によってドイツ王国は再建され、その政権は安定した。彼は巧妙に諸侯の同意をとりつけ、王位世襲の原則を導入することに成功する。そして、936年、彼の息子オットーが即位した。これが史上有名なオットー1世(大帝)であるが、彼の治世前半には反乱が続出した。とりわけ、長子のリウドルフは父王に対し大反乱を起こし、一時は王が危険な状況にさえなった。しかし、リウドルフは強暴なマジャール族(ハンガリア人)を味方に引き入れ、彼らが王国の各地を劫略したことで、多くの同盟者が彼を見離し、反乱は失敗に終わった。955年、マジャール人は大挙してドイツ領内に侵入して来た。オットーはレヒフェルトの地で彼らを迎え撃ち、戦いはドイツ軍の決定的勝利に終わった。この輝かしい軍功がドイツ王オットーのヨーロッパ世界における威信をこの上なく高めることになった。
その後、イタリア王ベレンガリオがローマ教皇領に侵入した際に、教皇からの救援要請を受けたオットーは、大軍を率いてアルプスを越え、侵略者を打ち破った。助けられた教皇からオットーは皇帝位を受け取った(962年)。しかし、オットー軍がドイツへ引き上げると、この教皇はベレンガリオと共謀し、ビザンツ帝国やマジャール人に働きかけ、オットーに対抗しようと企てた。これを知ったオットーは再びイタリア遠征を行い、ローマ教皇を廃位、ベレンガリオを追放して、自らイタリア王となった。かくして、オットーは、カール大帝に始まったヨーロッパ世界を支配するローマ的皇帝の地位を継承したのである。オットー以来、皇帝には、ローマ教皇の承認を得て、ドイツ王が就任するという伝統ができ上った。後年、このドイツ人の帝国は「神聖ローマ帝国」と命名されることになる。
オットー大帝の子と孫のオットー2世および3世は帝位を世襲し、「西ローマ帝国の復活」という理念をも受け継いだ。オットー2世は、それを実現すべくイタリアの地に進軍したが、志半ばにしてローマにおいてマラリアのため死去した(983年)。わずか28歳の若さであった。そのとき、長男のオットー3世はまだ3歳の幼児であり、叔父に当るバイエルン大公が王位簒奪を画策していた。オットーの母テオファノはかのビザンツ帝国の皇女であった。彼女は幼いオットーの摂政として、多くの有力諸侯を敵に回し、支持者に援助されながら、我が子の王位を守り抜いた。成長したオットー3世が王としてとった最初の行動は、イタリア遠征とローマでの皇帝戴冠であった。995年、大軍を率いてアルプスを越えた彼は、ローマにおいてイタリアの全諸侯に臣従の誓約をさせ、イタリアの支配権を承認させることができた。しかし、ローマ教皇や教会を自らの支配下に置き、ローマを帝国統治の中心地にしようというオットー3世の意志は、イタリアの貴族たちの強い反感を買った。オットーがドイツへ帰った後すぐにローマで反乱が発生する。彼は再びイタリアに赴き、ローマを完全に制圧して、反乱者の厳しい処罰を断行した。彼は、永遠の都ローマをドイツ帝国の首都とし、彼の帝国統治が「西ローマ帝国の復活」であることを明確に意図した。このような考えをローマ人たちは決して受け入れてはいなかったし、また、ドイツ人たちは、皇帝がドイツの地を長期間不在にしていることを不快に思っていた。遂に、1001年、大反乱が出来し、オットーはローマから一時避難を余儀なくされた。駆けつけた援軍とともにローマ奪還を目指す行軍の途中で、彼はマラリアのため死亡した。享年わずか21歳であった。彼は独身であったので、帝位は傍系のハインリヒ(2世)に引き継がれたが、彼にも男子がなく、1024年、彼の死とともに、ザクセン家の王朝は5代にして途絶えた。その後、帝位は主として、ザリアー家、シュタウフェン家へと移ってゆく。およそ3世紀半に及ぶこれら三王朝の時代は、ドイツ史において特別な意味を持っており、後世のドイツに重大な影響を与えた。
前述のように、フランスでは、王家が王権の強化に大いに努め、15世紀末頃には統一国家が形成された。そして遂に17~18世紀には、ルイ14世(太陽王)を頂点とする絶対王権国家が出現する。その一方で、ドイツは、オットー大帝という偉大な祖先を持ちながら、諸邦に分裂した状態のままで長い時代を過ごし、19世紀後半に至るまで遂に国土を統一することができなかった。それゆえに、近世に至って、ドイツは、既に強大な勢力を有する統一国家を作り上げていたスペイン、イギリス、フランスなどの諸国に比べて、海外発展すなわち貿易や植民地獲得の競争において甚だしい遅れをとったのである。
その理由は容易に理解できる。オットー大帝以来、ザクセン、ザリアー、シュタウフェン三王朝を通じて、歴代の皇帝たちのほとんどは、「帝国理念」すなわち、かつてのカール大帝の時代のような「西ローマ帝国の復活」という大層な観念にとりつかれていた。その呪縛から解放されることなく、彼らはイタリア支配に拘泥し続け、大軍を率いてのイタリア遠征を度々繰り返した。その結果、ドイツ本国の統治がおろそかになって、ドイツ人たちの不満が鬱積してゆき、皇帝に対する人民の信頼は薄らいでいった。しかも、遠征に必要な莫大な費用の大部分は、ドイツ諸侯の援助に頼るしかなかったが、彼らも何の見返りもなしに軍資金を差し出すはずがない。彼らは、関税徴収権、裁判権、貨幣鋳造権、領地購入権など、種々の特権の認可と引替えに軍費を提供した。そのような事態が頻発したために、ドイツ諸侯は次第に強い勢力を持つようになって、皇帝が諸邦を支配下に置いてドイツの国土統一を成し遂げることなど到底不可能となり、その影響が近世にまで及んだのである。
参考文献
1 世界歴史大系 「フランス史1」 山川出版社
2 世界歴史大系 「ドイツ史1」 山川出版社
3 五十嵐修 「地上の夢・キリスト教帝国」 講談社選書メチエ
4 菊池良生 「神聖ローマ帝国」 講談社現代新書
5 田辺保編 「フランス学を学ぶ人のために」 世界思想社
(平成27年12月記す)