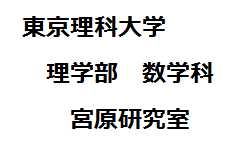奇跡の歌曲 ~ 一期一会のシューベルトとハイネ
歌曲の王と呼ばれるウィーンの作曲家フランツ・シューベルト(1797~1828)の死の約1年後に、彼の遺した歌曲を集めた歌曲集「白鳥の歌」が出版された。彼の次兄フェルディナントが彼の遺稿の中から見つけ出し、出版社ハスリンガーに引き渡してでき上がったものである。全部で14曲から成るこの歌曲集は、シューベルトの最晩年の作品の一つであるが、どの歌をとっても実に見事な傑作である。その中でも特に、第8~13曲の6曲は、同年生まれのもう一人の天才ハインリヒ・ハイネ(1797~1856)の詩に作曲されたもので、この歌曲集の他の曲とは全く趣を異にする。ハイネの6編の簡潔な詩のそれぞれに、異なる、驚くべき曲想が与えられており、シューベルトが歌曲の分野において斬新な境地を開いたものだと言われている。これらのうちの何曲かは彼の歌曲の最高傑作と言ってよいだろう。もし、彼がもう少し長生きしていたなら、ハイネの詩によってさらに多くの歌曲の傑作が生まれていたであろうにと、まことに残念な思いを禁じ得ない。その仕事は、シューベルトより10歳余り若い作曲家ローベルト・シューマンによって受け継がれた。シューマンは50数曲のハイネの詩による歌を作曲した。それに比べ、わずか6曲しか存在しないシューベルトとハイネの歌曲、しかし、これらはまさに珠玉のような作品であって、どの曲も例えようのない美しさと魅力に満ち溢れている。シューベルトが生涯に作り出した600を超える膨大な数の歌曲の中で、たったの6曲しかないからこそ、これらは極めて高い価値を持つのだ、とも言えるだろう。ハイネが詩集「歌の本」をハンブルクのカンペ社から刊行したのは1827年10月であった。シューベルトが死去したのはその翌年11月のことである。彼はその年の9月頃から体調を崩していたから、それ以降はまともに仕事ができる状況にはなかったであろう。従って、彼が「歌の本」に出会い作曲できたのは、1年にも満たない短い期間に限られていた。その時期に彼が「歌の本」をたまたま手に取り、その中からわずか6編を選んで美しい歌曲に仕上げた――その出会いこそ、まさしく一期一会であり、あたかも奇跡が起こったかのような出来事である。
シューベルトは、1797年1月31日、小学校の教員であったテオドールの四男として、ウィーン郊外のリヒテンタールに生まれた。幼い頃から音楽の才に優れ、彼にピアノを教えていた12歳上の長兄イグナッツが「フランツは2、3か月で長足の進歩を遂げ、自分がもう追いつけないほどの名手になっていた」と言うほどであった。そこで、彼はリヒテンタール教会のコーラス指導者ミヒャエル・ホルツァーに預けられ、歌やオルガンなど音楽全般の指導を受けることになった。11歳のときには、教会の第一ボーイ・ソプラノをこなし、時々先生に代わってオルガンを見事に弾くまでになった。この先生は、フランツ少年の才能を伸ばすために、自分の豊かな知識を存分に与え、あらゆる努力を惜しまなかった。そのような折、オーストリア・ハンガリー王室の少年合唱団(ウィーン少年合唱団の前身)に空席が二つでき、彼は、ホルツァー先生の勧めにより応募することになった。試験では抜群の成績を示し、審査員でもあったウィーン宮廷楽長アントニオ・サリエリ(モーツァルトのライヴァルとして有名)の強力な推薦により、見事に合格した。
合唱団員はウィーン大学付属神学校の給費生と同じ待遇を受けることができた。しかし、フランツにとっては、12歳から16歳まで続けた神学校の寮生活は、部屋は汚いし、厳しい規則に縛られ、まるで囚人の生活のように苦しいものであった。けれども、ここで受けた高度の音楽教育は、彼の才能を養い育む上で申し分なく、彼はピアノやヴァイオリンの演奏に熟達し、作曲も行うまでに成長していった。このような彼の音楽への熱中ぶりは父の気に入らず、一時は勘当を受け、彼の母の死に目に会えないという悲しむべきこともあった。また、一方では、この神学校において、彼は、文学的な素養も培われ、ゲーテの作品まで深く読むことができるようになったが、このことは、後年、彼の歌曲作成に際して非常に良い影響を与えたに違いない。ところが、音楽や文学の勉学は順調であったものの、数学の成績が極めて悪かったために、フランツはとうとう神学校を退学しなければならなくなったのである。その後、彼は、兵役を免れるため、教員養成機関である聖アンネン学校に入学し、10か月後には助教員の資格を得た。これは父を非常に喜ばせ、フランツは父が校長を勤める小学校の助教員に採用されることになった。聖アンネン学校時代は、交響曲第1番を始めとする多くの作品を生み出し、シューベルトにとって作曲家として実りの多い時期であった。この頃、彼は17歳になっていたが、テレーゼ・グローブという初恋の女性が現れた。絹織物工場の経営者の娘であって、美人ではなかったが、非常に美しいソプラノの声を持っていた。彼が作曲したミサ曲がリヒテンタール教会で初演されたときには、彼女がソプラノのパートを歌ったのである。二人は相思相愛の仲であったらしいが、フランツの収入が低いことからテレーゼの父が結婚に反対し、この恋は実らなかった。しかし、この時期に、彼は、ゲーテの詩による二つの素晴らしい傑作「糸を紡ぐグレートヒェン」、「魔王」(その他にもおよそ140編の歌曲がある)を作曲している。彼は、17歳にして、革新的な、しかも完成度の高い歌曲を創造できるほどの能力を示しているのである。それだけではなく、この間には、四つのオペラ、交響曲第2、3番、ピアノソナタ2曲、その他多数の作品を生み出していた。シューベルトの頭脳にはまさにミューズ(音楽の女神)が住み着いていた。
シューベルトは多くの良き友人に恵まれた。彼は背が低く小太りで、風采は見栄えがしなかった。性格も内気で引っ込み思案であったが、交際下手の反面、率直で快活なところもあり、人と一旦打ち解けた後には胸襟を開いて親密に付き合うという面を持っていた。彼の最初の友は、神学校で一緒に学んだヨーゼフ・フォン・シュパウンという人物であった。シュパウンは、シューベルトより9歳年上で、後に法律家となるが、生涯の誠実な友となった。そのほか、同じく神学校の仲間で、家を持たないシューベルトを自分の家に同居させたり、生活の面倒を見たフランツ・ショーバー、画家で、シューベルトの肖像画を数多く残したモーリッツ・フォン・シュヴィント、数年間の同居生活を通じて、シューベルトがその多数の詩に作曲をした詩人ヨーハン・マイルホーファー、音楽家のアンセルム・ヒュッテンブレンナーなど仲間が多かった。その一人ショーバーが、当時、非常に有名だったウィーンの宮廷歌手ヨーハン・ミヒャエル・フォーグルを、自分の家に連れて来て、シューベルトに引き合わせることに成功した。フォーグルは始めはそっけない態度を見せていたが、彼の歌曲の二つ三つを歌ううちに、次第に表情が変わってきて、別れ際にはシューベルトの肩を叩いて「あなたは素晴らしい才能を持っている」と励ましたという。それ以来、フォーグルはシューベルトの歌曲をウィーン中に広めようと、積極的にいろいろな場所で歌うようになり、作曲家シューベルトの最も価値ある「伝道師」となったのである。そして、フォーグルはシューベルトの友人たちの集まりに参加しては、彼の作品を次から次に歌い、この仲間はどんどん数を増やしていった。この集まりは「シューベルティアーデ」と呼ばれた。フォーグルは、シューベルトより29歳も年上で、音楽家としても遥かに有名であったが、シューベルトが集まりの約束を忘れて来なかったときには、「我々は、彼の天才に敬意を表して、這ってでも彼の後を追うべきだ」と言ったという。さらに、フォーグルは、シューベルトの作曲に関して好意ある助言をするなど、精神的・芸術的援助を行った。それのみならず、当時は作曲だけの収入は極めてわずかだった貧しいシューベルトのために経済的援助を与えたことも多く、第二の父親のような存在であった。
シューベルトが20歳の頃、友人ヒュッテンブレンナーの紹介により、彼は、ハンガリーの貴族エステルハージー伯爵に招かれ、二人の令嬢の音楽教師を勤めることになった。勤めていた小学校の校長である父親から長期の休暇を貰って伯爵家に赴いた。ハンガリーがすっかり気に入った彼は、伯爵家に長居をし、休暇期間をとっくに過ぎてからウィーンに帰ったため、父親の怒りを買って、遂に教師を辞めることになった。父親の家を飛び出してしまった彼を、ショーバーが自宅に引き取り同居させたが、このときから彼は生涯一か所に落ち着くことがなく、マイルホーファー、シュパウン、そしてまたショーバーの所へと、友人たちの家を転々とする生活を続けてゆくのである。彼の目的は音楽に没頭することで、その外の事には一切欲がなかった。生涯において、彼はいくつかの小旅行を除いてはほとんどウィーンの外へ出ることはなく、総じてその生活は非常に単純なものであった。朝起きると、9時頃から数時間は作曲に打ち込み、午後は友人たちと散歩をしたり、カフェーやレストランに行ったり、夜はそのまま飲食、歓談に興じて、遅くまで過ごすという日々が繰り返された。こうした交友の場において数々の歌曲が生まれた。友人が作った即興の詩に、あるいは誰かが持って来た詩集の中の詩に、彼は即座に旋律をつけ歌って聞かせた。そのようなときに、五線紙がないことがしばしばあり、友人たちが急いで有り合わせの紙に五線を引いて彼に手渡すのであった。親友のシュヴィントは、後年、ドイツロマン派絵画を代表する画家の一人と目されるほどの大家になったのであるが、「シューベルトに五線を引いてやったことが、自分の仕事の中で一番価値のあるものだった」とよく述懐していたという。
あるきっかけから、シューベルトは、名歌手フォーグルのように、彼の人生に大きな影響を与えることになる知己を得た。それは、熱烈な音楽愛好家であったウィーンの弁護士イグナーツ・フォン・ゾンライトナーという人物であった。彼は沢山の音楽家を知っており、度々コンサートを主催していたが、そこでシューベルトの多くの作品を演奏させたのである。このコンサートにおいて有名な「魔王」が演奏されたところ、大きな反響を呼び、これほど素晴らしい歌がまだ出版されていないことを聴衆は非常に不思議がった。そこで、それまで出版社に演奏が難し過ぎるという理由で出版を拒否されていた「魔王」が、ゾンライトナーを始めとする友人たちが費用を出し合い、出版社と交渉することによって、やっと印刷されることになったのである。その楽譜は飛ぶように売れた。ようやく彼の名はウィーンの上流社会に知られ始め、その名声は次第に広まっていった。シュパウンやショーバーたちの努力とフォーグルやゾンライトナーたちの協力によって、遂にシューベルトの音楽がウィーンやその他の都市で演奏されるようになったのである。しかし、彼の作品の楽譜をその価値に見合った金額で引き受ける出版社は存在しなかった。彼の音楽は極めて高尚で格調高く、時代に先行しており、その真価を理解できる人間はごく少数であったからである。それでも、シューベルトの歌曲を予約制で出版してはどうかという、ゾンライトナーの提言を受け入れる出版社も現れ始めた。この企画は成功し、シューベルトもまとまった収入を得たのだが、このようなお金はすぐに無くなってしまうのだった。彼にはまるで経済観念が無く、時折り手にするお金は、オペラ見物やコンサートの入場料に、あるいは友人たちとの飲食などに無頓着に消費されて、大体いつも彼は無一文だった。加えて、友人たちが嘆くほどの彼の無欲、無策による売り込み下手のために、後に傑作と呼ばれるような作品も、出版社に安く買い叩かれるのであった。シューベルトが遺した1000曲以上の作品の中で、わずか100曲ほどしか、彼が生きている間に出版されたり、演奏されたりしたものは無いであろうと、言われている。19世紀半ばを過ぎてから、彼の名作、大曲が発見されたことも少なくはない。例えば、有名な交響曲「未完成」が作曲されたのは、彼が25歳のとき、1822年であるが、その原稿は友人の机の中にしまい込まれたままになり、それが初演されたのは1865年のことであった。また、1825年に作曲された幻の交響曲と言われる「グムンデン・ガシュタイン交響曲」のように、原稿が失われてしまったものもある。
シューベルトの創作活動は、器楽曲、室内楽曲、交響曲、宗教曲、声楽曲など、音楽のほとんどあらゆる分野に及び、それぞれに名作、大作を残しているのだが、残念ながら、オペラについては際立って優れたものを生み出していない。彼は、オペラ見物が大好きで、特にモーツァルトのオペラの大ファンであって、当然、自身もオペラで成功することを夢見ていた。事実、彼は10数編のオペラを作曲しているのであるが、どの作品も失敗に終わり、彼をいたく失望させた。台本が悪かったからだとか、彼には演劇的才能が無かったからだとか、いろいろな理由が挙げられている。ただ、部分的には、「さすがはシューベルト」と思わせるような魅力的なアリアや間奏曲などが数多く含まれているのである。彼は、オペラ「魔弾の射手」を作曲した大作曲家カルル・マリーア・フォン・ウェーバーと良好な交友関係にあった。シューベルトがショーバーの台本に作曲したオペラ「アルフォンソとエストレッラ」をウェーバーも評価し、彼の指揮でベルリンの歌劇場において上演するという約束が取り付けられていたという。そのような折に、ウェーバーの新しいオペラ「オイリアンテ」がウィーンで初演され、そのとき彼はシューベルトに会ったのである。そこで、彼は、讃辞を期待して、新作オペラの感想を求めたところ、お世辞を言えないシューベルトの率直な言葉が返って来た。これはウェーバーの気持ちを傷つけることになり、シューベルトとの約束は果たされなかった。
ともあれ、彼の偉大さは歌曲にあった。名作の多い個々の歌曲や、「美しき水車小屋の娘」、「冬の旅」、「白鳥の歌」の三大歌曲集の素晴らしさは、今もって聴く人の感動を呼ばずにはいない。中でも、死の前年1827年に作曲された「冬の旅」は、ドイツ歌曲の最高峰として、現代に至るまで歌い継がれている。1827年3月、シューベルトにとって尊敬惜く能わざる大音楽家ベートーヴェンが死去した。これは、彼には大衝撃であった。折も折、同年2月には、彼は歌曲集「冬の旅」の作曲に取り掛かっていた。不治の病に侵されていたシューベルトは、その頃体調も思わしくないため、精神的に鬱の症状に見舞われ、「毎晩眠りにつくとき、二度と目が覚めないように願う」という内容の手紙を友人に送っている。自らの死を意識するようになった状況において「冬の旅」は作曲されたのである。同じ年の秋のある日、シューベルトはシュパウンに「今夜ショーバーの家に来給え。新しい連作歌曲を披露するから」と言った。友人たちが集まると、シューベルトは作曲を終えて間もない「冬の旅」(第1部)の全曲を心を込めて歌って聴かせた。それを聴いた皆は、その歌のあまりにも暗い雰囲気に驚き、絶句した。しばらくして、やっとショーバーが「良かったのは<菩提樹>だけだよ」と言った。シューベルトは「この歌曲集は僕の作ったほかのどの歌よりも気に入っているんだ。そのうちに君たちもこの歌が全部好きになるよ」と返した。その通りであった。後に「シューベルティアーデ」において、名歌手フォーグルがこの歌を感動的に歌うのを聴いて、彼らはこの陰鬱な曲集にすっかり魅了されてしまったという。
1828年8月頃、シューベルトはレルシュタープの詩による7つの歌曲とハイネの詩による6つの歌曲を作曲した。これらにザイドルの詩による1曲が付け加えられて、彼の死後「白鳥の歌」としてハスリンガー社より発刊された。これらがシューベルト最後の歌曲となった。ちなみに、「冬の旅」については、第1部は彼の生前1828年1月に出版されたが、第2部が出版されたのは彼の死の直後のことであった。同年9月、シューベルトはハンガリーへの小旅行の途中で体調を乱したのを機会に、次兄フェルディナントの家に引き取られた。彼は弟を母親のような愛情をもって看病したが、11月には、フランツは食物をほとんど受けつけなくなり、独力では歩けなくなってしまった。医者はおそらく腸チフスだろうと診断した。このような容態に陥っても、友人が見舞いに訪ねると、彼はベッドの上で「冬の旅」(第2部)の校正をしていたり、自分のオペラの計画を話して聞かせるのであった。以前から彼はベートーヴェンが死の1年前に作曲した弦楽四重奏曲を非常に聴きたがっていた。そこで、友人たちが手配した結果、その曲が、演奏家の手によって彼が寝ている部屋で演奏されることになった。彼はそれを恍惚として聴き入り、とても感動した様子であったという。これが彼が聴いた最後の音楽となった。その5日後、11月19日夕刻、フランツ・シューベルトは静かに息を引き取った。31歳の若さであった。彼は、彼が神のように崇拝してやまず、松明を携えて棺のそばに付き添いその葬列に加わった楽聖ベートーヴェンの墓の隣に埋葬された。その墓碑には、友人であった詩人フランツ・グリルパルツァーの次のような言葉が刻まれている。
「音楽は、ここにその豊かな財産と、より美しい数々の希望までをも葬った。」
ドイツの詩人、ハインリヒ・ハイネは、1797年12月13日、ライン川下流の町デュッセルドルフに生まれた。幼名はハリーで、後にハインリヒと改名した。両親はともにユダヤ人で、父ザムソンは布地を扱う商人であったが、商売に失敗し、1827年、窮乏のうちに死んだ。ライン地方は、フランス革命以後、フランス国の影響を強く受け、1813年までナポレオンに支配された。ナポレオンの新しい思想、政治の下で、この地域は封建ドイツの圧政から一時的にではあるが、解放されることになり、特に、虐げられていたユダヤ人は、多少なりとも恩恵に浴することになった。しかし、ナポレオンの没落後、1814年には有名なウィーン会議が行われ、ドイツは過酷な反動の時代に移ってゆく。1816年、18歳のとき、ハリーは父の弟であるザロモン・ハイネの許へ送られた。この叔父は、ハンブルクで銀行を営み、その地域の財界に重きをなす百万長者であった。やがて叔父の出資により、彼はハンブルクで「ハリ-・ハイネ商会」というイギリスからの輸入織物を取り扱う取次店を開設したが、すぐに破産の憂き目を見た。商売は彼の性格には全く向いていなかったのである。この叔父には、ハリーよりも年下の二人の美しい姉妹があった。彼は姉のアマーリエに一目惚れしてしまい夢中になった。これは、彼にとっては痛切な生涯の恋となり、彼が歌った恋愛詩の多くはこのアマーリエを念頭に置いて作られたものであるという。例えば、それらは、詩集「歌の本」の中の「若き悩み」、「抒情挿曲」、「帰郷」などに多く見られる。ところが、彼女は始めからハリーに冷たい態度で接し、彼の愛を拒絶したのである。そして、彼女は財産家の地主と婚約してしまった。ハリーは大きな衝撃を受け、強烈な挫折感を味わった。悶々として過ごす日々を送ったが、彼はアマーリエを決して恨まず、彼女への思いは終生変わることなく、その恋情を詩に歌い続けた。
1819年秋、ハリーはもう商売もアマーリエも諦め、法律を学ぶため、ボン大学に、次いで翌年ゲッティンゲン大学に入学した。その学費、生活費、旅費などはすべて叔父が出してくれた。このように、叔父ザロモンはことあるごとに、常に彼に対して経済的援助を惜しまず、できるだけのことをしてくれたのだった。この叔父の助けが無ければ、後の大詩人ハイネは生まれなかっただろう。しかし、当初は、叔父はハリーの文才を全く理解しなかった。彼がアマーリエに会うことを非常に嫌っていたし、彼をまるで無能なろくでなしのように扱うのだった。ハリーにとっても、叔父はありがたいけれども煙たい存在で、決して好いてはいなかった。後年、彼は「ドイツ冬物語」の中で、叔父についての思い出として、「あの高潔な老紳士にもう一度<この馬鹿野郎>と怒鳴られてみたい。その声が今でも僕の耳に音楽のように残っているのです」と、皮肉とユーモアを交えた調子で書いている。ハリーが詩人として名を成してからは、さすがに叔父も彼の価値を認めたらしい。それでも、ハリーが叔父の金を使い過ぎて散々に叱られることもよくあって、そのようなとき、彼は「ねえ叔父さん、あなたの一番いいところは僕と同じハイネという名前を持っていることなんですよ」と憎まれ口を叩くのだった。この叔父もかなりの皮肉屋だったとみえて、彼はハリーへの手紙の宛書に「私の一番いいところは自分と同じ名前を持っていることだと思っている男へ」と記し、末尾には「有名な詩人と同じ名前を持つ叔父ハイネより」と書くのであった。
大学では、法律学にはほとんど興味を持てなかったハリーは、文学や歴史の勉学に熱中し、それまで書き溜めていた詩集の処女出版を試みたが、不首尾に終わった。ゲッティンゲン大学では、彼はユダヤ人であったために、学生組合を除名され、それが原因で、一学生に決闘を挑み、その事件により大学から半年間の停学処分を受ける始末となった。そこで、彼はドイツ第一のベルリン大学に転入学し、心機一転、学問と芸術に取り組んだ。多くの優れた教授たちの中でも、とりわけ大哲学者ヘーゲルの講義は、ハリーに強い刺激を与え、その後の彼の思想に大きな影響を及ぼした。また、当地の有力者や活躍中の文学者らの知遇を得て、大変良好な文学的環境に恵まれた。そして、初めて「詩集」をベルリンの書店から出版した。これは後の「歌の本」の始めの章「若き悩み」に当る。また、「歌の本」の別の章「抒情挿曲」を書き始めた。後年、この中から16編を選びシューマンが美しい歌曲集「詩人の恋」を作曲することになる。異郷ベルリンの慣れぬ生活によってハリーの健康は損なわれ、1823年春、大学を中退し、当時リューネブルクに住んでいた両親の許に帰った。その後、彼は、叔父ザロモンの経済的援助を求めるため、辛い思い出の町ハンブルクへと赴く。そして、法律学の勉学を続けるため、叔父の援助の了承を取り付け、夏には北海沿岸の町クックスハーフェンで休養するための費用まで都合して貰ったのである。彼にとっては海辺の生活は初めての経験だった。ここで、彼の海を題材とする詩が生まれ、「歌の本」の「帰郷」や「北海」の章の中にとり入れられることになる。彼は海を詠んだドイツで初めての詩人であった。
ハリーは1824年1月、ゲッティンゲン大学に再入学して、今度は法律学にまじめに取り組む学生生活を送った。同時に詩作も続けられてゆく。この年、彼はヴァイマールにゲーテを訪問したが、深い尊敬の念を抱いていたにも拘わらず、このときは良い印象を持てなかった。翌1825年、法律学の学位審査をにめでたく合格し、大学を卒業した。卒業の前に、ハリーはハイリゲンシュタットにおいて洗礼を受け、プロテスタントに改宗することとなったが、このとき名前をハインリヒと改めた。この改宗は就職など社会生活を有利にするための方便であった。弁護士を開業する意志も持っていたようである。他方、文学活動も続けられ、1826年には、「帰郷」、「北海」、「ハルツの旅から」を含む詩集「旅の絵第1巻」が、ハンブルクのカンペ社から出版され、一躍ハインリヒ・ハイネの文名は上がった。続いて、「旅の絵第2巻」が公刊されるが、その内容に教会や貴族、政治や社会への批判が含まれていたため、世評騒然となった。結局、この書は、ハノーファー、プロイセン、オーストリアにおいては発禁処分とされた。この頃からハイネの、思想家、ジャーナリストとしての活動が始まり、彼の政治批判、社会批判が次第に強まってゆくのである。一方、1827年10月、ハイネは、それまでの詩、すなわち、19歳頃からおよそ10年間に書き上げた詩を集大成し、詩集「歌の本」として、ハンブルクのカンペ社から出版した。このドイツ文学史上不朽の傑作に対し、カンペ社はわずかな印税しか支払わなかった。
ハイネは、記事執筆の契約を結んだ出版社に招かれ、ミュンヒェンに赴いた。ここで、彼はバイエルン王の宮廷に仕えるか、あるいは、ミュンヒェン大学教授の職を得るか、手を尽くして就職活動を行った。しかし、彼に敵対する勢力の強い妨害によって、いずれも成功しなかった。失意のハイネの、敵に対する憎しみと罵倒は激しさを増し、また、彼の社会・政治批判の過激な記事は留まることなく、物議をかもし続けた。やがて彼は、身辺に危険を感ずるようになり、遂に、意を決した彼は、1831年5月、祖国ドイツと決別し、パリに向かった。事実上の亡命である。そして、生活費としては年金の形で、保護者としてこの上ない存在のザロモン叔父から定額の送金を受けることになったので、暮らしに困ることはなかった。当時ブルジョワ文化華やかなパリの優雅で自由な生活は、ハイネに大変心地よく、上流の社交界に出入りするようになった。パリでも、ハイネの名はよく知られていたのである。彼は、バルザック、ユゴー、ジョルジュ・サンド、デュマ、ベルリオーズ、ショパン、リスト、メンデルスゾーン、マイヤーベーアなどの名だたる文学者や音楽家、その他有力な財界人など多くの名士と多彩な交際を楽しんだ。他方、彼はパリの地よりドイツの新聞、雑誌に寄稿し、祖国プロイセンの政治批判を行い続けた。当時のプロイセン政府は、封建ドイツの反動政治に戻り、民権を圧迫、言論の自由を束縛していたからである。
パリに移って3年ほど後、ハイネは19歳も年下の靴屋の売り子マティルドを知り、二人の同棲生活が始まった。詩人ハイネと全く教養のないマティルドとは、およそ考えられぬ組み合わせであった。事実、じきに二人は別れてしまい、長い間会わなかったこともあったが、結局はよりを戻してしまうのである。彼女はハイネに幸福より不幸をもたらす方が多い女であった。彼女の浪費癖は凄まじいものだったが、それに対する彼の態度は恐ろしく甘かった。そのため、ハイネは多額の借金を背負いこみ、困窮に追いこまれるが、それから逃れるために、詩人は自分の全著作の版権をカンペ社に安い金額で売り渡したこともあった。しかし、このような状態であっても、彼らは別れることができず、何年か後には正式に結婚してしまった。この夫婦生活はハイネの死まで続く。彼は彼女を嫌悪しながらも熱愛し続けたと言えるだろう。彼の作品に「夜の想い」という美しい詩がある。「夜にドイツを思えば、眠ることができず、熱い涙が流れ落ちる」という詩句で始まるのであるが、この詩の最後の部分は「美しいフランスの朝のような妻がやって来て、その微笑にドイツの憂愁は消えてゆく」となっている。この妻というのはマティルドのことである。
1835年、ドイツ連邦議会はそれまでドイツの政治批判を行っていた青年ドイツ派作家の著作の出版禁止を決議した。絶えざる政府糾弾を続けていたハイネはその代表と見なされた。彼はすぐに祖国への忠義を誓い、この決議案の撤回を求める嘆願書を提出した。このような彼のご都合主義はよく見られるものであった。一方、ハイネの周囲の人物への手当たり次第の誹謗、嘲笑は止まず、敵の数は益々増えていった。あるとき、ハイネは、知人の三角関係を記事にして暴露した。侮辱されたその男に決闘を挑まれる騒ぎになり、実際にピストルによる撃ち合いが行われた。相手の弾丸はハイネの体をかすめ、ハイネは空に向けて発射し、二人とも事なきを得たのだった。そしてまた、別の話であるが、シューマンは若い頃、既に名声が上がっていたハイネを大変に尊敬し、ミュンヒェンまで足を運んで、彼に面会したことがある。彼はかなり年下のシューマンに対して、余裕を持って接し、励ましの言葉をかけたという。シューマンはこの詩人に対する崇敬の念を持ち続け、彼の詩による歌曲を50数曲も作っている。ところが、ある時から、突然ハイネの詩への作曲をぴたりと止めてしまったのである。それは、ハイネが、シューマンの親友である作曲家メンデルスゾーンを、例によって、非難、攻撃したため、シューマンのハイネ熱がすっかり醒めたからであろうと推測されている。メンデルスゾーンも有名な「歌の翼」を始めとして、ハイネの詩による歌曲を作っているのであるが。
ハイネ40歳の頃、流感に感染し、また、ひどい眼疾を患った。それ以来、彼は身体に変調をきたすようになり、もともと頭痛持ちであったことも加わって、度々病の床に臥すようになった。そのうち、左半身の感覚が麻痺し始め、視力も衰弱してきたが、小康状態を得たので、実に12年ぶりにハンブルクに帰った。1843年10月のことであった。感慨深い帰郷ではあったが、プロイセンの土地は通れないので、遠回りをしながら、ブレーメンから船に乗り、ハンブルクに上陸した。母や妹、それにザロモン叔父に懐かしの対面をした。また、カンペ書店にも掛け合い、印税支払いの契約をしっかり取り付けた。ハイネはこのときの体験を後に「ドイツ冬物語」として発表する。12月には彼はパリへ帰った。翌1844年、詩人のパトロンであったザロモン叔父が死んだ。彼からの年金を長年受けていたハイネは、遺産相続者の従弟にその後の年金受給を請求したが、拒否された。そこで彼はいろいろな友人知人を動員して、長期にわたり要求を続けた。従弟を非難する文を新聞に掲載するというお得意の手まで使って、この醜い争いは翌年まで持ち越される。その間、ハイネの病状は進行し痩せ衰え、それを知った従弟は、今後は自分たちの事を記事にしないという条件つきで年金の継続を了承した。しかし、彼の容態は悪化の一途をたどり、病臥したままという有様になった。一説には、この病気は結核性脊椎カリエスではなかったかと言われている。以後8年間、彼が名付けた「しとねの墓穴」の生活が死の時まで続くことになる。肉体的には、生ける屍のような状態であっても、文学に関しては、この詩人は異常なほどの輝きを放ち始めた。口述筆記で最後の大詩集「ロマンツェーロー」(バラード集)を書き上げ、その原稿をカンペに見せたところ、彼はその出来栄えに驚嘆し、早速彼の書店より刊行することになった。この詩人会心の作は大好評を博し、短期間に4版を重ねた。その後も、瀕死の病床で、「流謫の神々」、「ルテーツィア」、「雑録」3巻、「告白」、「回想」などの傑作を次々に生み出した。彼が病床にあった頃、故国から友人がハイネを訪ねて来て、「ローレライ」や「君は花のごと」など彼の詩に作曲されたものが、ドイツ全域でまるで民謡のように歌われていることを知らせると、彼はことのほか喜んだという。また、その頃には、彼は自分の詩に作曲したシューベルトの名もよく知っていて、偽のシューベルトが現れたことに憤慨する文章を残している。長い期間を「しとねの墓穴」に呻吟しながら、超人的な精神力でもって耐えてきた詩人も、遂に力尽き、1856年2月17日、永眠した。享年59であった。彼の遺言により、遺体はパリのモンマルトル墓地に埋葬された。
今から200年余り前、死を間近に控えたシューベルトが、出版されて間もないハイネの「歌の本」を、たまたま手に取って、その中の6編の詩に一種の霊感を覚え、まさに入魂の歌曲を作り上げたことは奇跡でなくて一体何であろうか。同年生まれのこの二人は、互いに遠く離れた地に暮らしていたために、直接会ったことはないが、このような形で一期一会の巡り合いをした。この奇跡の6曲は、いつ作曲されたのか詳しくは分からないのだが、シューベルトの死の年1828年8月頃とされている。また、同じ年、シューベルト畢生の大作「冬の旅」の最後の数曲と同時期に作曲されていたこともあり得る、という説もある。この説は極めて興味深い。なぜならば、この6曲の中には、「冬の旅」の情景や心情を連想させる曲がいくつか存在するからである。それにしても、この6つの珠玉のような歌曲の作曲についての詳しい経緯を誰も知らなかったということは、大変に神秘的である。しかし、次のような話もある。シューベルトの死の年の1月末、いつのことか正確には判明しないが、ある日朗読会が行われて、出版後間もないハイネの「歌の本」が取り上げられ、朗読されたのである。その会に出席していたシューベルトは、その本を借りて持ち帰った。これこそがシューベルトとハイネの詩の初めての出会いであった。シューベルトの友人で、美しいテノールの声を持つ歌い手であったシェーンシュタイン男爵という人物がいる。この人がある日(それがいつだったのか全くはっきりしていない)シューベルトの住まいを訪ねると、机の上に一冊の本が置いてあった。それがシューベルトが借りてきたハイネの「歌の本」であった。シェーンシュタインがそれを少し読んで気に入り、「貸してくれないか」と頼むと、シューベルトは「いいよ、それは僕にはもう必要ないから」と言ったというのである。彼が自宅にその本を持ち帰って頁を開いて見ると、シューベルトが選んだ6編の詩の箇所に印がつけてあったという。もうその時には、この6曲の作曲は終わっていたのであろう。この話が本当だとしたら、なぜシューベルトはこの6編以外の詩に興味を持たなかったのであろうか。ほかにも彼が注目するような詩が沢山含まれていたはずなのに。「歌の本」は大部な本であるから、短時間でこの本の全体に目を通すのは難しいことであるし、しかも、その当時は、シューベルトは大作「冬の旅」の作曲あるいは校正に重点的に力を注いでいたと思われるので、ほかのことにあまり多くの時間を割くことができなかったのかも知れない。
この6編の詩はすべて、「歌の本」の「帰郷」の章中に見られるのだが、ハイネ27~8歳頃の作品である。各詩には題名がつけられてなく、楽曲中の並び順は詩集中のそれを全く無視したものである。「白鳥の歌」におけるこの6曲は、第8曲から第13曲までに配置されていて、シューベルトがつけた題名は、その並び順に「アトラス」、「彼女の絵姿」、「漁師の娘」、「都会」、「海辺にて」、「影法師」であるが、これらのほとんどに、ハイネの永遠の恋人アマーリエの影が直接的あるいは間接的に映し出されているのである。例えば、「彼女の絵姿」は、彼が恋人アマーリエの肖像画に見入って涙を流しながら嘆く歌であり、「都会」は、アマーリエを失った痛切な悲しみを歌っている。また、「影法師」は、ある月の夜、彼の分 身がアマーリエの住んでいた家を訪ねているのを彼自身が目撃するという不気味な設定となっている。「都会」と「影法師」の2曲には明らかに「冬の旅」に共通する雰囲気がある。また、「海辺にて」は、ハイネが北海沿岸の町クックスハーフェンで休養していたときの体験から生まれた詩で、恋人と浜辺で過ごしているときの情景を描いた非常にロマンティックなものである。シューベルトはこれに極めて美しく変化に富む旋律を付した。その原詩は下記のようなものである。ハイネがアマーリエとこのように行動をともにしたことはあり得ないが、彼女を意識してこの詩を読んでいたかも知れない。
|
Am Meer Das Meer erglänzte weit hinaus Im letzten Abendscheine; Wir sassen am einsamen Fischerhaus, Wir sassen stumm und alleine. Der Nebel stieg,das Wasser schwoll, Die Möwe flog hin und wieder; Aus deinen Augen liebevoll Fielen die Tränen nieder. Ich sah sie fallen auf deine Hand, Und bin aufs Knie gesunken; Ich hab’ von deiner weissen Hand Die Tränen fortgetrunken. Seit jener Stunde verzehrt sich mein Leib, Die Seele stirbt vor Sehnen; Mich hat das unglücksel’ge Weib Vergiftet mit ihren Tränen. |
海辺にて 海はいちめんに輝いていた 落日の光を浴びて; 僕たちは寂れた漁師小屋の前に座っていた ただ二人切り何も語らず。 ふいに霧がたちのぼり、潮が満ちて、 鴎があちらこちら飛び交っていた; 君の愛らしい目から 涙があふれ落ちた。 それは君の手の上に流れ落ち、 僕は君の前にひざまづいた; そして君の白い手から その涙を飲み干してしまった。 その時から僕の体は病み衰え、 心は憧れのため死んでしまった; きっとあの不幸な女が僕に 涙で毒を飲ませたに違いない。 |
ハイネの詩風の特徴は、機智に富んだユーモアや冗談、きつい皮肉や嘲笑、鋭い風刺や暗喩などが多用されていることである。それらが平易な言葉遣いと簡潔な表現のうちに散りばめられていて、それに気がつかなければ彼の詩は理解できない。しかし、いろいろな分野の知識がないと、それが分からないので、ドイツ語を母語とする人々でも彼の詩の真意を理解できないことが多いという。ハイネの表現は複眼思考的なので、彼の言葉通りに単純にその内容を受け取ってはいけない場合が多いのである。若いときは別として、作品の中で彼が上流階級の女性を純粋にありのままの姿で描写することはあまりなく、まじめにそのままを歌ったのは、あばずれ女や商売女だったという。また、ハイネの詩の他の特徴に、リズムと押韻がある。強音と弱音、長音と短音を巧みに組み合わせて配置し、彼独特のリズムを作り出している。彼の作品には4行詩が多く見られるが、押韻は交叉韻ABABや偶数行だけに韻を踏むXBYBの形が多い。上記の「海辺にて」はきれいな交叉韻を用いている。この詩は、絵のように美しい夕べの海の情景描写に始まり、極めてロマンティックな雰囲気のうちに進行してゆくが、そのつもりで読んでいると、最後の2行で拍子抜けするような思いにさせられる。これこそハイネ一流のユーモアあるいは冗談なのである。もっと深読みすると、この女(アマーリエ?)はうわべはしおらしく涙を流したりしているが、実は毒婦なのだと言っているのかも知れない。
次に、もう一つ「白鳥の歌」の第11曲「都会」を取り上げてみよう。非常に独創的な素晴らしい歌曲である。静かにささやくように朗誦風に始まり、終節で作者の悲痛な嘆きを劇的に表現している。ピアノ伴奏も特徴的で、風やさざなみを思わせるアルペジオが何度も繰り返される。シューベルト以前には、このような歌曲は全く存在しなかった。彼の歌曲の最高傑作の一つであろう。原詩は次の通りである。
|
Die Stadt Am fernen Horizonte Erscheint, wie ein Nebelbild, Die Stadt mit ihren Türmen, In Abenddämm’rung gehüllt. Ein feuchter Windzug kräuselt Die graue Wasserbahn; Mit traurigem Takte rudert Der Schiffer in meinem Kahn. Die Sonne hebt sich noch einmal Leuchtend vom Boden empor, Und zeigt mir jene Stelle, Wo ich das Liebste verlor. |
都会 遥かなる地平線上に あの町が尖塔とともに見える、 黄昏の薄闇に包まれて、 霧の中に幻影のように。 湿った風がしきりに吹いて ほの暗い水面を波立たせる; 悲しげな調子で漕いでいる 私が乗る小舟の船頭も。 陽よもう一度昇ってくれ 大地より輝きながら、 そして私が最愛の人を失った かの町を照らして見せてくれ。 |
始まりの1節は、まるで、黄昏どきの町の遠景を描いたモネの絵のようである。この町というのは、ハイネにとって辛い思い出の町ハンブルクなのだ。彼の乗った小舟は夕暮れのエルベ川を下り、ハンブルクに向かっているところである。第3節が、愛してやまぬアマーリエを失った悲しみを爆発的に表現している。曲では、最終行の“Liebste”が最高音のフォルティッシモで絶叫的に歌われ、彼の悲痛な思いが強調されている。ついでに、最終行の“das Liebste”に注目してみよう。これは中性形である。ところが、これは「最愛の人」という意味であり、アマーリエを指しているのであるから、本来は女性形“die Liebste”でなければならない。それにも拘らず中性形を使用しているのはなぜであろうか?ハイネにとって最愛の恋人であった彼女は、彼がこの詩を詠んだ頃には、もう女性とか恋人の域を脱して愛の象徴のような存在に昇華していたのではないかと推測される。それゆえに、女性形ではなくあえて中性形を用いたのではないだろうか。また、この詩は、ハイネが舟でハンブルクの町に向かっているときのものだということになっているが、逆の解釈はできないのだろうか。つまり、この詩は、彼が失恋の痛手に耐えかねて、ある日の夕暮どき小舟に乗って、町を立ち去り旅立つときのものであるという解釈である。そうすると、これは、まさに「冬の旅」の第1曲に相通ずる情景である。ただし、雪は降っていないが。そしてまた、次のような考え方もある。最終行の“verlor”は「失った」という意味であるが、読み手が先入観なしにこの詩を読んだとき、これを「失恋で失った」のではなく、「死んで失った」と解釈するならば、この詩の悲哀の度合いがより一層増し、極めて悲痛な印象を与えるに違いない。もともと、この詩を読む者が作者の恋愛の具体的な事情を知っているとは限らないので、読者は自由に解釈してもよいはずである。シューベルトも、ハイネの恋愛事情など知る由もなかったのだから、この個所を「死んで失った」と解釈して作曲したかも知れないのである。
シューベルトの生前、誰の目にも触れず、誰の前でも演奏されることなく、机上に積まれたまま忘れられていた、この上なく美しいシューベルトとハイネの6つの歌曲が、彼の兄によって発見され、世に出たことはまことに喜ばしい限りである。この作品に接するとき、これら6つの歌は、二人の天才が互いに他をより豊かにし、高め合い、見事な結実を見せた数少ない例であると思わずにはいられない。
参考文献
この記事を書くに当り、参考にした書物は20冊余りになるが、その中で特に頻用させて頂いたものを挙げておく。
マルセル・シュナイダー著「シューベルト」(城房枝・桑島カタリン共訳) 芸術現代社
リチャード・キャペル著「シューベルトの歌曲」(服部龍太郎訳) 音楽之友社
オットー・ドイチュ編「シューベルト 友人たちの回想」(石井不二雄訳) 白水社
井上正蔵著「ハインリヒ・ハイネ」 岩波書店
舟木重信著「詩人ハイネ」 筑摩書房
万足卓著「ハイネの詩」 社会思想社
(平成30年2月14日脱稿)